�@�m�{�Ƃ̐����n�@�@�@�@�@�@�@�g�D���Q�[�l�t��ǂށm�����e�n
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�D���Q�[�l�t��ǂށ@�����ɏA����
�@
�@���̕��͂��������̂́A�z�[���E�y�[�W���n�߂ĊԂ��Ȃ�2010�N�t�̂��Ƃ������B���̍ہA�����Ō��y�����A�A�����E�g�����C���w�g�D���Q�[�l�t�`�x�i�s��T���q��@2010�N�@�����Ёj�����̉āA�ǂݏI�����B���̂��Ƃ����̕��̖͂��ɒNjL���A���e���ēǂ��������������B
�@�z�[���y�[�W�Ɍ��J�������͂��݂�����ēǂ���ꍇ�A�킽���̓E�G������_�E�����[�h���v�����g�A�E�g�������ʂ�ǂށB��NPC�̌̏Ⴊ�����Ĉȗ��A����܂ł̃t�@�C����PC�̒��g�͐s�������A���낤���ăE�G����ɃA�b�v���Ă������z�[���y�[�W����A���̕��͂��N�������B���݁A����ꂽ�t�@�C���́A�ăt�@�C���������z�[���y�[�W���v�����g�E�A�E�g����������Ł@�ۊǂ��邱�Ƃɂ��Ă���B
�@��������z�[���y�[�W�́A�ҏW�������ʂƈقȂ�B���p�ȂǏ��������f����Ȃ��B�����ʼn�����Ƃ����A�����Ƀg�����C���w�g�D���Q�[�l�t�`�x��ǂ����������邱�Ƃɂ����B�����Ƃ��u�����v�ƌ����Ă��A����̒����ɂ��A�ǂ݂₷���\�����������ɗ��߂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@
�@�g�D���Q�[�l�t�ƌ����A���V�A�̍�Ƃ��䑶�����낤���B�C�����E�Z���Q�[���B�b�`�E�g�D���Q�[�l�t�́A1818�N�A���{�̔N���ŕ������N���܂�B1883�N�A����16�N65�A�p���x�O�ŖS���Ȃ��Ă���B�ނ���{�ł͒��炭�u�c���Q�[�l�t�v�ƕ\�L����ė����B�ނ͈ꎞ���u���̏����̌|�p�I�\���A�d�����Ɣ������̓_���猾���āA�����炭19���I�ő�v�iP.�N���|�g�L���j�Ƃ܂ŕ]�����ꂽ�A���V�A��Ƃ��B
�@���V�A���w�ƌ����A�h�X�g�C�F�t�X�L�[�Ƀg���X�g�C�ƌ����A��勐�����ނ��Ă���B���̍�Ƃ́A�e�������Ȃ肪�����B70�N�㍠�܂Łi�H�j�g�D���Q�[�l�t�ƌ����A�������I���݊������Ȃ��������A���V�A���w�ƌ����Έ킷�邱�Ƃ̏o���Ȃ���ƂƂ��āA��N�w���琬�l�܂Œm���Ă����B�w�����x�ƌ��������́A���q�����e�̎Ⴂ���l�ɗ�������Z�҂��B�ŋ߁A�V�����o���B�w�l���L�x�w���Ǝq�x�́A���݂����ɖ{�œǂ߂�B�ǂ��Ƃ������Ƃ��A���̖��O���炢�́A���ɂ̔w�\���Ɍ����L��������̂ł͂Ȃ����B����ꐢ��ɂ́A�g�D���Q�[�l�t�̑��݂́A�ǂ��m���Ă����B
�@
�@60�N��㔼�w�M���̑��x���f�扻����A�b��ɂȂ������Ƃ��������̂��B�����̃\���B�G�g�A�M�́u������v�ƌ����āA���ɂ��Ďv���Ζ��������₩�Ȃ��̂��������A���R�����n�܂��Ă����B�f��ɂ����̒����ĂƂꂽ�B�f�扻���ꂽ�w�M���̑��x�́A���̐�삯�ƕ]������Ă���B����œ����A�g���X�g�C�̋��҂𒉎��ɉf�扻�����w�푈�ƕ��a�x���A�����O�E������f����Ă����B
�@���̑��ɔ䂵�w�M���̑��x�́A�@���ɂ����i�������B�����炱���A����̍s���͂����ӎ��������Ă����B�[������ɂ����f���ƌ����A�Ⴂ���ɗ�������v���M���̗J�������V�A�̖L���Ȏ��R��w�i�ɕ`���A���V�A���E�j���[�V�l�}�̑���I��i�Ƃ��čD�]���ꂽ�̂������B�����A�f�揭�N�������킽���ɂ��w�M���̑��x�́A�f���̔��������ۂ����āA����܂ł̃\���B�G�g�f��Ƃ̎�̈Ⴂ�́A��R�Ƃ��Ă����l�Ɋ�����ꂽ�B
�@���̍��A�����ƌܖ؊��V�����n�߂Ă����B���̌ܖ́A����c��w�I���ȏo�g�ƌ������Ƃ��m���Ă����B���������łȂ��A�G�b�Z�[��e���r�A�[��̃��W�I�ȂǁA�����͘b��ɂȂ��Ă����B�ܖ́w���ɐ�����āx�́A�����̎�҂̊ԂōL���x�����ꂽ�G�b�Z�[�W���B70�N��A���̕��ɖ{�́A��҂ɍL���ǂ܂�Ă����B
�@���̒��̈�͂ŁA���Ԃ��Ȃ����A�n�R�w���̒��ҁi�ܖj���A���ɍ���u�g�D���Q�[�l�t��i�W�v��m��Ȃ��Ö{���֔��蕥���b���������B�t�������̂Ȃ��Ö{���Ŗ{��B�{�́u�]���v�ɕs�����c��B�v�������A�s�����̌Ö{����l���炨������A���l��荂���l�i�Ŕ����߂��ƌ����b�ł������B�g�D���Q�[�l�t�́A�w�ɕ��͕ς����Ȃ��Ƃ��A�������₷����������Ƃł͂Ȃ����Ƃ��A�����ܖ�ǂގႢ�ǎ҂ɂ��A�����o����ʂɒm���Ă������ƂɂȂ�B
�@����ȉ���70�N������݂��炷��A�ڂ�ڂ₵�Ă���Ɣ����I���o�߂��悤�ƌ������̂ŁA�����ɂ��A����Ă��ē�����O�ƌ������ƂɂȂ�B�g�D���Q�[�l�t�̏������ǂ܂�Ȃ��Ȃ��Ă��A���̕s�v�c�ł��Ȃ����Ƃ́A�킽���Ƃďd�X�������Ă���̂��B�����炱���M���I�Ɍ���āiRhapsodize�j�݂����A�ƌ����z�����킽���̒��ɕ��X�ƗN���N����B
�@���́A����ȍ��Ԃ�C���ɂ�����ꂽ�̂ɂ́A���R������̂��B�ŋ߁A�Â����ɂŃg�D���Q�[�l�t�w�����n�x�i����F�q��@1974�N�@��g���Ɂj�|�ނ̍�i���ł����ҏ����|��ǂ�ŁA���Ȃ炸������������Ȃ̂��B�w�����n�x�ɏA���ẮA��قǏڂ������Ƃ��āA���������킽�����g�D���Q�[�l�t�ɋ��������������[���A�܂��͏q�ׂ����Ă������������B
�@���������̎n�܂�ƌ����̂́A��t���l���i1864�N�`1909�N�j��ǂ�ŗ������Ƃɂ���B��t���l���u�������āA���߂��v�łȂ���Ηm�H�X���̗l�ȁA���X�ގR�Y�����O�����]�ˊ��̋Y��҂ł͂Ȃ��B������Ƃ����ߑ㕶�w�̑n�n�҂̈�l�Ȃ̂��B����l�ɂ́A�g�D���Q�[�l�t�̕����A�܂������m���Ă���悤�Ɏv���̂����A�ǂ����낤�B
�@�킽���́A���N���̓�t���l�����h�����ė����B�ߔN������ɓ�t���Ɋւ��āA����܂ł̑z���͂ɂ��Ă݂����v�����Ƃ�����B���ꂪ����A���߂đS�W�̓ǔj�����݂�l�ɂȂ����̂������B��t���l���ɏA���ẮA������z���͂ɂ������B�ڂ����́A���̎��_���邱�Ƃɂ������B�����ł̓g�D���Q�[�l�t�Ƃ̊ւ��Ɍ����āA�ȒP�ɐG��Ă������Ƃɂ��悤�B
�@��t���́A�����Ō����ƌ������i1864�j�N�A���B�ˎm�̒��q�Ƃ��ĎY�܂ꂽ�B�N���������ɕς��������11�N�i1878�N�j15�A���R�m���w�Z������B�u�Љ�Ǝg�����̋����v����̎������B������ĎO���邪�A�s���i�B���ǁA�R�l�̓��͊���Ȃ��B
�@����14�N�����O����{�Z�I��Ȃɓ��w����B���V�A����U�����̂ɂ́A�����|���ɒ��N�ƌ����Ă��ǂ����낤�|���B�������ʂł̒鐭���V�A�Ƃ̐����I�ȋْ�������A�����������ۏ�ւ̍v�������]�����Ƃ����B
�@�@
�@���@���@�����O����w�Z�w������@�@�@�E�@���[��t���O����w�Z����1901�N��
�@�@�@

�@

�@�����O����{�Z�I��Ȃɓ��w���邱�Ƃɂ��A��t���́A���V�A�����ĕ��w�Ƃ̉����[�܂�B�����̊O����{�Z���A����ꂽ����Ɣ�r���Ă������̍���������{���Ă������Ƃ́A���Ɍ���Ă���B��t���́A�O����{�Z������18�N�i1885�N�j9���A�������ƛ{�Z�ƍ����ғ����ꂽ���N����ފw����܂ł̊یܔN�ԍݐЂ��A���V�A�l�����Ƀ��V�A����w��ł����B�����̂��Ƃ���A�������Ȍ�w�͂��}�X�^�[���Ă����Ƃ����B
�@����19�N�A�ؓ��ꡂ̒m���A�x�����X�L�[�̖|����n�߁A�S�[�S���A�g�D���Q�[�l�t�ȂǕ��w��i�̖|�n�܂�B��蕪���A�g�D���Q�[�l�t�̖|��ɂ́A�S���𒍂����B��A����̏����ɂ��A�u������v�v�̑n�n�҂Ƃ���Ă��邪�A����̍�i�ɔ䂵�Ă��|��̔�d�͑傫���B���̌�A��t���̃g�D���Q�[�l�t�|��́A���ؓc�ƕ���ɉe�����y�ڂ����ƂƂȂ�B���炭�A�킽���͓�t���ɂ��g�D���Q�[�l�t�����̖|��́w���ЁU���x�w�߂��肠�Ёx��ǂɉ߂��Ȃ������B��t�����g�̏����ɔ䂵�āA�ނ̖|��͓��ɒ��ڂ��ė��Ȃ������̂��B�����\���グ�Ȃ���A��t�����g�̎�v�ȏ����́A�͂��O������݂̂��B�|���i�Ɣ䂵�Ă����Ȃ��B�ŐV�̒}�����[�őS�W������ƁA��ꊪ�Ɏ�v�ȏ����ƒf�Зނ����^�������ɂ܂Ƃ܂��Ă���B��t���̏����݂̂�ǂނȂ�A���̑�ꊪ����ł��������̂������B�S�W�͈ȉ��A�|�����L�A���Ȃ������B�Â��|��̂��ߑS��������̂́A���S���ʂ̕��S�Ɏv�����B
�@��t���̖|��ɐϋɓI�S�����ĂȂ������C�����ɂ́A�g�D���Q�[�l�t���n�߁A��t���̖����V�A��Ƃ��A�킽���B����̓ǎ҂��牓�����݂ł��邱�Ƃ��傫���B�k�����J�́A����������20�N��A�p�ꂽ�h�X�g�B�F�t�X�L�[�Ɍ��y���Ă���B��t���̖|�u�h�X�g�B�F�t�X�L�[�Ȃ�܂������A���X�g�D���Q�[�l�t�ł��Ȃ��ł́A�Ȃ����I�@�v�ƌ����A�C���������������炾�B���鎞�A�g�щ\�Ȋ�g���X�őS9���̑S�W����肵�A�Q���������|����ǂނ��ƂƂȂ����B���^���ꂽ�������|���i���A�g�D���Q�[�l�t�w�������x�i����30�N�w���z�x�f�ځj�ƌ����M��Ŗꂽ�|���̏����́w���[�a���x�ƌ�������ŁA���a�̖�҂ɂ���ŁA��g���ɂɂ����^����Ă����|�́A�Q����g�őS�W�œǂނɋy�B���̏����́A�g�D���Q�[�l�t�|���i�Ƃ��ẮA��r�I���ҁA�ǂ݉����̂��鏬���������B�m���ɁA���݂���݂�ΌÕ��Ȗł͂���B���������ꂪ������ǂޏ�Q�ɁA�Ȃ��Ă͂��Ȃ������B��t���̖|���ǂނ��ƂŁA�g�D���Q�[�l�t�ƌ�������ł͌ڂ݂��邱�Ƃ̖����Ȃ��������Ƃ��A�ĔF������@��ɂ��Ȃ����̂������B
�@�����ŁA��t���l���ɂ��A�g�D���Q�[�l�t�̖|���i�������o���Ēu�����B
�@����21�N�i1888�N�j�w�����U���x�m�����V�F�n�w�߂��肠�Ёx�m�s�̉ԁn����29�N�i1896�N�j�w�М��x�|��W�w�М��x�i�w�М��x�w����x�w���ЁU���x�O�т����^�j���^��i�́A���o�Ƃ͎�قȂ�B����30�N�i1897�N�j�w�������x�u���z�v�f�ځB����41�N�A�P�s�{�Ƃ��Ċ��s�B����31�N�i1898�N�j�w�P���l�x�u�����V�F�v�w�����ꉏ�x�u���Y��y���v�Վ������f�ځB����34�N�i1901�N�j�w��������x�u���|��y���v�Վ������f�ځB����36�N�i1903�N�j�w���ӂ�x�|��ɒ���A���������B��L�̂����w�М��x�w�����ꉏ�x�Ɓw�������x�́A�V��ł��ǂނ��Ƃ��\���B���̑��͓�t���ȊO�̖�҂ɂ��|��́A���̂Ƃ���v������Ȃ��B���݂ł��A�܂Ƃ߂ăg�D���Q�[�l�t��ǂނȂ�A�悸��t���̖�œǂނ̂��A��߂ȕ��@�ƌ������ƂɂȂ�B
�@�w�������x��ǂ�A���ɖ��ǃg�D���Q�[�l�t�̕��ɖ{�����邱�Ƃ��v���o���āA�Â��V�����Ɂw���Ǝq�x�i�Đ쐳�v��j�����˂���o���ēǂB���̉��Ƃ��Z���`�����^���ȏ�����ǂݏI�������ɂ́A�g�D���Q�[�l�t�ƌ�����Ƃɑ���e�����Ƌ������N���N�������̂́A���Ȃ�������������B�����ŁA�V�����ɔŁw���Ǝq�x���u�Â��v�ƌ������̂́A���̕��ɂ͂킽�������Z��N�̎��ɍw�����A�����܂œǂ܂��A���˂Ŗ����Ă������ɖ{����������Ȃ̂��B���̍ۂ�����A�킽���̎茳�ɂ���g�D���Q�[�l�t�̖{�i���ɖ{�j�������o���Ă��������B�{�̃^�C�g���A��҂̑��ɔ��s�N���ƍ����܂ŋL�ڂ���̂́A�ǂ�ʓǂ܂�ė����̂���m��A�w�W�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���A�ς��}�͂������o���Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@�w�����т��E�߂��肠���x��t���l����@���a28�N���s�@���a44�N15�����Ł@���a45�N17���i�V�����Ɂj�w�З��E�t�@�E�X�g�x�Đ쐳�v��@���a27�N���s�@���a45�N22���i�V�����Ɂj�w�U�����x���R�ȎO�Y��@���a26�N���s�@���a43�N22���i�p�앶�Ɂj�w�n�����b�g�ƃh���L�z�[�e�@����сx�͖�^��ēc���O�Y��@���a30�N���s�@���a41�N5���i��g���Ɂj���̕��ɂ́A�|�ꂽ�g�D���Q�[�l�t�B��́i�H�@�����j�]�_�W�B�w���Ǝq�x�Đ쐳�v��@���a26�N���s�@���a45�N�@35���i�V�����Ɂj�w�����x�Đ쐳�v��@���a8�N���s�@���a35�N14�����Ł@���a50�N31���i��g���Ɂj�w�����n�x����F�q��@���a49�N���Ŕ��s�i��g���Ɂj�Â��|��̂͂����B�@�w�l���L�x�H������Y��@���a47�N���s�@���a49�N6���i�V�����Ɂj�����ɔN��������֗��A�w�����x�̐V�o��܂ŁA�ߔN�ł͍ł��V�����|��B���̕��ɂ́A��X�ג��̃��[�Y�h�{���œ��肵���{�B�Ȃ��A�����w�l���L�x���ȑO�́A�Đ��ŏ�E���œ����ɂɎ��^����Ă����B
�@�ȏオ�킽���̎茳�ɂ���g�D���Q�[�l�t�{�i���Ɂj�|���݂܂ł́|�S�Ă��B���ꂼ��ʂȖ�҂ő��̕��ɂɂ����^����Ă��āA�L���ǂ܂�Ă������Ƃ�������B�Ȃ��A�c�O�����w�M���̑��x�i�m���p�앶�Ɂj�́A��������Ȃ������B�܂��A����F�q��w���̑O��x�i��g���Ɂj���A�ȑO�Ö{���Ō������Ƃ��������B���̎��͋������Ȃ��A����Ȃ������B�����āA�ߔN�w�����x�̐V�o�����Ƃ́A���ɐG�ꂽ�B�g�D���Q�[�l�t��70�N��܂Ŕ�r�I�ǂ��ǂ܂�Ă������Ƃ́A�ȏ�m���t�n�̃f�[�^���痝�����Ă���������̂ł͂Ȃ����B�Q�l�����Ƃ��āA�B��A�A�C�U�C�@�E�o�[�����w���Ǝq�g�D���Q�[�l�t�Ǝ��R��`�҂̋ꋫ�x�|��ɁA�q�ׂ�|������B�ŋ߁A�o�������̂����A�s�S�̍ő�̕i�������ւ��^���X�́A�����ł͊e���ʂɕ��w��i�ƕ]�_�E�������̏��I����������Ă���B�����Ń��V�A���w�������̏��˂̑O�ɗ����A�g�D���Q�[�l�t�Ɋւ���{��T���Ă݂��B���ʂ̓[���������\���́A�A�x�����ɏ��X�̒I�̑O�ɗ����āA�������B�A�����E�g�����C�A�w�g�D���Q�[�l�t�`�x�������Ђ���|��o�ł���Ă����̂��B�g�D���Q�[�l�t�{�u0�v�ƌ����Ă������A�����ɗ��āu1�v�ƌ������ƂɂȂ����B�{�͍w�����Ă��Ȃ��̂ŁA���̕��͂ł͎Q�l�ɂ��Ă��Ȃ��B�\�i���j�B
�@�킽���B�̃��V�A���w�ɉ�����S�̈�ŁA���X�ɂ���̂̓h�X�g�B�F�t�X�L�[�ƃg���X�g�C�ȊO�A�`�F�[�z�t�̊֘A�����h�����Ă�����x�B�A�C�U�C�@�E�o�[�����w���Ǝq�g�D���Q�[�l�t�Ǝ��R��`�҂̋ꋫ�x�����݂͕i�ꂾ�|���݂Ƀl�b�g�Ō�������ƁA�w���\�|�B�o�t�`�[���̒����V�A�E�t�H���}���Y���̕��|���_���ǂ܂�A�\���B�G�g����ɂ́A����I�ȓǎ҂ɂ����b�܂�Ȃ����������i�w�v���g�[�m�t��i�W�x������@1992�N�@��g���Ɂj���|�ꂽ���݁A�g�D���Q�[�l�t�֘A�̖{���F���Ȃ̂��A����̕ω��̂����炵�߂�Ƃ���ƒ��߂���Ȃ��Ɗ�����̂́A�킽�����肾�낤�B�������A����Ȏ������A�l���Y��Ă���{�i�g�D���Q�[�l�t�̖{�j��ǂ݂��Ǝv��Ȃ��ł͂Ȃ��B
�@��قǁA�h�X�g�B�F�t�X�L�[��g���X�g�C���o���̂Ō����Ă����ƁA80�N��I��肩��90�N��̏��߂ɂ����āA�킽���Ƃ��Ă͐��l���ď��߂āA�������̍�i�ɐG�ꂽ�̂������B�h�X�g�B�F�t�X�L�[�́w�߂Ɣ��x��w���̉Ƃ̋L�^�x�ȂNJ���̏������A�Ⴂ�����ɓǂ�ł͂����B�����҂��W���I�ɓǂ̂́A�Q�����N���ɂȂ��Ă��炾�����B�N��I�ɂ͎Ⴍ�Ȃ������ɑS���҂�ǔj����@����������̂��B�����Ƌ����͌�������A����������g���ɔŁw��Ƃ̓��L�x���Z�b�g�ōw�������B�w�푈�ƕ��a�x�w�A���i�E�J���[�j�i�x�g���X�g�C�̓�咷�҂��A���̎����ɓǂB����ł��A���V�A���w�Â������́A�e�Ղɗ�߂�P�E�N���|�g�L���w���V�A���w�̗��z�ƌ����x�㉺�i������Y��@��g���Ɂj�w����v���Ƃ̐��U�x�A�`�F�[�z�t�w�T�n�������x�㉺�i�����Z��@��g���Ɂj�ȂǁA�ǂ��炩�ƌ����Γǂ܂��@��̑����Ȃ����w��i�ɂ܂ōL�������B���̒��AP�E�N���|�g�L���w���V�A���w�̗��z�ƌ����i�㉺�j�x�̌����́A�鐭����Ɋv���^����簐i���A��A�i�[�L�X�g�Ƃ��ă����h���ŖS�������𑗂����N���|�g�L���ɂ��A�ِF�̃��V�A���w�����B1905�N�ɏo�ł���A��g���ɔł�1916�N�V�ł����s���ꂽ�p��ł���|��B���V�A���w�j�������Ȃ��킽���ɂ́A�B��ŋM�d�Ȗ{�ƂȂ��Ă���B
�@���̖{�ŋ����[�������̂́A�����N���|�g�L����������l�Ƃ��āA�������͂��߂Ƃ������V�A��Ƃ�_���Ă��邱�Ƃ��B���ڂ��ׂ��́A�g���X�g�C�Ƌ��Ƀg�D���Q�[�l�t�̕]�����������Ƃ��B�������A������l�h�X�g�B�F�t�X�L�[�Ɋւ���L�q������B�������A�g�D���Q�[�l�t�ƃg���X�g�C��l���L�q�����͂́A���ɏ㊪�O���̈ꋭ�̃y�[�W���B���J�ɍ�i����_���Ă��邱�Ƃł�������B�ق��̍�ƂƂ́A�e�������Ⴄ�̂������B
�@�g�D���Q�[�l�t�̍�i�̈Ӗ���m�낤�Ƃ���ɂ́|�N���|�g�L�����������]�����悤�Ɂ|�w���[�W���x�w�M���̑��x�w���̑O��x�w���Ǝq�x�w���ނ�x�w�����n�x�̘Z�т��Â��ēǂ܂˂Ȃ�Ȃ��B�����̍�i��ǂ߂A�ނ̕��w�I�˔\�͊��S�ɗ����ł���B������ǂ߂A1848�N����1876�N�܂Ń��V�A�̒m�I���������ǂ����A��X���@���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���V�A�̗��j�I�����ɂ�����A�i���v�z�i�ߑ�ӎ��j�ɑ����҂̑ԓx�������ł���̂��B
�@
�@���̕��͂��������O�A�g�D���Q�[�l�t�́w�����n�x�Ɓw�l���L�x�̓҂�ǂB�h�X�g�B�F�t�X�L�[��g���X�g�C�A�����́w�T�n�������x�̃`�F�[�z�t�ƕ��ׂĂ��A���܂��ɐF�����Ȃ��݂��݂�������X������i�ł��邱�ƂɁA�^�Q�����B���̓�̍�i��ǂ�ŁA�킽���̃g�D���Q�[�l�t�̕]���́A����I�ɂȂ�A���㖢�ǂ̍�i��ǂދ@������Ă��A�ς�邱�Ƃ������Ɗm�M�����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�����n�x
�@
�@�w�����n�x�́A1877�N�i����10�N�j����59�̍�i�B�g�D���Q�[�l�t��1885�N8���ɖS���Ȃ�A���҂ɂ�鐬�n���̒��ҏ����ƌ������ƂɂȂ�B�����̓��e���ȒP�ɏЉ�Ă݂����B
�@��l���́A�l�W�_�[�m�t�\�u���҂���Ȃ��l�̈Ӂv�ƁA���ɂ���\�ƌ������̋M���̏��q���B���������̏o�����́A�y�e���u���O�̔ނ̕����֊��W�܂�A�s�s�̃C���e�����Y�K���|�Љ�ϊv�ւ̈ӎ��ƕϊv���i�܂Ȃ����Ƃւ̉���������Ă���l�X�|�̕`�ʂ��珑���N������Ă���B
�@���̓��A�l�W�_�[�m�t�̕����ɂ́A�������̗l�ɒj�����W�܂��Ă���B�ŏ��A�l�W�_�[�m�t�́A�s�݂��B����Ȓj���̒��Ɂu���ɏ�������Ȃ��A�����ѐD��̕��𒅂��v�����^�o�R���ӂ���30�Έʂ́A�^���̘A����I���݂Ńl�W�_�[�m�t�̕����ɏo���肵�Ă��鏗�i�}�V���[���i�j������B���̏��́A���������ӎ��������Đ�����^�C�v�̏����Ƃ��ĕ`���Ă���B���̏����ɂ́A�B����Ă͂��邪�����̐��������A�e�[�}�̈�Ȃ̂��B�`���Ɏ�l���ł��q���C���ł��Ȃ��A���i�̓ǂ߂Ȃ��������������̂ɂ́A���̏����̑_���i�e�[�}�j������ƂȂ��\�����Ă���̂��B�}�V���[���i�͍Ō�ɂ܂��o�ꂷ��̂ŁA�ǎ҂͓��̋��ɒu���Ă����Ăق����B
�@�`���̓��������ɂ���ė����A�l���ł�����lᰂ��炯�̊z�����āu�������̉����͒��F�̂����ւ����������������Ⴊ����A�@�͊��̚{�̂悤�ɏ�����Ɏ���������A�����ȃo���F�̌�����������Ă��v��A��i�т����j�̓����߂����j�p�N�[�������Љ���B����C�Ȃ��`����Ă���̂ŁA�ǂݎn�߂�����̓ǎ҂ɂ͕�����Ȃ����A�}�V�����[�i�ƃp�N�[�����́A��l���l�W�_�[�m�t�ƃq���C���i�}���A���i�j�ɑ��āA�ΏƓI�ȃL�����N�^�[�i�����ҁj�Ƃ��āA�Ή�����B�e���ł߂�l�����Љ�A�Q���l�W�_�[�m�t�������ɖ߂�B
�@�l�W�_�[�m�t�̂��Ƃɂ́A�^������݂̎����S�ɗ���҂�����B�l�̗ǂ��l�W�_�[�m�t�́A��������邱�Ƃ����B����Ȗ��A�l�W�_�[�m�t�ɂЂ��Ȃ��Ƃ���A�n���̑����ł̉ƒ닳�t�̌���������B�ǂ��b�ł͂��邪�A�n���֍s���Ɩʓ|�Ȑl�ԊW�Ɋ������܂�Ȃ��Ƃ������Ȃ��B�Ă̒�A���̌�l�W�_�[�m�t�́A�v�������Ȃ��s�������܂��邱�ƂɂȂ�B�l�W�_�[�m�t�ƌ����A�s��炿�ŐV��������̒j���ƒ닳�t�Ƃ��āA�����ɌĂ̂́A�̎�i�V�s���[�M���j�̌��h����ŁA�̎�̍ȃ������`�i���}���A���i�ɑΗ����Ă���B
�@�}���A���i�́A����̓��{�ň�ʓI�Ɍ����鎩���^�̏������Ƃ���A�������`�i�̕��́A�@���ɂ������ȑ��݁\�u��⍕�������F���̏��ŁA�V�X�`�i�̃}�h���i�̊�e���v�킹��悤�ȁv�\�ɕ`�o���Ȃ���u���ɗZ�ʂ̂����Ȃ���}�̏��R�ƁA�Ђǂ�������n��̂��܂��A���ςȏ����V�A���Ƃ̖��v�ŁA�T���ł͂Ȃ������̂ɁA����M�����w�Z�i�݁A���z�̗ǂ����肪����ɏ㗬�K���Ɏ�����A�㗬���Y�Ƃɍ��ꍞ�܂�Ȃ̍����l������̂ɐ�������B�������h�̋��������́A����ł��e�ՂɌ�����B�����̎��͂ɑ���x�z�~�̋����́A�����̃}���A���i�ɑ��ĘI�����B�G���̃L�����N�^�[���ۂ����Ă��邱�ƂŁA�}���A���i�̒u���ꂽ�ɋْ�����^���Ă���B
�@���̂ق��A�������ɓo�ꂵ�ė���l���ɁA�������`�i�̌Z�ŁA�}���A���i�ɋ�������}���P�[���t�A�ނ̗̒n���߂��ɂ���A�g�D����̘A�����l�W�_�[�m�t�Ɏ�莟�����肷��B�܂��A���̒n���̑g�D�̐��i���\���[�~���́A�_���ł͂Ȃ��H��Z�p�҂ŁA�p���Ŏd���������o��������B�l�W�_�[�m�t�͎���ɁA���̒n���Ŏ����Ɋւ��l���ɏo��B����ɂ������ȋύt���j���A����͎v��ʓW�J�����Ă䂭�B
�@���������l�W�_�[�m�t�̐��i���ڂ����q�ׂ�ƁA�@�ׂŐ_�o���Ȋ����́A��������̋M������̌��B�����ɍ��v�̎蒠�Ɏ����������߁A���F�ɂ͎���̐l����̐ߖڂ̕����˂ɓf�I����B����ȂƂ���́A���������̗D�����ƌ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����A�̎�̖ÂʼnƂɈ�������Ă���}���A���i�́A�������`�i�ɔ�ׂ�Ɓ\���u�قƂ�ǁe�s�|�k(�Ԃ���悤)���f�Ɍ������B�~����A�傫���h�@�A�\�\�D�F�̂�����傫���A�Ђǂ����邢��\�\�ׂ����A�ׂ��O�������Ă����B�ޏ��̓u�����h�̔Z�����̖т�Z�������Ă��āA�ЂƂ��������̂�邢���Ɍ����Ă����B�������A�ޏ��̑S�̂��炭�銴���ɂ́A���̋����E���Ȃ��钖�˓I�ȁA��M�I�Ȃ��̂��������B��Ƒ��͂܂�ŏ����������B��������Ƃ��Ȃ₩�ɂł��������ȑ̂́A��Z���I�̃t���[�����X�̏������v�킹���B�ޏ��͂���Ȃ�ƌy�₩�ɓ������B�v���\�ƕ\������Ă���B��i�ł́A�������`�i�̕������A���e�B�[������̂́A�����̏����̕��ՓI�Ȑ��i��t�^���Ă��邩�炩������Ȃ��B
�@�����āA�l�W�_�[�m�t�����ꂽ���Ƃɂ��A�n���̏����Ȑ��E�̋ύt���j���āA�l���e���̐��i�����炩�ɂȂ��čs���B����̓��V�A�̑�����ɁA�ꌩ�ɂ₩�ɓW�J���čs���B����ɁA�}���A���i�ƃ������`�i�̊W���ْ��𑝂��A�l�W�_�[�m�t����������Łu�삯�����v�i�W����B��x�́A�������A���邩�Ɍ����邪�A�l�W�_�[�m�t�ɂ́A�ӊO�Ȕj�ǂ��p�ӂ���Ă���̂��B�\���[�~���̋@�]�ɂ��A�u�삯�����v�����l�W�_�[�m�t�ƃ}���A���i�́A�\���[�~���ɓ�����l�̐l�����n�ߗl�Ƃ���B
�@����Ȗ��A�l�W�_�[�m�t�́A�}���A���i�ɑ��Đl���I�Ȉ��͂����Ă��A�ꏗ���ւ̈�����l�������Ɋ���������ӎu���Ȃ����Ƃ����A�������Ȃ��A���E���Ă��܂��B���E�܂ł̓W�J�͋}�ŁA���˂̊��͖Ƃ�Ȃ��B
�@�l�W�_�[�m�t�ƃ}���A���i�ł́A�����ƌ������A�l�W�_�[�m�t�̓}���A���i�Ɉ��������Ăƌ����̂��A�����j���̈��ƌ������A���u�Ƃ��Ă̐M���W�ɋ߂��̂ł͂Ȃ����B�l�W�_�[�m�t�́A������̃����S�̎��̍����ŁA��l�s�X�g���Ŏ���ɒe����������Ŏ��E���v��B����́A���������@���E�S�b�z�̎������v�킹�A������Â����ɂ͂����Ȃ��B�����̍Ō�A�}���A���i�́A�n�ɑ��̒����������҃\���[�~���́u�ȂƂȂ��čs���܂����c�@�v�ƁA����ďI���B���̌�ɁA�G�s���[�O���Ɉ�N�����o�߂����y�e���u���N�̑}�b���Y�����Ă���B
�@
�@������A�p�N�[��������������Ȃ�������Ă���ƁA�������V���̃}���g�𒅂����A�啿�̕w�l�Ƃ���Ⴄ�B�\���u�p�N�[�����͋C�ɂ����߂��A���S�������������̏��Ɍ������ē����A�C�ꂿ�����čs���߂����c�c���ꂩ��}�ɗ����ǂ܂�A�l�����݁A������Ђ낰���\�\�����Đ����悭�����߂��炵�A���̏��ɒǂ����ƁA�X�q�̉�������`�����B�v���\�ŏ��͂�Ȃ����Ă����}�V�����[�i�������B�p�N�[�����̌�����l�W�_�[�m�t�̖����o���̂ŁA�߂��̃p�N�[�����̕n�����A�p�[�g�܂ŕt���čs���C�ɂȂ�B
�@��l�Ƃ��A�l�W�_�[�m�t�̂��Ƃ��Y���ꂸ�ɂ��āA�b�����̎v���o����ɘb������B�p�N�[�����͖��Ɠ�l��炵�ŁA���̖����p�N�[�������m��Ƃ������o�̎�����ŁA�\���u��������߂āA���������������Ɣޏ��i�}�V���[���i�j�߂Ă���A�ޏ��̎���������\�\���ԂƂ��āB�v���\
�@
�@�e�����ŗ����ł��鏬�������邪�A�g�D���Q�[�l�t�̏����ł́A����̕���͌���I���B����̓W�J���傫���͂Ȃ��B�l�Ɛl�̔����ȊW�́uあ�v���X�g�[���[�̗v�ɂȂ�B�����Ȑ��x��̋M���Љ�ƁA����̕ω�������Ⴂ����ӎ��Ƃْ̋��ƍ��܂��`�����B�j���Ƃ��ɋ����ȎЉ�ւ̖��𗝉����Ă���B�ϊv�Ɋւ��āA�j�͉��a�A�����͕ω�������Ȃ��B�j���͐��i���ア�B�g�D���Q�[�l�t�̐��i���ʂ��Ă���l�Ɏv����B
�@�g�D���Q�[�l�t�̏����ɉߏ�ȁu�Z���e�B�����^���Y���v�́A���Ȃ̂��B�h�X�g�B�F�t�X�L�[�w�n�����l�X�x�w���̉Ƃ̋L�^�x�ȂǁA��N�̒��҂ɂ͉M���Ȃ��ߓx�ȃZ���e�B�����^���Y�����A�Ȃ������ł͂Ȃ��B�������A����̓ǎ҂ɂ́A�g�D���Q�[�l�t�́u�Z���e�B�����^���Y���v�ɂ́A焈Ղ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����ŏڂ����G��Ȃ����A���݂����ɖ{�ŗe�Ղɓǂ߂鏬���Ɂw���Ǝq�x������B�ȑO�A���̍�i��ǂہA�������̂́u�Z���e�B�����^���Y���v�̔Z�����|����ɂ͊�ȁ|�������B�w���Ǝq�x�́A�Ⴂ����́u�j�q���Y���v�ɂ�鐢��Ԃ̑Η��������̃��V�A�Љ�ɏՌ���^�����Ƃ���Ă���B�������A����̓ǎ҂ɂ́A�������V�A�Љ�ɗ^�����Ռ��̒��͑z���ł��Ȃ��B���ł͊��������肪��ۓI�������B�g�D���Q�[�l�t�����̃��V�A���w�Ɣ�r���āA�ǂ܂�Ȃ��Ȃ��Ă���B����́A�ߏ�ȁu�Z���e�B�����^���Y���v�ɁA���������̂ł͂Ȃ����낤���B�w�����n�x�̃l�W�_�[�m�t�������Ղ����i�ł͂���B����ł��A���E�͓��˂�����C�������B�������A���\�����A�c�_�Ɣᔻ���Ă̂́A���̂��Ƃł͂Ȃ������l���B���������c�_�́A��҂̕s���_�ł͂Ȃ��A�܂��č�i���ǂނɒl���Ȃ��ƌ������Ƃɂ́A������Ȃ��B
�@���������Ă�������Ȃ����낤�B��肠�����������ɖ{��ǂ�ŗ~�����B�V�����ꂽ�w�����x�́A�ǂ������m��Ȃ��B�g�D���Q�[�l�t�ƌ����A�ߋ��ɗǂ��ǂ܂ꂽ�̂ŁA��ʂɗ��z���Ă���͂����B�K����������o���邾�낤�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�l���L�x��ǂ�
�@
�@�w�����n�x�̓��e�Ŏ�Ԏ���Ă��܂����B��͂�A�L���ȁw�l���L�x�Ɋւ��āA�G��Ă��������B���݁A�����̕��X�́u���X�w�l���L�x�Ȃ�āA�ʔ����̂��v�ƁA�v�����Ƃ��낤�B���ꂪ�ǂ����āA�ǂݏo���Αދ����Ȃ��ǂ��납�u����u���\�킸�v�����I�ȏ����Ȃ̂��B
�@�w�l���L�x��1852�N�i�Éi5�N�j�g�D���Q�[�l�t34�A���V�A���d�ւ̃f�r���[��B�w�����x�w���Ǝq�x�ƂȂ��ŁA�g�D���Q�[�l�t�̏������A�ǂ��m���Ă����i����B
�@�\�u�ꔪ�l���N����ꔪ���Z�N�ɂ����ď����ꂽ��\��҂̒Z�҂����̒P�s�{�Ƃ��Ĉꔪ�ܓ�N�Ɋ��s����A�ꔪ���Z�N�̔łɂ͂���ɎO�҂�������ꂽ�B�Z�Ґ��Ƃ������́A�Ƒn�I�ȒZ���X�P�b�`�Ƃ������ׂ����́v�\�@�ƕ��ɉ���ɂ���B�@�u���V�A�̔_�z�v�ƈ���Ɍ����̂ł͂Ȃ��A��l��l�̐��i�������ƕ`���o���ė]���Ƃ��낪�Ȃ��B���̏������w�����x�⑼�̍�i���l�A�g�D���Q�[�l�t���g���o�����A�o������l�X�����f���ɂ��ď�����Ă���ƌ����Ă���B
�@�g�D���Q�[�l�t�̓`�L�I�o����1818�N�i�������N�j10���A�Z���Q�C�E�j�R���G���B�b�`�ƃ������[���E�y�g���[���i�Ƃ̓�j�Ƃ��ĎY�܂��B��e�̃������[���́A���e�Z���Q�C���6�ΔN��ŁA��n��Ŏ��Y�Ƃ������B�܂��A��e�́A�̒n�̊Ǘ��Ɍ������A�_�z�ɂ������鈵�����ߍ��������ƌ����B�x�z�~�̋�����e�̂��ƂɈ�������ƂŁA�g�D���Q�[�l�t�̗D���������Ȑ��i���`�������B�X�ɁA��e�̐��i�́A��N�g�D���Q�[�l�t�̏����W�ɁA�����e���������Ƃ�\�z������B���̂悤�ȋ����I�ȗ̎�ƁA�x�z�����̖��̒��ň�����Ƃ��납��A�̖��ւ̐l�ԓI�ȊS�ނ��Ƃɂ��Ȃ�B�w�l���L�x�͑薼�ʂ�A�y�n�̎҂��ē��l�ɂ��āA�����]���e���g���āA���O�𑖂���A�f�r���u�U�߁v�̊�����_�ɂ��āA���V�A�̓c�ɂɐ�����l�X�Ȑl�X�̌��������ƕ`�o���ēǎ҂�O�������Ȃ��B
�@�����́A�g���X�g�C���n�߃h�X�g�B�G�t�X�L�[�A�`�F�[�z�t�܂ŁA���w��i��ǂނ��ƂŁA���V�A���O�̎p�ɏo����ė����B���ł��g�D���Q�[�l�t�́w�l���L�x�́A���V�A�̓c���I���R�̒��Ő������閯�O�̌X�̐��i�������ƁA���I�m�ɕ`���Ă��č����V�N���B�����̓ǎ҂ɂ́w�l���L�x�ŕ`���ꂽ�_���̐l�X�́A�V�����̑��݂ŋ������������Ƃ��낤�B���݁A�킽���B���ǂ�ł��A�o�ꂷ��l���X�̐��i�E����I�m�ɕ`���A�c����ɂ�������Ƃ��Ă̕M�G�A�݂��݂������́A�������Ă��Ȃ��B
�@���́A���̕��͂������Ȃ���A�Đ쐳�v��œ�t���l���̖|��ł��m���Ă���w�З��x�|�w�l���L�x���̈�т��|��ǂB�l���̎p�A�w�i�̒��╗�i�̌����ȕ`�ʂ�ǂ܂��A����C�Ȃ�����Ɉ������ގ�r�̏�肳�����߂ĔF�������Ƃ��낾�����B�w�l���L�x�́A����ȋ������A�����̓ǎғ��l�A����̂��������L�ł���A��L�ȏ����Ȃ̂��B���̏����̕���́A�S�ă��V�A�̓c�����B�����ł̏o�����A���V�A�̎��R��w�i�ɁA�o������l�X����l���ɁA�g�D���Q�[�l�t�̌����̏�肳���ǂ�������B�e�Ҋ��������Z�҂Ƃ��āA��C�ɓǂ߂�̂��B�����ɁA�����̑��̍��肩����n�̐��̓����A���̐S�n�ǂ�����A��������C�Ƌ�̐ɁA�����_�̖����ȕω��A��������̋�̐F�̕ό��ȂǂȂǁA���V�A�̎��R�Ɣ_���̕�炵�U��������܌��邱�Ƃ��o����B���ł����͂́A�܊������������������鐐�X������ۂ��Ă���B
�@�����āA�g�D���Q�[�l�t�̍�i���ŁA�ȊO�ɂ��ł����邭�J�����������Ă��邱�Ƃ��B�w�����x��w�З��x�ȂǁA�ނ̑�\�I�ȍ�i�́A�Ⴋ���ւ̊Â��lj��Ƌ��ɉ�������O�̐F�Z����z�������Ȃ̂��B���ꂪ�A�����ł͎��R�`�ʂƁA��{�I�ɉ��O�ł̏o��\�����̕`�ʂ�����o�c���Ă���M���K�����A�`�����͂���̂����\�J�����ƕ��ꐫ�ɖ����Ă���B�����A�w�l���L�x�̓g�D���Q�[�l�t�̏����ɂ���A�ߓx�Ȋ������A��قǐ\���������u�Z���e�B�����^���Y���v���A�e����߂Ă���̂��B
�@�g�D���Q�[�l�t�̍�i�́A�J��Ԃ��ɂȂ邪�A��������Ɍ��炸�ߏ�ɃZ���`�����^�����B���{�ł�����ł͊F���ɋ߂��e����߂��u�Z���e�B�����^���Y���v���A�����吳���̎��̂⏬���̕\���ɘI��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��ȑO����C�ɂȂ��Ă����B�u�Z���e�B�����^���Y���v�́A�g�D���Q�[�l�t�ƌ�����Ƃ́u���i�v�����낤���A���鎞��ɕt���܂Ƃ����̂Ȃ̂��B�����ł͍l�@�o���Ȃ����u�Z���e�B�����^���Y���v�́A�������@�����A�l���Č������e�[�}���B
�@�l�I�Șb�ŋ��k�����A�ȑO�d���̊W�ŁA�A�E�g�h�A�E���C�^�[�̌�A����ɐe�������Ē������B�����A�{�̊�悪����A���Ɉ�x�����ڂɂ�����@����������炾�B���鎞����A���w�l���L�x���́u�x�[�W���̑����v�̂��Ƃ����ɂ������Ƃ��������B�c�O�Ȃ���A���̎��ق��ɂ��b�肪����A�g�D���Q�[�l�t�̏ڂ����b�͏o���Ȃ������B���ɂ��Ďv���A����̃A�E�g�h�A�E���C�^�[���猩��ƁA�w�l���L�x�ɂǂ�Ȋ��z�����̂��AA���S���Ȃ�O�ɁA�����Ă����Ηǂ������Ǝv���̂��B�Ȃ��AA����|�̈��V��m���̂��Ƃ́A���b�P�����|14�|�m�A�C���b�V���E�n�[�g�r�[�g�n�ł��f�`�����B���킹�Ă��ǂ݉������B
�@
�@���݁A�킽���B�̒m��g�D���Q�[�l�t�̕��w�I�����ƌ����A���V�A�c���̌����Ȏ��R�`�ʂƂ����ɐ�������l�X�Ȑ��i�̐l�X�́A���������Ƃ����`�ʗ͂��B������\�ɂ����̂́A�ނ̗T�������e�q�̏�ɂ͌b�܂�Ȃ��ƒ���A���V�A�̑��ɐ�����G�K���̑��ʂȐ��i����w�l�Ԋώ@�͂ƌ������ƂɂȂ邾�낤���B
�@�܂��A�ނ̑@�ׂȊ����i�|�p���j�́A�N�����烈�[���b�p�e�n������{�w�~�A���Ȑ��i�ƌ����������Ă���B�{�w�~�A���M���I�ȁw�����x�w�З��x�����́w���Ǝq�x�ɉ��삷��u�g�D���Q�[�l�t���o�v���l������Ɓw�����n�x�o��l���̎Љ�I�w�i��i�A��҂̍�i�ɑ������v�z�́u�s���S�v�ƌ����̂��A�n����Ă��Ȃ�����������������邾�낤�B���ɂ̉���Ŗ�ғ���F�q�́A���V�A�ł̍�i���\��̕s�]���Љ�Č�A����炪�C�f�I���M�[�ɌX�������߂ŁA�������Ɍ�����Ƃ��낪���������Ƃ�F�߂Ă���B
�@�g�D���Q�[�l�t���߂���C�f�I���M�b�V���Ȕ����́A�Â��̐����h�炢�ł������V�A�Љ�ƌ�������������B�����ɁA�Љ�ɕq���ɔ�������Љ���A�g�D���Q�[�l�t�̐��i�ɂ��������Ƃ��ĔF�����Ă����K�v������̂��B����̓ǎ҂ɂ́A��i�ɐ��荞�܂ꂽ����̓��ꐫ�́A��������Ȃ��Ă���B�킽���B���g�D���Q�[�l�t�̏�����ǂ�ł��A���̎���̎Љ���ӎ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���̂��ƂƔނ̍�i���A�����e�̔��������̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�ꖬ�ʂ��Ă���Ƃ킽���ɂ͎v����̂��B
�@�@�@�@�@�@�@�A�C�U�B�A�E�o�[�����w���Ǝq�@�g�D���Q�[�l�t�Ǝ��R��`��(���x����)�̋ꋫ�x
�@
�@���ɐ\���q�ׂ��l�ɁA�g�D���Q�[�l�t�Ɋւ���Q�l�����́A��������Ȃ��B�g�D���Q�[�l�t����A���V�A�̊v�����Ɋ֘A���镶���Ȃ�AE.H.�J�[��h�C�b�`���[�̍_�j�Ȍ��������m���Ă���B���������{���l�ŏ������Ă���ǎ҂��ǂ�����邾�낤���B�킽���������ĂȂ��B�܂��A�킽���̋��Z���Ă���s�̐}���قɁA���������{�͑����Ă��邾�낤���A�����������낤�B
�@����ȖY�p�̕��ɂ���g�D���Q�[�l�t�̐��U�Ǝv�z�A��Ƃ̔ӔN�����V�A���w�̑��������̒��Ɍ����Ɉʒu�t������]�I�G�b�Z�C������B�A�C�U�B�A�E�o�[�����w���Ǝq�@�g�D���Q�[�l�t�Ǝ��R��`��(���x����)�̋ꋫ�x�i���r�_��@1977�N�@�݂������[�j���B���̖{�̖`���A�g�D���Q�[�l�t���x�����X�L�[�ׂ̗�ɑ���ꂽ���Ƃ�����o�����B�S�y�[�W���́A���Ƃ����U��Ȗ{���B����ł��A�g�D���Q�[�l�t�ƌ�����Ƃ���̃��V�A�̕��w�A�v�z���̂Ȃ��Ɉʒu�t���A�ނ̐^���E���݈Ӌ`���A�����ɒm�邱�Ƃ��\�ɂ����d�v�ȃG�b�Z�C���B�o�[�����iIsaiah�@Berlin�j�́A�p���̎Љ���w�҂Ƃ��Ē��������A1909�N�A���g���B�A�̐��܂ꂾ�B���V�A��ɂ����\�A����1950�N�Ɂw�����x���p�Ă��邻�����B
�@�o�[�����́A�g�D���Q�[�l�t�ɂ́A�����I�Ȏu���͂Ȃ������B�ɂ��ւ�炸�A�����Љ��тт���Ȃ������ƌ����Ă���B����͓������V�A��������Ă������ւ���Ă����B�c�@�[�ɂ��ꐧ�����A�_�z���̑��݂Ɍ�����l�ȋߑ㉻�̒x�ꂪ�A�ߑ�Љ�i�����j�ɑ���A���V�A�l�̕����ځi�R���v���b�N�X�j�ƂȂ��Ă����B����ɑ��ă��V�A���w�́A�����ϗ����|���`�Ɛ^���ւ̖O���Ȃ��T���|�ƌ�������Ȑ��i���݂�����w�����A���V�A�I���������̕ϊv��S�����ƂɂȂ����ƌ����B
�@�g�D���Q�[�l�t�̎Љ�ւ̖ڊo�߂́A1830�N�ヂ�X�N����w�̃j�R���C�EV�E�X�^���P�|���B�b�`�i1813�`40�j�̃T�[�N������n�܂�B�����ɂ́A��Ƀ��V�A�̏����ɉe����^����˔\�����W���Ă����B�X���u��`�҂Ŏ��l�̃R���X�^���`���E�A�N�T�[�R�t�i1817�`60�j�|�w�ދ��G�M�x����g���ɂɂ���|�A�v���ƃ~�n�C���EA�E�o�N�[�j���i1814�`76�j���j�ƃO���m�t�X�L�[�i1813�`55�j�炾�B�Ƃ�킯�A�g�D���Q�[�l�t�ɂƂ��Đ��U�̗F�ƂȂ��]�ƃ��F�T���I���E�x�����X�L�[�i1811�`48�j�̉e���͋������ƌ����B�@�ׂ������|�p���̔�������g�D���Q�[�l�t�́A��ƂƂ��ă��V�A�̂����ꂽ�����ւ̊��\�͂ł��D�ꂽ���̂��������B���V�A�ł́A�|�p�����`�݂̂ł͋�����Ȃ��B����������A�g�D���Q�[�l�t���I�n���V�A�Љ�̂�������ӎ�������Ȃ��������Ƃ�������̂��B
�@1852�N�i�Éi6�N�j�A����܂łɔ��\���ꂽ���т��܂Ƃ߁w�l���L�x���s����B���̒���Ń��V�A�Љ�ɔ_�z���ւ̊S�������L�߂邱�ƂƂȂ�B�X�ɁA1862�N�i���v2�N�j�w���Ǝq�x�����s�A���̏�����1861�N�_�z�����̐���Ԓf��ƁA�Љ�̉��l�ς̍��������ꉻ�����B�w���Ǝq�x�̎�l���i�o�U�[���t�j�̐��i�Ƃ��ĕ`���ꂽ�A���|���Ђɑ��Ďq�|�Ⴂ����̊o�߂��F���u�j�q���Y���v�̑��݂́A�����̃��V�A�Љ�Ŕ����I�ȋc�_�������N�����B1863�N�|�[�����h�œƗ����u�����Ĕ������N����A��N����������B�|�[�����h�ł��_�z������s���A���Ӎ�����������ŁA�ߑ㉻�ւ̈��͂����܂������炾�B���������ߑ㉻�̉ߒ��ŁA�C���e���Q���`������v�����^���A�K���݁A����w�Љ�ϊv�̋C�^���オ�邱�ƂɂȂ�B
�@�g�D���Q�[�l�t�̍�i�́A��ɂ��������ϊv�̈ӎu���M����Љ�ɂ����āA���V�A�̒m���l�Ƃ́A������ꗂ������čs���B���āw�l���L�x�ōD�]�Ȃ���A�_�z�����u�u�E�i���[�h�i���O�̒��ցj�v��������i���[�h�j�L��`�����w�����n�x���^���̒����܂�`�����Ƃ��āA�ᔻ�ɎN����邱�ƂƂȂ�B�g�D���Q�[�l�t�͔ӔN�A���[���b�p�e�n��]�X�Ƃ��Ȃ���A�t�����X�𒆐S�ɑ����̕��l�ƌ𗬁A�����ł̕��������܂�B1848�N�A���F�x�����X�L�[�������B�g�D���Q�[�l�t�́A���F���������Ő�������̂ƕ��������킹�A���V�A���d��Љ���a瀂��d�Ȃ�B50��O�ɔᔻ�ɎN����čs���ߒ��́A�l���̉����Ƌ��ɔ߈�������������B�g���X�g�C�A�h�X�g�B�F�t�X�L�[�ƌ����A���V�A���w�̑�\�I��Ƃœ�����l����A�a�܂�邱�ƂɂȂ�̂��B�u��噂̔@���v�ƌ��������������邪�A�v�z�I�ɔᔻ����邾���łȂ��A�l�Ƃ��Ċ������čs���B�h�X�g�B�F�t�X�L�[�̕]�������܂�قǁA�g�D���Q�[�l�t�̉e�͔����Ȃ��čs������������B
�@�w�����x��w�l���L�x�̌|�p���⊮���x�̕]���������Ă��A�ނ���i�ɐ��荞�v�z�����A�����ڂ݂��邱�Ƃ͂Ȃ��̂́A�䑶���̒ʂ肾�B�����I�ߑ�ӎ���g�ɕt�����u���R��`�v�҃g�D���Q�[�l�t�́A�M���I�ȏ@���҃g���X�g�C��X���u������`�I�h�X�g�B�G�t�X�L�[���炷��Ƌ�������݂Ɍ�����B�o�[�����́u���x�����v�Ƃ́A��ɉ����đΉ�����p���ŁA���E���ɂ̐w�c����G�����������ȗ���Ȃ̂��ƌ����Ă���B
�@�@
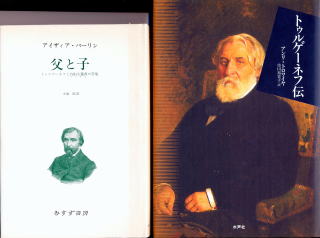
�@�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����E�g�����C���w�g�D���Q�[�l�t�`�x
�@
�@���̕��͂��A�b�v������A�A�����E�g�����C���w�g�D���Q�[�l�t�`�x�i�s��T���q��@2010�N�@�����Ёj����肵���B�Q�����̉āA�ǂݏI�����B�ǂݏI����܂ŁA�������Ԃ����̂́A����{��ǂݏグ��̂ɁA���\���Ԃ�������킽���l�̎���ɂ��B�w�g�D���Q�[�l�t�`�x�́A���ʓǂނ̂ɓ�a����l�Ȗ{�ł͂Ȃ��B
�@���R�Ƃ͌����A�g�D���Q�[�l�t�ƌ����A�����ڂ݂��邱�Ƃ̔�����Ƃ̏����ނ�ǂ�ŁA���̊��z���L���Ă���Œ��A�Ƃ��̍�Ƃ́u�`�L�v���|��o�ł��ꂽ�̂��B�����������R�ł��Ȃ���A�g�����C���̓`�L�́A���̎����ɓǂ܂Ȃ������B����A���e�ɉ������{���A�����ɂ��̖{�̊��z�����̂́A�g�D���Q�[�l�t�̍�i��Y��Ȃ��ƌ����ӎu�\���̈Ӗ��|�����ɂ��Ď����C�͖ѓ������|�ƁA���R�Ƃ͌����A�{�Ƃ̏o��ɂ��s�v�c�ȕ���������ƌ������Ƃ��A�����Ă������������B
�@�A�����E�g�����C����1911�N���X�N�����܂�B���V�A�v���̍ۃt�����X�ɋA�������A���V�A�n�t�����X�l���B2007�N��95�ŖS���Ȃ��Ă���B�`�L��ƂƂ��ē��{�ł��ǂ��m���Ă��āA�킽���́A�鐭���̃��V�A�c��Ɋւ���`�L�A�v�[�V���L����S�[�S���̓`�L�͔w�\������������������B�w�g�D���Q�[�l�t�`�x��B5�Ō����A��҂̉�����܂߂Ă�260�y�[�W�B�ǂݎn�߂�Α邱�ƂȂ��ǂݒʂ���B�g�D���Q�[�l�t65�N�̐��U�́A���x�{�l�̏��������ҏ����ɍ��������l���������Ƃ��A������B
�@���V�A��Ƃ̓`�L�ƌ����A�킽���ɂ͈ȑOV�E�V�N���t�X�L�[�w�g���X�g�C�`�x�㉺�i��蟳��@1978�N�@�͏o���[�V�Ёj��ǂo��������B�g���X�g�C�̓g�D���Q�[�l�t�̓�����l�A���O�e�������������A�����Ă������Ƃ͌��y�����B
�@�w�g���X�g�C�`�x�́A�v������t�H���}���X�g�̋}��N�������V�N���t�X�L�[���A�\�r�G�g�̐�����A���Ē������A�����̓`�L�I�������B���{��ł́A�l�Z���Ɋ������i�ɑg�݁A�㉺���킹���700�y�[�W��L�ɉz����_�j�ȓ`�L�ŁA���̐��U���n�߂��玀�Ɏ���܂ŁA�ڍׂɋL�q�����{���B�������V�A�̓������Ƃł��A�g�D���Q�[�l�t�ƃg���X�g�C�ł́A�������ł͂Ȃ��ʓI�ɂ��A����Ȃɂ��Ⴄ�̂��B
�@���̖{����ɂ����̂́A��w�̑��ƔN���������B�킽���́A�����w�푈�ƕ��a�x���w�A���i�E�J���[�j�i�x���ǂ�ł��Ȃ������B�����炩�A�㊪��ǂݏI���A������ǔj���閘�ɂ��Ȃ�̌�����v�����̂������B�g���X�g�C�̓�咷�҂́A���N���Ƀh�X�g�B�F�t�X�L�[�̒��ҍ�i��ǔj������A�������܂ɓǂ݊��������B����@�������āA�V�N���t�X�L�[�w�g���X�g�C�`�x�̍ēǂ����������̂��Ǝv���Ă���̂����A����Ȃ��B
�@����ɔ�ׂ镪���ł͖������w�g�D���Q�[�l�t�`�x�́A�g�D���Q�[�l�t���g�̏����Ɏ��āA��������Ɠǂ߂Ă��܂��B�v�z�j�Ƃ�I�E�o�[�������A�v���ԍۂ̃��V�A���w�E�v�z�E�Ƀg�D���Q�[�l�t���ʒu�Â����{���A�Q���S�y�[�W�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����ƌ������������v���Ă݂�A�g�D���Q�[�l�t�ƌ�����Ƃ́A����ɉ�����S�̂���l�������ʂ�邩������Ȃ��B
�@�g�D���Q�[�l�t��1818�N�ɐ��܂�A1883�i����16�j�N�A65�ŖS���Ȃ������Ƃ́A���ɐ\���グ���B�g���X�g�C���o���̂ŕt�������Ă����A�g���X�g�C��1828�N���܂�A1910�N�A82�ŖS���Ȃ�B�g���X�g�C�͐��O�̃g�D���Q�[�l�t�����������A�S���Ȃ��Ă݂�ƁA�g�D���Q�[�l�t�̂��Ƃ��v���ĂȂ�Ȃ��Ȃ�B�g���X�g�C���ӔN�A�v�w����ƒ���̂��������ɁA�U�X�Y�܂���Ă������Ƃ͗L�����B
�@�g�D���Q�[�l�t�́A�����ɉƒ���c�ސ��i�ł͂Ȃ��A�ӔN���V�A�ƃt�����X���s�������Ă����B�t�����X�ł͎��̕����B�ƌ����|���Ƀt���[�x�[���Ɛe���������|���V�A��ƂƂ��āA�C�O�ō����]������Ă����B�ꍑ���V�A�ł́A�g���X�g�C��h�X�g�B�F�t�X�L�[���猙���ĂȂ���A����ł����V�A�ł̎���̕]�����C�ɂ����Ă����B�p���x�O�ŖS���Ȃ�A�r�����V�A�ɋA������ƁA���V�A�̍����͂������Ĕނ̎��𓉂ށB�g�����C���̓`�L�ł́A�����Č̍��Ɉ��Z���ďI���|���������n�b�s�[�E�G���h�̔@���|�B�g�D���Q�[�l�t���炸�v���ǎ҂́A�����ꖕ�̈��S�A���ʼn��낷�ƌ����������B
�@�`�L�ɏ�����i�Ɋւ��錾�y���A���������ł͂Ȃ��B���̓`�L�ł��w���[�W���x��w���ނ�x����҂̌o�������Ƃɏ�����Ă��鏬���ł��邱�Ƃ�������B�g�D���Q�[�l�t���g�̌o���ɏƂ炷�ƁA�����̎�l���̐��i�����҂̉e��ттĂ��邱�Ƃ������o����B�����́A�����̎�l���̗l�ɁA��ҁ|�g�D���Q�[�l�t�|���u���ɂȂ��āv���܂����̂�������Ȃ��B
�@�g�����C���̓`�L�́A���ʃ��V�A���w�I�m���������Ȃ��Ƃ���Ȃ��ǂ߂�B�����g�D���Q�[�l�t�̏����ɐe����ł��Ȃ��Ƃ��B
�@����ɂ��Ă��A�����̓`�L��ǂ����Ƃ���l�Ƃ́A�ǂ̗l�Ȑl�Ȃ̂��B��́A�`�L���������l���́A�����Ă݂�u�̐l�v�I�ȗL���l���B����l�́A���j�I�Ȑl����u�̐l�v�̓`�L����A�����悤�Ƃ���̂��낤�B��́A����l�ƌ����̂́A����ɋ߂����u���ʂ̐l�v�ɗׂ荇���u�L���l�v���D��ł���̂ł͂Ȃ����납�B
�@�u�`�L�v�ƌ������w�`���́A�����g�D���Q�[�l�t�̏������l�A�ڂ݂��邱�Ƃ̂Ȃ��\���`���Ǝv���Ă����B���̓`�L��ǂݏI���A����܂łɓǂ`�L�I�Ȓ�������ꂱ��Ǝv���Ԃ����B�`�L�ƌ����`���́A�����ꏭ�Ȃ���A���̐l���̍�i��͕킵�āA�l���̐���`���Ă��܂����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�ȑO�A��L�̎d�������Ă��鎞�A�����r���̏o�ŎЂɗp���ŏo���肵�Ă����A�x�e�����ҏW�҂�K����ƍ��ӂɂ��Ē��������Ƃ��������B���鎞�AK���u�ǂ����āA���͓`�L�����]�`�����Č����낤�H�@���`�L���ł�������Ȃ����I�@�v�Ƃ��������ꂽ�B
�@�g�����C���w�g�D���Q�[�l�t�`�x��ǂ�ŁA����K����̂��Ƃ��v���o�����B�u�`�L�v�Ɓu�]�`�v�̈Ⴂ�A���l���ɂȂ������Ƃ͂��邾�낤���B���ꂩ�琏�����Ԃ��o�����B�킽�������̊ԁA�`�L�I������������ǂB�����ŁA�`�L�ƕ]�`�̈Ⴂ�����l�����B
�@�u�`�L�v�ƌ����̂́A�ꉞ�m��ꂽ�l���̃��C�t�E�q�X�g���[�𒆐S�ɁA�ꐶ��H�钘��B����u�]�`�v�ƌ����̂́A��ʓI�ɂ��d�v�Ȑl�������A����ȗ̈�ł����m���Ă��Ȃ��l���������A��葽���̐l�ɒm���ė~�����A�l�X�ɂȂ��ꂽ�]�����ᖡ���Ȃ���A���̐l���̎d����l���̎��Ԏ��ɍč\�����ĒH��B���ɗǂ��m��ꂽ�l���̏ꍇ�́A������̗l�X�Ȏ�����،����������āA�����ۂ̐l���ɓ������鎎�݂��B
�@�ߔN�u�`�L�v���u�]�`�v�ƃ^�C�g�����ꂽ���삪���������̂́A�l���Ȋw�I�Ȋw��E�����̕��@���i�����āA�������g�p�E���p���������I���삪����ɂȂ������炾�낤�B�Ƃ�킯�ڗ��̂��A�t���C�g���̐S���w��_���͓I�����ł͂Ȃ����낤���B
�@�g�����C���w�g�D���Q�[�l�t�`�x�ł́A�Ⴆ�g�D���Q�[�l�t�̏I���̏����W���A�x�z�I�ȕ�e�Ƃ̐e�q�W�ɋN���������Ƃ���킹����x�A�펯�I�ȋL�q�Łu��������v�Ƃ��Ă���B����́u�]�`�v�I��ƌ����Ȃ�A�t���C�g���̍l������_���͓I�Ȏ��_�荞�݁A������T��ȂNjc�_�Ɏ������������낤�B���_���͓I���_�́A���͂���펯�Ƃ���閘�ɂȂ��Ă���B
�@
�@���݁A�`�L�I����Ńs�[�^�[�E�A�[�N���C�h�iPeter Ackroyd�@1949�`�j�ƌ����p���̍�Ƃ��m���Ă���B80�N��㔼�AT�ES�E�G���I�b�g�̓`�L���|��A���ڂ��ꂽ�B���̌�A�E�C���A���E�u���C�N��V�F�[�N�X�s�A�̓`�L���|��Ă���B
�@�킽���́w�u���C�N�`�x�i�r�c��V�Ė�@2002�N�@�݂������[�j��ǂB���҂�P�E�A�[�N���C�h�́A���g�̋������ւ̊S�ƁA���炪�����h���o�g�ƌ������ƂŁA�����h���q�̃E�C���A���E�u���C�N�̓`�L�ɁA�K�C�ƌ����]�����������B�m���ɁA����܂łɂȂ��ڍׂȓ`�L�������B�������A���҂��傫�߂������炩�A�������̑���Ȃ��C������������������Ƃ��������B
�@���̂��̑���Ȃ��̂��A�u���C�N�̐��U�����ǂ�ہA�m�F�\�Ȏ������d�����đz���≼���������Ȃ��������ƁB��i�̓lj��|�z���͂������Ắ|�́A���R�Ȃ���|�����ł͂Ȃ��̂Ł|�`�L�̔��e�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ����炩������Ȃ��B
�@�v���A18���I�l�̃u���C�N�ƌ������l�́A�x�T�ȊK�w�̐l�ł͂Ȃ��B�����h�������́A�n�������܂ꂾ�����B�T���ȊK�w�o�g�̎��l��|�p�Ƃ̗l�ɁA�c����苳����{���ꂽ��͂Ȃ������B�v�t���ɁA�C�^���A���w�Ƃ��嗤�ւ̗��ȂǁA�o�������Ă��镪���ł͂Ȃ��B�����h���̉����Ƌߍx�̌���ꂽ�̈���Ő������A�����ɕ�炵�Ă����B���}���I�Ȗ`���|��i�Ɨ����Ɂ|�́A�Ȃ����U���B�����炱���A����G�͑z���͂Ɉ��Ă����ƌ������Ƃɂ��Ȃ�B
�@18���I�̉p���́A�嗤�Ői�s����t�����X�v���̋��ꂩ��A���R�v�z�ւ̗}�����������Љ�����B����̗l�Ȏ��R�Ȑ�������I������]�n�́A�ɂ߂Č���I�������B���ۂ̐l����H���Ă��A�����ɑ��������U�́A�ĊO�n���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��̂�������Ȃ��B
�@�u���C�N�������Ă����v����l���́A�l����̎����ɑ������`�L�I�ȋL�q�Ƃ́A�܂��ʂ̂��Ƃł��邱�Ƃ�������B���ɁA�u���C�N�́A�������ł͂Ȃ��G���`���Ă��āA���ƊG���ӑR�Ƃ����\�������Ă����B��i�̓lj��ɓ��ݍ��߂A���ꂾ���œƗ�����������\�z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���m�Ŏ����ɑ������`�L�ƃN���e�B�J���Ȓ���Ƃ́A��͂蕪���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�������Ȃ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014�N8���@�}���S�[�n�l�_
 �@
�@
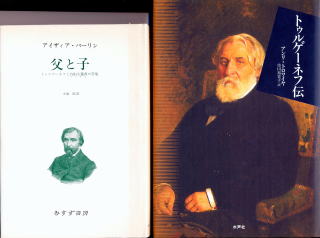 �@�@
�@�@