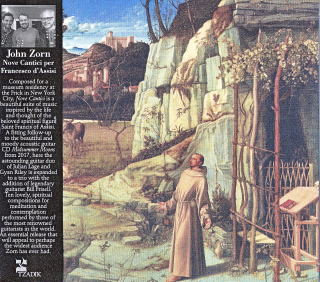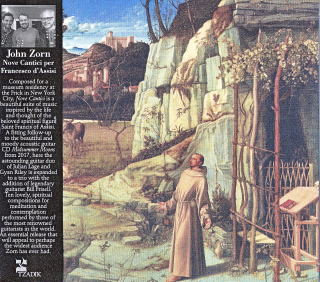巣ごもり通信 Ⅰ 二年前のこと
一昨年春、村上陽一郎『ペスト大流行-ヨーロッパ中世の崩壊-』(1982年 岩波新書)を久々に読み返した。最初に初めてこの新書版を初めて読んだのは、ヨーロッパの中世ルネサンスへの興味からだった。
『ペスト大流行』は、数時間あれば読み終えることが出来る。手軽に読める新書版をわざわざ手にしたのも、著者には『科学史の逆遠近法 ルネサンスの再評価』(1982年 中央公論社)と言う、中世・ルネサンスの科学に関する、専門的な単行本があるからだった。
この時期『ペスト大流行』を再読したのは、何もペストの流行とコロナ禍を重ね合わせたからでは無かった。実は、数年前から気になっていたことがあったからだ。
『ペスト大流行』では、本の始め50頁ほどの文章で疫病ペスト流行の兆しとして、イナゴ(トビバッタ)の大発生があったことが記されている。
十年程前から、北アフリカやアジアのパキスタンやインド西部パンジャーブ辺でイナゴの大発生のことを、新聞の海外記事で見ることが、あったのだ。そして、コロナ・ヴィルスが流行し始めた最初期も、アフリカ、パキスタン、中国北部、インドまで〈蝗害〉が発生していることが新聞に報道されていた。
そこで、そう言えばこの新書に蝗害の記述があることを思い出し、それと同時に、何とコロナの流行が大きなニュースになり出したのだった。今回『ペスト大流行』を読み返して驚いたのは、何とかつてペストの発生地も中国だったらしいことなのだ。新型コロナヴィルスは21世紀のペストなのだろうか。そうだとすれば、〈もの造り〉とリバウンド観光客を中国に依存している日本は、果たしてどうなることか気になった。
もっともそんな一昨年前のことを良く憶えているのは、蝗害とは違う。不要不急の外出が憚られ、巣ごもりしなきゃならないと言う時期に、CDプレーヤーが故障したからなのだ。CDプレーヤの故障は、前に兆候がなかった分けでは無いので、巣籠もりをしなきゃならないこの時期の故障は、一層精神的打撃だった。
もともと自分は、家の近所以外、極力外出はせず、家に籠もっている。そんな中、こうした文章を書いている時、また読書の最中、音楽を聴きかないことは、先ず無い。だからCDプレーヤーの故障は、日常生活に支障を来す〈緊急事態〉なのだ。
大体、使用中にCDプレーヤーが故障したのは、何とこれで4度目なのだ。最初の故障は、ディスクを自動で挿入するトレイが出て来なくなったことだった。二度目の故障は、ディスクが入ったままトレイが出て来なくなった。その時はディスクを入れたまま、購入した新宿の量販店の修理窓口へ持って行った。インドで入手した、今では貴重なCDだったので修理を終えて、ディスクも戻って来て安心した。
三度目の故障もトレイの不作動だった。この三度目の故障時点で、五年の補償期間が終了していて、修理代は有償となったと言う分けだ。
その時、量販店の窓口で言われたのは、先ず3500円先払いし、分解して部品交換など部品代とは別途に、一万数数千円+消費税を前払いせよと言うことだった。一万円と言えば、普通の生活者には可成りな金額だ。一万円もあれば、新品のポータブル式くらい買える金額だ。保証期間中は、何度修理しても無料だが、期間を終えると一気に修理代金が跳ね上がるのには驚きだが、当然とも言える。
製造は簡単でも、修理は人の手先しかないから。この経緯を、長年のオーディオ・ファンでジャズのアナログLPのコレクターをしている兄に相談すると「今度こそ、故障が出ない様に、確り修理する様に確約させる」と言う、アドバイスだった。
一万円はたいて修理することにして、販売店の店員に「仕方ない、修理するけど、今度はこんな故障が無い様、確り修理して欲しい! 」と、兄のアドバイスに従い、言ったのだ。
すると、若い店員は「確り直す」との確約はせず、代わりに「日本のメーカーだけれど、中国で製造した製品だから… 」と、不満そうな表情で言ったのだ。それから一年もせず、四度目の故障と言うていたらくだ。
今回四度目の故障は、液晶表示が突然プチッと切れて、Noディスクだけ点滅しつづける。CDを再生して曲を聴こうと思っても、CDを挿入するトレイが全く作動しないのだ。今更、件の量販店に持って行く気にはならなかった。しかし、買い換えるにしても、コロナ禍で、急遽都心へ出て探す情況ではなかった。「ブチッ切れ」たのは、コロナ禍で〈巣籠もり〉を強いられるこの時期によりによって、CDプレーヤーが故障してアルバムが聴けないこと、こんなことは、おれには狂気の沙汰だ。出て来た保証書には、三度目の修理の伝票があった。見ると、前回の製造メーカーの伝票が一緒にあり、連絡先電話番号もある。ともかくメーカーに電話してみることにした。すると、何と修理に応じてくれると言うことだった。修理代は幾らくらいかも訊くと、修理箇所を見ないと分からないが、一万円程+消費税程とのことだった。またもや一万円と言うのは、どう言うこっちゃ!
いやはや、コストをかけずものを作るために、中国で生産したおかげかどうか、分からないが、結局人の手先が必要になるのが〈もの〉の道理って言うことで、全ての〈ものごと〉の理(ことわり)がここに帰着する。ともかく、メーカーに修理を依頼することにした。これまでの故障の実情と「中国で製造した… 」と言う店員の反応など、洗いざらい経緯をワープロで作文した手紙を付けて梱包して、郵便局から宅急便で送った。数日後、電話があった。メーカーの修理部門からで、中年の男性が出て、連休明けに修理するとのことだった。それも、一応、製品を開いて故障箇所を確認する手数料の3500円+消費税で良いとのことなのだ! 。三度目の故障の際の量販店との遣り取りを手紙に詳細に書いておいたのが功を奏したと思った。
今や世の中、音楽やドラマの視聴は、ネットから直接ダウン・ロードして、性能の良い
レシーバーで、聴きたい個人で耳から脳髄に流し込む。料金は定額で、それをクレジット・カードで支払えば聴きたい音楽を何時でも、幾らでも聴ける分けだ。CDを買う必要はない。CDを聴くには、プレーヤーが必要だが、スマホが一丁あれば映画、音楽、読書が可能なのだ。
だから、音響機材は、目の玉の飛び出る金額のマニアックなものと、一般の家電製品に比べればかなり高額な中間的な音響機材と、若者でも購入できる、それなりに音の出る廉価な、ミニコンポしか無いのだ。
ミニコンポの類のユーザーは、補償期間が切れて故障したら、買い換えるのだろう。修理の費用より、それに少し足せば新製品が手に入るだから。もともとCD自体が売れないご時世だ。あれこれ小うるさく拘るのは、おれら、おじん世代だけと言うことなのだろう。
こんな不足の事態があったコロナ禍第一波の非常事態宣言下、おれは昨年の連休明けに修理され、戻って来たCDプレーヤーで、お気に入りのアルバムを聴きながら〈音楽で辿る最初のインド旅行〉と言ったテーマで、小説を書き継いでいたのだ。
昨年来、大凡の国民は、クリスマスもお正月も家に逼塞して過ごした。そして、その後は、毎日千人を超える感染者数が告げられて、皆、非常事態の延長は、止むを得ないと諦めて情況を受け入れていた。
仮にこの先、感染者数が低くなっても、また人が活動し始めれば、また感染の波が押し寄せるだろう。そんな波が何度も退いては繰り返すと言う。そんな流行の波を挽回する可能性は、唯一ワクチンの接種とも言われ、イスラエル、英国など、功を奏した国もある。
ワクチンの様な薬品の完成には、多額の経費と長い研究の積み重ねが必要だ。何より安全性も第一に考慮しなければならない。国産が出来ればそれに越したことはないが、一応欧米の製薬会社の製品なら信頼しても良いのじゃないか。こんなところが、今の政府や専門家の思いだろう。
そのコロナ・ワクチンのニュースを聞いた。英国ファイザー社がEUで生産したワクチンは、英国への輸出には規制をする様な案配らしい。まるで、一年前のマスクの時の様な仕儀だ。
そもそも、われわれの国では-故障したCDプレーヤーの様に-もの造りは、工賃の安い中国やアジアの何処かで製造すれば良い、と言う体勢だ。取り分け、マスク様な取るに足らないものの製造は、国内ではやりたがらない。
マスク生産国の中国として見れば、国内のコロナ流行で、自国の需要を優先し輸出を制限した。それで、日本では、マスク不足で、騒ぎになった。
幸い今、マスクは、幾らでも入手可能だ。今や家から一歩踏み出せば、マスク無しでは居られない。マスクは外出時の必需品だ。このマスク、この先一体何時まで、外出の必需品として、着けて回らなければならないのか。
この春、医療従事者にワクチンが接種され始めた。何時かはいろいろ言われてはいるが、国民大半に行き渡るまでの見通しとなると不明だ。マスクはこの先結構長く着けつづけなければならないと言うことになる。それで、女性は自前で作った、おしゃれなマスクをする人もいる。女性達は、マスクを〈おしゃれアイテム〉の様に多様にした。こうして社会の雰囲気の変化が起こる。この先、どんな風になって行くのやら。
CDプレーヤーの様な電器製品やマスクの様な消耗品でも何でも、工賃の安いアジアで、大量に作らせ廉く輸入する。そんな当たり前だが、歪んだ行き方も、この際見直す機会にして欲しい。現在のコロナ禍は、どうもそんな長年の歪みが関わっている様に思えるのだ。
ジャケットの絵が気になって入手したCDがある。NOVE CANTICI PER FRANCESCO D`ASSISI「アッシジのフランチェスコへの新たな讃歌」と言う、タイトルのアルバムだ。ジャケットの絵は、ジョバンニ・ベルニーニと言う画家の絵画だ。このCDのタイトルとジャケ写を検索画面で見た時、直ぐ聴いてみたいと思ったのだ。
CDジャケットはLPレコードに比べれば、かなり小さい。ジャケ写は、精々本の図版よりやや大きい程度だ。ただ、このNOVE CANTICI PER
FRANCESCO D`ASSISIのジャケットの繪は、カラーで、多分デジタル処理され、ディテールもなかなか綺麗に再現されている。 FRANCESCO
D`ASSISI〈アッシジのフランシスコ〉とは、サン・フランシスコのもとにもなった、聖フランシスコで、中世末期イタリアで世俗を離れて神に祈り、伝道をし、後にフランシスコ修道会のもとになった聖人のことだ。皆さんもご存じの様に「ブラザー・サン、シスター・ムーン」としても、知られている。
このCDは、作曲とプロデュースをアバンギャルド音楽家-サキソフォン奏者-のジョン・ゾーンJohn ZORNが行っている。このアルバムで、ジョン・ゾーンは、自らのサクソフォンによる演奏は、一切せず、作曲とプロデュースに専念している。演奏は、ジュリアン・ラージJulian
Lageとギアン・ライリーGyan Rileyの二人によるガット・ギター演奏。そして、この二人に、ジャズ・ギタリスト、ビル・フリゼールBill
Frisell が、スティール弦を張った、ギブソンのアコースティック・ギターで参加している。異色なアコースティック・ギタートリオによる、作品だ。楽曲は、表題の付いた十楽章からなる、ジャズと言うより現代音楽作品になっている。
曲の始まりBrother Sun, Sister Moonは、明らかにスパニッシュな雰囲気の曲調で始まる。これは、もともとギターと言う楽器が、西欧においてはスペイン辺で発達したからだろう。ギター類の弦をはじく楽器には、恐らく、イスラームと言うかアラビア半島や北アフリカの血も入り交じっているはずだ。この最初の曲は、西欧が誕生する中世・ルネサンスを意識していることも良く分かる。作曲者のジョン・ゾーンは、アヴァンギャルド系ジャズ演奏者で知られているが、このアルバムでは、ジャズの片鱗を感じさせない、現代音楽になっている。
聖フランシスコが修道生活を送った中世末からルネサンス期の西欧は、多数の都市国家が繁栄し始める時代であった。同時にその頃のヨーロッパは、戦乱とペストの流行に、何度も見舞われた、荒廃と波乱の時代でもあった。スペイン、イタリアで、コロナ・ヴィルスで死亡した死者を葬る場所すら確保するのに苦慮する様子をTVで見て、中世・ルネサンス期のペスト流行でも、正に同じことがあったのだと思った。そんな、コロナ禍の世界なかで、聖フランシスコの生きた時代を思い返すなんて、とても奇妙な附合と思った。
過去と現在を考え合わせ、地球の環境破壊や温暖化にSDG`sが言われ、ついには、現代のペストとも言うべき、コロナ禍の現在を、中世・ルネサンスの聖人フランチェスコの存在を思い起こすことで、小さな光明を見出そうとする音楽の様でもある。
美術愛好癖のあるおれとしては、NOVE CANTICI PER FRANCESCO D`ASSISIは、その音楽もさることながら、美しいジャケットも魅力的なのだ。コロナ禍の最中にも、CDを聴きながら、ジャケットの写真を眺めていると、少し気分が安らがないではない。ジャケットのベルニーニの絵は、ニューヨークのフリック・ミュージアムが所蔵していると言うことだ。フリック・ミュージアムは、フリック氏のコレクションをもとにして創設されたミュージアムで、既に五十年代からコンサート・ホールがあることは、故・吉田秀和の初めての外遊レポート『音樂紀行』(1957年 新潮社)にも出て来る。美術館にコンサート・ホールも併設とは、如何にもニュー・ヨークらしい。ジャケット裏のライナーを書いているのは、多分ジョン・ゾーンだろう。そこには、MOMAやシカゴのアート・インスティチュートなど、アメリカの多くの美術館で、彼らがコンサートを行ったことに就いて触れている。
NOVE CANTICI PER FRANCESCO D`ASSISIのジャケット絵の作者、ジョバンニ・ベルニーニとは、どんな画家なのか。これまで関心がなかったこの画家に就いて、『風景画論』の図版にあったことを思い出し、直ぐケネス・クラーク卿の『風景画論 Landscape
into Art 』を出して確認して見た。ジャケットの絵と他に数枚モノクロ写真が収録されている。経歴など余り詳しいことは分からない。ただ、ルネサンス期の重要画家だったことが分かる。そんな絵画がニューヨークにあると言うのも面白い。『風景画論』でも、ルネサンス期ペストの流行に触れた記述がある。クラーク卿は、ルネサンス絵画のテーマや描写の発展にペストの流行が影響していたと言う。「ヒューマニズムの父」とも言われるペトラルカが、各地を転々としたのも、ペストの流行から逃れる為でもあった。人文主義者や画家は、ペストの流行する都市から逃れ、避難先の都市で仕事をした。そんな避難先で語る形式で書かれた本が、ボカッチョの『デカメロン』だった。
岩波新書『ペスト大流行』でも、ルネサンスと言う時代は、中世末のペストの流行と深い関係があると言われている。この新書では、1320年代の終わり中国で、干ばつ、洪水、地震にイナゴの大発生がつづき、1334年、浙江流域で干ばつの後、悪疫が発生し500万人に上る生命がペストの流行による死者としている。
この1300年代、14世紀は、イタリアを中心にルネサンスの機運が、次第に高まる時期に相当するのだ。盛期ルネサンスには、イタリア各地が都市国家として勢力を競う。当時の都市は、城壁を繞らし、市民は、外敵や別の都市国家と戦になれば、城門を閉じ、城砦に籠もって戦う。都市とは、外部を閉じて内部に拡がる機能をもった城砦が、その始まりだったのだ。現在のコロナ禍では「ロック・ダウン」なんて、聴き慣れないことばも飛び交ったが、ロック・ダウンとは、正しく都市の城門を閉じることだ。
ルネサンスの繁栄とペストの流行がどう関わっていたのか、これまで読んで来たルネサンス期の美術史の論文では、ルネサンス絵画をはじめ藝術のペスト流行の関係や影響と言ったことには、殆ど触れた記述がなかったことに気がついた。おれは、書棚なの奥からルネサンス関係の本を何冊か引きだし、ページをめくった。研究書は索引が付いている。索引でペストの項を探すが、殆どの本は〈ペスト〉の項は無かった。唯一、宮下志朗著『本の都市リヨン』(1989年 晶文社)には、索引に〈ペスト〉が挙げられていた。本文で確かめると、1560年代宗教戦争真っ直中のフランス各地域で、未だ散発的ながらペストの流行が起こっているとのことだ。
1300年代中国から発生したペストは、中央アジア、イラン、エジプトから地中海を渡り、ヨーロッパ中に拡がり、中世、ルネサンスを経て200年以上に亘って居座りつづけ、ヨーロッパ各地で、間歇的に猖獗を極めたと言う分けなのだ。先日、TVで免疫学者が発言していた。コロナ発生の前、インフルエンザの一種とおぼしき流行病が、ロシア、スラブ圏に発生したことがあったそうで、それがどうも今にして思えば、新種のコロナ・ヴィルスによるものではないかと言うのであった。
トップページに戻る