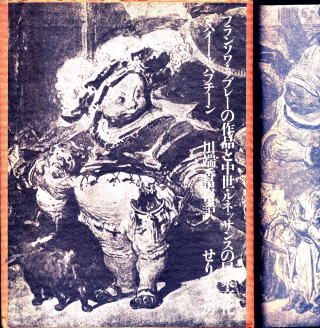巣籠もり通信 Ⅲ 『性の歴史Ⅳ 肉の告白』と『バフチン、生涯を語る』
新年を迎えて、遂にコロナ禍は、3年目に突入した。取り分け、この新年は、オミクロン株が猖獗を極めている。昨年、12月初旬、一時コロナ・ヴィルス感染者が100人を割った時期に、おれはここぞとばかり書店とCDショップを回った。本とCDの入手は、おれにとっては〈不要不急〉の用事では無い。本やCDが必要となれば、何時でも都心へ出る覚悟なのだ。
年明け『バフチン、生涯を語る』を読み出し、1月末、この本を読み終えた。この本に就いて通信する前に、昨年の調度今頃読んだ、ミシェル・フーコー『性の歴史Ⅳ 肉の告白』(槙改康之訳 2020年 新潮社)のことをに触れさせて欲しい。コロナ禍の昨年1月~2月、ミシェル・フーコー『性の歴史Ⅳ 肉の告白』を読み、コロナ禍の三年目に入った今年一月『バフチン、生涯を語る』を読むにおよび、コロナ禍のこの時季、おれの青春と因縁浅からぬ、この二冊が刊行されたことを通信したかった。
それにしても、フーコー『性の歴史Ⅳ 肉の告白』が刊行されて、丸一年経過した。それなのに、新聞、雑誌などで、この本に就いての評が掲載された様子がない。最も近年は、固い内容の人文書など書評で見かけることもなくなった。大体、翻訳書とか人文系の書籍の出版は、少なく、当然のこと、そんな本を紹介する様な雑誌も無くなって久しい。今、フーコーの遺著が翻訳出版されても、まるで興味を持たれていないとすると、フーコーの遺著の出版と言う事件より、こうした本を返り見ない世の人々少なくないことが、衝撃的なことに思えるのは、時代遅れなおれだけなのだろうか。

そもそも『性の歴史』の最初の一冊目『性の歴史Ⅰ 知への意志』が刊行されたのが1986年9月、翌月『性の歴史Ⅱ 快楽の活用』が、やや遅れて1987年4月『性の歴史Ⅲ 自己への配慮』と三冊は、順調に翻訳されていた。それが昨年、突然『性の歴史Ⅳ 肉の告白』が刊行された。それから調度一年が過ぎて、今年はコロナ禍が三年目に突入した。そんな不自由な時季、自らに閉じこもる様に読む本としてフーコーの『性の歴史Ⅳ 肉の告白』は、如何にも相応しい本と、思って今通信申し上げるのだ。
フーコーと言えば、有名な『言葉と物』が翻訳さたには、調度おれが、大学に入学した年だ。それでも、実際に『言葉と物』読んだのは遅く、社会人になって間もなく、八〇年代はじめのことだった。その後、大冊『狂気の歴史』も読んだ。つづいて『監獄の歴史』そして『性の歴史Ⅰ』の刊行が始まったのだ。それでも、おれは、フーコーの熱心な読者と言う分けではなかった。フーコーがエイズで亡くなったのは1984年だ。早いもので38年も前のことになってしまった。38年間と言えば半端な年月じゃない。フーコーのことなど、露程も知らない人がいても不思議じゃない。おれと同世代で多少はフーコーを読んだことのある人でも、今更『性の歴史』を読んで見たいと思うかどうか。それが33年後の2020年末、突然シリーズ四冊目『性の歴史Ⅳ 肉の告白』が刊行され、おれとしてはとても驚いた。
それにしても、この本の刊行までに33年経過してしまった。なぜか、それは、フーコー自身が死後の刊行を望まなかったことにある様だ。フーコーの死後、講義録や論集が出て、更に著作がプレイヤード叢書に入った。それで、漸く『性の歴史Ⅳ 肉の告白』も禁を解かれたと言う。
存命中フーコーは、日本でも現代思想をリードする知識人として突出した存在だった。確かに、二〇世紀の最後に人文科学を活性化させた立役者だったことは、間違いない。ただ、おれとしては、フーコーの存在は、レヴィ=ストロースやバタイユなどと比べて身近な存在ではなかった。
刊行を知り、直ぐにでも書店へ行きたかった。コロナ禍の非常事態の宣言中とあって、外出は控えた。刊行後、新聞の読書欄や雑誌の何処かで書評がなされていないか気にしていたが、この本を話題にしている様子は、今に至っても無いのだ。年明け早々、書店に行くと、『性の歴史Ⅳ 肉の告白』は、売り場の脇に特別置かれたバスケットに、多数積まれていた。ところが、手に取って見ている人は、おれを除けば一人もいなかった。現在、フーコーが以前の様に感心が持たれていないのは、現代思想への流行が遠のいたからなのだろうか。また、フーコーをはじめとする人文科学の流行が過ぎたとして、現在人、どんな思想を求めているのか。
今、フーコーの遺著など、大方の人々が感心を持たないのは、分かる。年年「どうしても読みたい、読まなければ… 」と言う、切実な思いに駆り立てられる本に出会えなくなって来ている。誰がどの様な本を読もうと自由だ。だからこそ、おれはおのれの感心の赴くところ自由に読みたい本を読ませてもらおう。ともかく、フーコーの『性の歴史Ⅳ 肉の告白』は、おれが出会った久々の〈是非モノ〉現代思想本だ。コロナ禍の最中にあって、ますます渾沌とした世界を生きるには、読書こそ最も手がかりになるはずだ。果たして、フーコーが生きていたら、このコロナ禍をどう診てどう評価しただろうか。そんなことを想像しながら、おれは『性の歴史Ⅳ』を読んだ。
この本でのフーコーの語りは、それまでの著作の特徴の複雑な文体から遠ざかり、死を前にした者特有の静まりかえった透明な文体になっている。引用されているローマ時代の教会関係者の訓導書は、結婚や異性との交わり就いて、淡々とキリスト者の守るべき道を説いていて、われわれ日本人には遠い響きしか無い。それでも、500ページ程に亘りテクストを読んで行くフーコーの胸の内を思うと、どこか悟り澄ました響きさえ聞こえてくる文章だ。いずれ全四冊を読み返して、そこから性に関するどんな考えが導かれるか、興味をそそられる。
*
『性の歴史Ⅳ』の後、何とこの後通信する『バフチン、生涯を語る』(佐々木寛訳 2021年 水声社)が刊行されたのだ。
このバフチンの本も、半年経過してもこの本意触れた書評の様な文章は、まるで見ることなく経過した。確かに、読書と言う知の営みが終焉したと言われ、人文書も書籍の中央に積まれる様な知の座からは、転げ落ちた領域と認識する人がいても仕方がない。
それでも、一年に一冊は、重要な本が出版されている。調度半年程前、アレン・ギンズバーグ『吠える その他の詩』(柴田元幸訳 スイッチ・パブリッシング)の新訳が、刊行されたのが好例だ。これらの本は、今、この時代に刊行されたからこそ、何を置いても読みたい本だ、と言うことなのだ。

『バフチン、生涯を語る』(佐々木寛訳 2021年 水声社)は、21年6月に刊行されていた。この間も容易に書店に行けず、瞬く間に半年が経過してしまった。年末、漸くコロナ流行の第五波が収まり、かなり久し振りに出た神田神保町の書店で、実際にこの本を手に取った。
こうした〈渋い本〉が、この様な時代のしかもコロナ禍の最中に出版されたことを思うと、もとの本が出たこともさることながら、半世紀を閲して翻訳が出版されたことも、『性の歴史Ⅳ』と共に因縁が深い気がしないでもない。おれは翻訳され日本語で読めるバフチーンの著作は、ほぼ読んで来た。ほぼと限定するのは、現在、三冊刊行されている水声社版〈バフチーン全著作集七巻〉は、持っていない。水声社版著作集は、新訳の『フランソワ・ラブレーと中世・ルネサンスの民衆文化』をはじめ、三冊が刊行されている。この著作集の前身だった新時代社版全八巻を揃えているので、水声社版の三冊は、持っていないのだ。
なかでも『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』は、せりか書房から1973年に刊行された、川端香男里訳を愛読愛蔵している。また『ドストィエフスキー論』も、1969年に冬樹社から刊行された、新谷敬三郎訳の旧版によって読んでいる。水声社版著作集にも『ドストィエフスキー論』は、現在は未刊だが、一応リスト・アップされている。しかし、近年の人文書に対する関心の薄さを思うと、この先水声社版バフチーン著作集が完結するかは、分からない。
『ドストィエフスキー論』に就いては、冬樹社版の他に『ドストエフスキーの詩学』として筑摩書房(1995年)から新訳が文庫化されている。おれは、この文庫版新訳でも読んでいる。今では、老眼の進んだおれには、細かい活字で組まれた文庫より、やはりA5サイズの旧版が,読みやすい。
70年代半ばに、山口昌男により高い評価で一躍知的ヒーローの如き存在に祭り上げられたバフチーンだ。おかげで、本(紙の)が売れないと言われる昨今、その著作を手にすることが出来るのは、山口昌男と言うユニークな本好き知識人がいたからだ。おかげで、バフチーンの様な長く不遇な知識人が注目され、彼の流浪の人生を晩年補ったことは、われわれにとっても幸運なことだと思う。ともかく、バフチーンの全ての著作は、70~80年代の様に人文系翻訳書の出版が盛んでない現在、殆どが日本語で読めるは、ロシア文学者の影の努力のたまものだ。
さて『バフチン、生涯を語る』は、1895年生まれのバフチーンが、78歳の1973年2月~3月にかけて、文芸学者のヴィクトル・ドゥヴァーキンとの間で交わされた、長時間対話が、まとめられた本だ。バフチーンはこの対話の二年後1975年に80歳で亡くなる。この対話は、バフチーン最後の肉声が聴き取れる貴重な本だ。
バフチーンの研究として第一に挙げられるK・クラーク、M・ホルクイストの『ミハイール・バフチーンの世界』(1990年 せりか書房)でこの対話は、採り上げられていない。最も、この本に関しては、触れられてはいないからと言っても、この『バフチーンの世界』は、アメリカのスラヴ研究者による、バフチーン研究として画期的な本だ。この研究は、バフチーンやその周辺の人々のとの書簡やロシア側の資料を最大限生かして書かれた、バフチーンを知ることの出来る、現在最も頼れる文献であることにかわりはない。また『バフチン、生涯を語る』の存在に関して、バフチーンの論文を翻訳している北岡誠司による『バフチン 対話とカーニヴァル』(1998年 講談社)で「バフチーン自身の貴重な肉声が聴き取れる」対話として、巻末で注記されている。
『バフチン、生涯を語る』は、これまで翻訳されず残されていたバフチーン自身の最後の本だ。ここで、交わされるのは、バフチーン自身の生い立ちから、革命前から革命後、独ソ戦とその後のスターリニズムの時代のに出会った人々のことだ。ペテルブルグやモスクヴァの知的なサークルやサロンで、バフチーン自身が出会った人々が、ロシア革命の混乱と独ソ戦と、戦後のスターリニズムによる粛正のソ連時代に、どの様に変転を重ねたか明らかにされている。有名な言語学者ポリヴァーノフが麻薬中毒だったことなど、生前交友があったから分かることで、他にもマヤコフスキー、アレクサンドル・ブローク、フレーブニコフなど詩人の生前の印象を語っている。この対話では、バフチーンがマレーヴィッチと親しかったと言う。ヴェテブスクの美術大学をバフチーン夫妻が訪れた際、そこでマレーヴィッチと知り合う。この美術大学は、マルク・シャガールが中心に設立されたと大学と言う。生涯一貫して〈ことば〉の探求者だったバフチーンだ。それが、シュプレマティスムの画家マレーヴィッチとバフチーンが親しかったことは、この対話で、初めて知った。ロシア・アヴァンギャルドの造形言語を駆使した芸術から、バフチーンがどの様な刺激を得て来たか考えるのは、とても興味深い。このヴェテブスクの音楽院で、バフチーンは美学と音楽哲学の教師をする。ヴェテブスクの時代、バフチーンが音楽を志す若者にどの様な内容の美学と音楽哲学を語ったのか、これまた興味深い。ロシア・アヴァンギャルドと言えば、美術と造形だが、ロシアと革命後のソ連は、現代音楽に関しても興味深いのだ。
バフチーンはこの対話で、自らの基本はカント哲学の研究から出発したことを表明している。そこから、カッシーラーも戦前から読んでいることに触れて、対話の中で、バフチーンはカッシーラーの『象徴形式の哲学』を優れた著作と評価している。カッシーラーの『象徴形式の哲学 全4巻』は、現在でこそ文庫で読める本だ。しかし、完訳され文庫本になったのは、漸く90年代半ばのことなのだ。
それにしても驚くのは、流刑に処されたバフチーン夫妻には、常に親身な協力者がいて、窮乏の時代を生き抜くことを助けたと言うことだ。巻末、対話に出て来た人々に関して、原注と詳しい訳注が付され、それらの人々が、どの様な経歴の人物か分かる様になっている。かつてこの『通信』で、岩波『思想〈バフチン再考〉』(2020年8月)に触れたことがある。そこでは、ドイツの学者から、バフチーンの『ラブレー論』において、カッシーラーの『個と宇宙』からの引用が「剽窃」と言う指摘の件に触れたのだった。久々に『思想〈バフチン再考〉』を出して来て、ぱらぱらめくって見た。この〈特集〉では、バフチーンがカッシーラーのルネサンス研究の一冊『個と宇宙』に関し、ノートや覚え書きを作り、丹念に読み込み『ラブレー論』に組み入れていたことが、北岡誠司によって報告されている。カッシーラーは大戦前、アヴィ・ワールブルグの私的な文庫を利用して『象徴形式の哲学』やルネサンス関する論文を書いていた。このことからも、カント哲学者のバフチーンは、困難な時代に新カント派のカッシーラーの著作を通じてアヴィ・ワールブルグと通じ『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』を書いたと言うことになる。
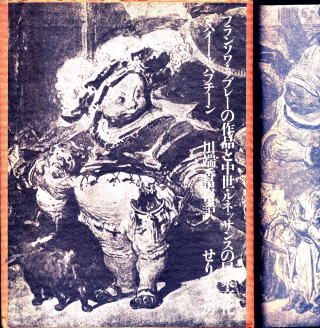
また、バフチーンはギリシャ・ローマの小説類に造詣が深かったことから、アプレイウスの小説やメニッペアがルネサンス期にラブレーに影響を与えていたことを見抜いている。
70年代半ば以来、学際(Interdisciplinary)を提唱していた山口昌男や渡辺一夫に師事していた大江健三郎などによる、強い〈推し〉があってバフチーンの評価は、一気に高まった。特にルネサンスの民衆文化に関して、バフチーンの〈カーニバル理論〉や〈グロテスク・リアリズム〉などの考え方は、流行にすらなった。
そのことをやっかむ日本の学者がいることは、分からないではない。バフチーンへの高い評価を日本のフランス文学系ルネサンス研究者は、バフチーンの『ラブレー論』をやっかむ感情いっぱいに、バフチーンを門外漢(どこの馬の骨とも分からない… )の越境行為として、否定的に見る向きがあるのだ。
以前、マイケル・A・スクリーチ著『ラブレー 笑いと英知のルネサンス』(平野隆文訳2009年 白水社)を読んだ際、訳者はあとがきで「バフチーンをスクリーチが無視している」と、如何にもスクリーチ先生を引き合いに貶める言い種だった。英国国教会牧師でもあるスクリーチ先生の『ラブレー 笑いと英知のルネサンス』では、『ガルガンチュアとパンンダグリュエル』物語のキリスト教信仰と聖書の世界が綿密に論じられている。一方、バフチーンは、中世ルネサンスの民衆に拡がっていた、ギリシャ・ローマの異境的な水脈とラブレーの思想の関わりを掘り起こしている。スクリーチがバフチーンを無視するもなにも、描こうとしている世界が異なるのだ。
もともと、ルネサンスは、キリスト教にギリシャ、ローマの異教的伝統が反応融合して形成された文化だ。今だから、異教的伝統なんて軽く口にすることが出来るが、ルネサンス期は、リベルテナージュは命がけだった。ラブレーをはじめパラケルススやエラスムスなど、当時の自由思想家達は、旧来のクリスト教会への批判が教皇朝の禁忌や異端審問所に目をつけられない様、行動や交友、手紙の文面まで表現は注意を怠れなかった。ラブレーの〈物語〉も、当時の民衆語や卑猥な表現で、教会批判をカモフラージュした。ルネサンスの思想家達が一箇所に落ち着かず、ヨーロッパ各地を遊行したのも、何より批判的な思想や自由思想を教会権力に嗅ぎつけられない様、用心していたからだ。また、当時間歇的に流行していたペストへの警戒で安全な都市へ移動する必要があった。
そんな辺りを憚るラブレーの姿勢は、バフチーンの流刑の境涯と似通っている。バフチーンの著作は、常に体制の目をカモフラージュする屈折した表現が幾重にもあり、現代のアカデミックな研究と言った著作とは、些か性格を異にしているのだ。分かりにくさはその辺にあり、それがまたバフチーンの本の面白さでもあるのだ。バフチーンの『ラブレー論』の英語版が出版されたのは、1968年、日本語版は73年、それでも英語圏では、バフチーンへの関心は日本よりかなり遅かった。バーバラ・A・バブコック編『さかさまの世界 芸術と社会における象徴的逆転』(岩崎・井上訳 1984年 岩波書店)で、山口昌男が指摘している。
日本でのラブレーの『ガルガンチュアとパンダグリュエル物語』は、戦前・戦後の長きに亘り翻訳刊行した有名な渡辺一夫先生の日本語版がある。そこには、本文と同じ分量の訳注が付されるなど、もともとラブレーの表現が現代の標準的なフランス語とは、かなり異なり、なかなか翻訳困難だったことも分かる。ラブレーは、日本でも欧米でも近代の小説と同等にそのまま読み通せる〈お話し〉では、ないのだ。おれは、岩波版の他に、2005年に第一の書を刊行し、第五の書が2013年に完結した、宮下志朗による筑摩文庫版新訳『ガルガンチュアとパンダグリュエル物語』も読んでいる。この文庫版新訳でも、岩波版とそう変わらない、多くの訳注が付され、一巻が500ページ程の厚手の文庫本になっている。近年、文庫本化されているからと言って、こうした大部の翻訳を誰もが読むとは限らないのだ。
バフチーンのフロイトに関する著作も重要だ。フロイトへの関心は、古くからバフチーンのサークルにあった。現在は、ヴォロシーノフの著作とされている『フロイト主義』だ。『フロイト主義』でバフチーンの関心は、この本でも一貫して〈ことば〉をめぐるもので、フロイトとその後の研究者による無意識と言語の生成をめぐる成果に注目している。この本は、フロイトを批判した論文に就いては『バフチン、生涯を語る』でも、フロイトを重要視する発言がなされている。フロイトの可能性を評価する論文でもある『フロイド主義』は、1925年雑誌に掲載された論文と言う。バフチーンの先駆性がうかがわれる著作だ。
『バフチン、生涯を語る』からは、革命により流刑に処され、以来周辺の知識人として生きながら、しぶとく生き、思索したバフチーンの性格が伝わってくる。
この対話からは、帝政ロシアが、革命を経て独ソ戦とスターリニズムと続く、窮乏の時代がうかがえる。それが、コロナ禍の現在が重なって、何とも言えずバフチーンの生きた時代がリアルに感じられる読書体験になった。この本は、正しく今こそ読れるべき本だと思った。
フーコーの『性の歴史Ⅳ 肉の告白』や『バフチン、生涯を語る』と言った人文書は、今や一年に一冊出会える程度の稀少な本になった。大体、おれが知っていた小出版の社主は近年亡くなったり、引退したりとその世界は空気も変わっている。大体、都心の大型書店に行けば分かることだ。
〈出版不況〉と言うことばを聞く様になって久しい。中でも紙の本は、売れないとされている。ただ、言わしてもらえば、そんなことは、七〇年代からさんざん言われて来た。そう言うことは、何を根拠に、経済統計から出された結果をもとにでもして言っているのだろうか。この時期『性の歴史Ⅳ 肉の告白』や『バフチン、生涯を語る』と言う〈渋い本〉が出版されているのだ。
二月二九日、遂にプーチンのロシア軍が、ウクライナに侵攻し、戦争になった。読み終えて、本棚に収めた『バフチーン、生涯を語る』を出して、あちこち読み返した。バフチーンは、1895年、オリョールのヴィリニスで生まれ、オデッサのギムナジュームから大学に進学し、更にペトログラードで哲学と古典学を学ぶ。1920年、ヴィテブスクでヴォロシノフやメドヴェージェフらと〈バフチーン・サークル〉を結成した。1928年、流刑宣告、1930年、クスタナイへ流刑になる。ほかにもバフチーンが点々とした都市は、オデッサやモルドヴァなど、今ニュースで聞かされる都市があり、妙な気分になる。バフチーンが流刑になった地方や縁の都市の性格など、注記があれば良かったと思う。
ウクライナの戦況は、毎日TVのニュースで見聞きする。そして、ロシア国内では情報統制がきつく、一部の市民を除き関心が薄いことなど、バフチーンの生た独ソ戦時とソ連時代のロシアと現在が重なって来る。同時にウクライナと言うことで、ここで前にギンズバーグの新訳された『HOLL吠える』と共に紹介した『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』も出して来た。それと言うのも、ハリー・スミス氏は、ウクライナのイースター・エッグの収集もしていたとのことだったからだ。ハリー氏は、文化人類学的なフィールド・ワークにアメリカン・フォーク・ミュージックの考古学的な採集・多岐に亘る収集など、バフチーンの読者なら喜びそうな仕事をした人だ。普通じゃない〈数奇な人生〉と言うことでも、バフチーンとハリー氏は、重なる部分があることも興味深い。
今度、一年ぶりに『バフチーン、生涯を語る』と共に『ハリー・スミスは語る』も読み返した。再読にも関わらず、二冊とも初めて読んだ時と同じ様に、痺れる。