[“本”との生活] その一
長谷川堯著『神殿か獄舎か』SD選書247(2007年12月 鹿島出版会刊)
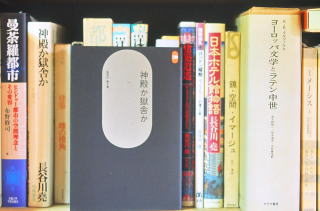
ホームページを始める目的の一つに、それとなく70年代(68年~79年)の研究をしてみたいと言った思いがあった。出来れば、70年代らしい本も紹介したいと思っていたのだ。ところが、創刊の準備を始めてみると、とてもそんな余裕など持てなかった。
基本的に、自分で文章を書いていると、確認や参考のための必要性で本を読んでも、それは本来の「読書」と言った、豊かに時間の流れるものとは別物なのだ。残念だが「本の紹介コーナー」は、ホームページが軌道に乗って、余裕が出来てからでないと、とても出来そうにない感じだった。
しかしここに来て、別に余裕ができたのではないが、やはり面白い本を読んで紹介したくなった。この半月程、何か紹介するとするなら、どの本が良いかあれこれと思い悩んでいた。出来れば、70年代の、忘れられた本が良いが… 。
最初、最近漸く読み始めた、堀田善衛のモンテーニュ伝『ミシェル城館の人』(全三巻)は、どうかと思った。そもそも、このホーム・ページのタイトルも彼の文章に縁がある。『ミシェル城館の人』は、80年代の終わりから90年、堀田善衛最晩年の仕事だ。新しい部類の本だが、堀田善衛は戦後直ぐ作家生活に入り、70年代には、『方丈記私記』や『ゴヤ』など活躍し、わたしも親しんだ作家の一人だ。悪くない選択と思った。
それなのに『ミシェル城館の人』は、読み進んでも一向気分が高揚しないのだった。面白くない分けではない。最晩年の仕事なので、ゴヤの評伝を書いた70年代の様な筆力は期待こそしないが、それに変わる、芳醇な味わいがあっても良いのだが… 大いに期待してるのに、何か淡泊と言うのか、読み進んでも酔いがまわらない感じ。本物の味を知る友人に勧めるとなると、明らかに物足りない。
当てが外れた感じでいたところ、閃いた本が、長谷川堯著『神殿か獄舎か』だ。昨年末、35年振りに新版として復刊されたのだ。
72年、著者の処女作として刊行されたこの本は、既に建築批評として揺るぎない評価を得ている。最も優れた建築評論書の一冊と言うだけでなく、建築を通して近代日本文化のオリジナリティーを掘り起こした本として、必読の一冊でもある。仮に、そんな評価が奇異に思えるとするなら、それは多分、建築と言うジャンルが文学とか美術などに比べて、親しみ薄いからだろう。ぼく自身も、この本を読むまでそうだった。
「読んで、びっくり! 」と言う話に入る前に、個人的な「昔語り」で恐縮なんだけど、この本と著者を知る切っ掛けになった出来事を書いておきたいのだ。
70年代のまっただ中のことだ。美術史を学ぶべく大学に入った、初めての秋、奈良の古寺を巡る「古美術研修」に参加した。ゼミのM先生は、忙しく遅れて、初日引率したのが、今は故人になったT先生だった。
日吉館に荷物を置き、東大寺の南大門をくぐり、大仏殿、二月堂、三月堂を巡り正倉院脇を過ぎ、手貝門を抜け右手に道なりに北山十八間戸まで歩いた。般若坂を登り右手に小さな荒れ寺が般若寺で、この辺りまで来ると市内から至近にもかかわらず、北の外れで郊外の趣だ。西へ幾らか行くと、赤煉瓦の正門と高い壁の奈良少年刑務所に辿り着いた。古美術三昧の奈良にあって、異色な正門と高い壁に遭遇する。
引き返しながら、「監獄や大正期の建築を研究していた、大学院の同級生が前に本を出している… 」と言うT先生と先輩の会話が耳に入った。その時、T先生の同級生の本と言うのが『神殿か獄舎か』だった。
実際にその本を読むことになったのは、卒業後社会人になってからだ。T先生とは、ゼミこそ別ではあったが、奈良の「古美術研修」以外にも謦咳に接する機会は少なくなかった。しかし、いまでも記憶に残るのは、教室での講義ではなく、普段の会話や酒の席での、ふと何気なく語る昔語りや感想だ。
80年代も終わりに近く、小出版社に勤めていたわたしは、アウトドア・ライターとして著名だったAさんに「アウトドアの精神誌」と言った本の企画をお願いした。Aさんの自宅を訪問して、仕事が一段落したら「やって見たい」と言う返事をいただいた。
それが、いよいよ執筆と言う段に、事情でその出版社を止めることになった。引き継ぎをしたいと言うと、Aさんは「何れ機会があって、その企画が出来る時に、一緒にやろう」と言ってくれた。そのAさんも『神殿か獄舎か』の著者と大学で同級生だったことが、直ぐ後にAさんの文章で分かった。
Aさん曰く「ぼくたちが良く似ているのは、アナーキーだって言うことかな… 」
『神殿か獄舎か』では、獄中記を書いた大杉栄が、後の著作ではクロポトキンが引用されるから「アナーキー」と言ったのではなく、Aさんらの権威に寄りかからない生き方を指していることが感じられた。
Aさんとの企画は数年後、凝った文芸書を刊行することで知られた出版社(今はない)が本にしてくれることになり、ぼくも定期的にお宅に伺う機会が出来た。
Aさんの本の件と平行して、ぼくは画廊の企画から雑用までをすることになり、ある時、長谷川氏の建築写真展が出来ないかAさんに話した。Aさんは喜んで、直ぐ先生の連絡先を教えてくれた。それが切っ掛けで、長谷川氏ご本人を知ることが出来たのだった。
長谷川氏の建築写真展の初日に、駆けつけてくれたAさんは、ぼくとの企画の本を完成すると程なくして急逝してしまった。
Aさんが亡くなってから、もっと本の話をしておけば良かったと後悔したものだ。何時か機会があれば、Aさんとその著作についても書きたいと思っている。Aさんは年長で著名だったことなど、どうしても遠慮してしまう。亡くなってから、誰かと気楽に本の話などすることは、余りなかったのではないかと、漸く思い到ったのだった。
四月下旬、東京目黒区美術館於いて『上野伊三郎+リチコレクション展 ウィーンから京都へ、建築から工芸へ』と言う展覧会に関連して、長谷川氏の講演会『建築と工芸デザイン』があった。前もってチラシを得ていたので、参加の申し込みが出来たのだった。氏にお目にかかる機会はあっても、未だ講義や学生(聴衆)を前にして建築を語る姿に接する機会がなかったので、一度聴いて見たい、見て見たいと思っていたので良い機会だった。当日は生憎の雨にも関わらず、会場一杯の聴衆で、御婦人方が多いことも意外であった。どうも、長谷川氏は女性に人気があるのかもしれない。講演内容、パフォーマンスは、自在の域に入ってなにも言うことはなかった。その講演で氏は、建築家村野藤吾のことばとして「良い建築とはなにか? それは、人に威圧感を与えない建築である」とさり気なくおっしゃっていたのが、印象的であった。つい個人的なことばかり書き連ねてしまったが、本題の『神殿か獄舎か』の面白さに就いて、私見をまとめたい。
当然ながらこの文章を書くに就いては、「新版」を入手して読み始め、その印象に従うことにした。何度も繰り返し読んだ本にも関わらず、コンパクトでライトな造本の「新版」で読むと、正しく新刊本を読んでいる感覚に陥るから不思議だ。挿入された写真もモノクロのみ、切手程の極小サイズなのだが、72年版より多数取り入れられ、紙面の印象が一変している。
新版はⅠ日本の表現派 Ⅱ大正建築の史的素描 Ⅲ神殿か獄舎か の三本の論文に絞り、72年版三分の一を占めていた、建築家論と万博批判が割愛され、主題が一層鮮明になっている。
Ⅰでは、明治に行われる国家体制の整備に対して、大正期に表現派の影響を受けながら建築の芸術性、と建築者の「自己性」意識に目覚めた大正時代の若い建築家を掘り起こす。Ⅱに於いては、明治と昭和に挟まれた、大正の建築的可能性を「雌」性として発掘再評価している。Ⅲでは、ⅠとⅡを前提にして、昭和(現在)まで視角を広げて、国家体制を賛美する「神殿建築」の主流に対して、建築の内部に「自己性」を胎む「獄舎」の建築的思惟を明らかにし、それを都市論へと展開して、より解放された建築的感性の可能性を探っている。
ⅠⅡともに大正建築の史的動向を探る研究論文のスタイルを取りながら、現代の建築とそれが妊む思惟への、深く的確な発掘手法と分析力-「知の考古学」と言うことばが流行ったことがあった-で著者はこの後、建築批評家として一時代を画して行くことになる。
Ⅲは、建築のみならず都市論へと批評的眺望を広げた評論だ。ここから、建築史を思想史の文脈へ接ぎ木して、歴史の尺度を明治大正から昭和の現代へぶれることなく展開している。ここで、大正時代の自由思想家大杉栄と戦中戦後の作家活動によって、精神の自由と革命を思索した埴谷雄高、この二人を豊多摩監獄の設計者後藤慶二と共に「獄舎の思惟」者として、再評価している。
大杉栄、後藤慶二らは、75年刊行される『都市廻廊-あるいは建築の中世主義-』においても引き続き言及され、『日より下駄』の永井荷風と共に中世主義(アート&クラフトのウイリアム・モリス)の視点から、日本の近・現代を批判する重要な登場人物(キャラクター)となる。この『都市廻廊』(文庫本もあった)も画期的な本だ。この本に関しては、ここで余り語ってはいられないが、ひとこと言わしてもらうとすれば。江戸情緒濃厚な花柳小説の著者として多くの愛好者を持っていた永井荷風を、都市の遊歩者と言うそれまでにない視点から、近代を鋭く批判する来るべき「中世主義」の一人として再評価し、文学誌の根深い黴を洗い流したのだった。
反時代的で情緒濃厚な小説家と言う評価が定着していた荷風を『都市廻廊』では、その反時代性によって、現代性(常に、過去より現在が勝っているとする)を批判する。「都市論」と言う梃子の支点(視点)により、習慣化した評価を覆すことが可能になったのだった。『神殿か獄舎か』が、建築への発進に向けた強烈な噴射とするなら、『都市廻廊』は第二弾ロケットへ点火され、「都市論」と言う成層圏への飛躍だった。
近年建築への関心が、広く一般化しているとは言え、建築史と建築批評の既刊書籍で、現在も古びることなく読者を魅了するのは、この著者の本以外それ程多くはない。
それと、これは日本の「近代」と言う、歴史的宿命に深く絡んで来ることなのだけれど、一般的に文化や芸術、学問も、西欧の影響やその流派、系譜を問うのが学問になりがちだ。何かに付け「モデルは外国にある」と言うのだ。「萩原朔太郎のオリジンは、ボード-レールにあり」と言う如く。日本の「近代」を脱亜入欧と和・洋の差異に伴う葛藤と見ると、分かり易い。日本の近代の歴史の中で、文学や絵画に建築など文化領域は「近代」と限定の名が付く時、西欧の影響による抜きがたい桎梏(コンプレックス)から逃れられないで来た。
大正期の建築家の種々の試行を読解した『神殿か獄舎か』を読むと、明治に始まった近代化の後を受けた大正期の若い建築家が、西欧の影響を消化して、建築を自らの内発的な表現(「自己性」)へとひたむきに練り上げる姿が、生き生きと再現されている。
ここにあるものは、単なる西欧の模倣などではなく、日本の大正時代に形作られた独自な建築とその世界であることが解る。過去をグサリと批判したり、ありきたりの評価で賛美したり、そう言うことでは歴史を未来に開くことは出来ない。
何かに付け閉塞し切った時代に突入して、文化全体ジャンルを問わず、近代に何が産み落とされたのか、どんな中身(オリジナリティー)を持っているのか、落ち着いて過去を読み直す機会に遭遇しているのじゃないか。
トップページへ戻る