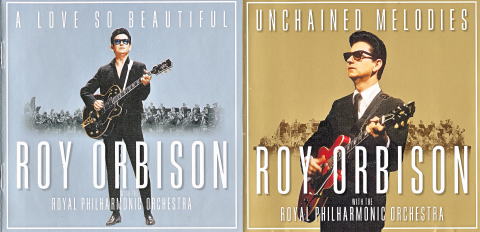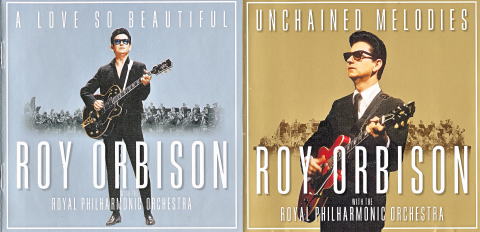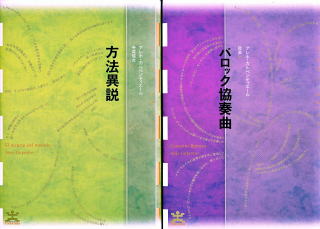リッケンばか-24-
毎年、晩秋を迎えると冬休みとクリスマスにお正月休みに合わせ、クリスマスソング集や久々に会う懐かしい人達とのパーティーで聴くに合わせたこころ暖まる音楽アルバムがリリースされる。今年はロッド・スティアートがロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラと共演盤がリリースされた。
そう言う分けで、おいらも、一昨年末ROY ORBISON with The ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRAされ、更に昨年末にその第二集UNCHAINED MELODIESがリリースされ、2アルバムとも聴き、夏頃よりこの文章を書いていたのだった。
何処かで、申し上げたと思うけれど、3月にインドから帰国して、インドを舞台というか、旅をテーマに小説の執筆をしていた。何時も小説のことばかり考えていても、なかなか書き進めない。好きで良く聴いている音楽のことも語ると、気分が変わり小説の執筆も進む。
ところが、書いたは良いが、何度も文章に手を入れ、次いでホーム・ページで写真を組んでアップする作業が追いつかず、書いた文章が溜まってしまった。そんな分けで、一昨年と昨年のクリスマス・アルバムの話、二周も周回遅れでお読みいただくことになってしまった。余程、ロッド・スティアートのロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ共演盤も入手して、聴いてからその感想も加えてとも思った。
ロットスティアートは、近年スタンダード・ナンバーのアルバムを複数リリースして評判も良い、おいらも嫌いなシンガーではない。
しかしながら、今はどうしても、メローなスタンダード・ナンバーを聴く気分ではない。何れその気になったら、聴いてみるかもしれない。その時はその時で、アルバムことをここで語らせていただくかもしれない。
そんな分けで、何度も手を入れた文章をアップさせていただく。今、聴いている新しいアルバムも無いでは無い。それに就いては、今後通信させていただくのでお持ち下さい。
昨年の‘UNCHAINED MELODIES’は、やはり一昨年末リリースのクリスマスとお正月休み向けアルバムROY ORBISON with The ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA‘A LOVE SO BEAUTIFUL’の続編だ。
クリスマス、お正月など関係なく、おいらは、このアルバムを愉しんでいる。「エッ、今時、ロイ・オービソンかよ! 」と言う人がいるだろう。全くその通りで、正統ロック・ファンを自認するおいらとしては、全く恐縮ものではある。
ロイ・オービソンは、オールディーズのシンガーだ。80年代『オー、プリティー・ウーマン』がリバイバルされるまで、ロイ・オービソンは、大方の日本人には、過去の遠い存在だった。ニール・セダカやポール・アンカ、それにエルヴィス・プレスリーなどと共に、ビック・ネームではあっても、過去のスター、オールド・ヴォイスだったのだ。
その彼氏が突然、ボブ・ディランとジョージ・ハリスンにトム・ペティーを加えて始めたプロジェクトTraveling Wilburysに参加したのは、80年代末だ。
残念ながら、プロジェクトに参加して間もなく亡くなってしまった。きっと時間があれば、ディランやジョージと一緒に、乾いた時代に新鮮で、ノスタルジックな歌を聞かせてくれたはずだ。
それにしても、ディランがノーベル文学賞を受賞した21世紀に、ロイ・オービソンだけではなく、ジョージ・ハリスンにトム・ペティーまで亡くなっていないなんて、嘘だろ。一層、殺伐とした空気が強まって来る。
今、ロイ・オービソンやジョージのヴォーカルを聴く音樂ファンは、ブルーズの様な年季の要る通好みの音楽ファンとは、可成り違うと思う。余り、マニアックな洋楽リスナーじゃないかもしれない。
素直に衒い無く、きれいなメロディーのスタンダードな甘い曲を聴いているのではないだろうか。おれも普段は、スタンダード曲が良いのは、分かっていても、わざわざその曲のオリジナル・バージョンを探してまで、聴き込んだりはしていない。
それが近年、昔親しんだスタンダードを、たっぷり聴き直したい気分になることがある。
おれのスタンダード好みは、きっと、中高生の頃、映画ファンだったからで、洋楽に深入りしたのは、映画音楽の影響があるからだ。トルーマン・カポーティーの小説を映画化した『ティファニーで朝食を』の主題歌、ヘンリー・マンシーニ作曲の『ムーン・リバー』は、好きな曲だ。
この映画でヘップバーンの相手役で、確か、ジョージ・ペパードがデビューしたのだ。ジョージ・ペパードは、おいらが映画を見始めた頃の、お気に入り俳優だ。ご存じいない方もいるだろう。60年代中盤『ブルー・マックス』に『トブルク戦線』と言った、アクション系娯楽映画で活躍した。所謂、名優として語られるタイプの役者ではなかった。
最近、廉価版CDで60年代のサントラ盤を聴くが、さすがもの足りない。やはり誰か、上手い歌手が歌っているものを探すのが良い。
『ムーン・リバー』なら、アンディー・ウイリアムスが直ぐ思い浮かぶ。アンディ・ウイリアムズなら、持ち前の癖のない甘いタッチで、原曲に忠実に歌っているはずだ。60年代後半、レターメンなどスタンダード・ナンバーを檄甘コーラスで聴かせていた。
人には、長く聴いても飽きない好きな曲が幾つかあるものだ。オールディーズと言われるジャンルは、そんな楽曲の宝庫だ。ロイ・オービソンをこの数年、結構「マジ」に聴く様になったのは、そんなスタンダードになった楽曲を多数歌っているからだ。
ところで、CDのカタログを見ていて、ロイ・オービソンの歌を「永遠のファルセット・ヴォイス」と表記してあった。そう、言われてみて、やっと「そうか、ロイ・オービソンの歌い方は、ファルセットなんだ! 」と、一人合点した次第だ。
実は、喉がひっくり返った様に歌う、日本の人男性歌手がいるのだが、おれとしては凄く苦手で、TVで歌うと音を切って映像だけえを見ている。思えば、その歌手の歌い方もファルセットだ。ただ、高い声で歌えばファルセットって言うことでも、良い分けでもないと思うのだ。
ロイ・オービソンのアルバムと共に、昨年末、同じロイヤル・フィルハーモニックとの共演で、今でも愛聴する、カーペンターズのオーケストラ共演アルバムも、同時にリリースされた。カーペンタースなら、オールディーズ・ファンではなくとも、フル・オーケストラとの共演は、全く違和感なく受け入れられると思う。
今回のロイヤル・フィルハーモニックとの共演は、カレンの兄リチャードがプロデユースして、カレンが生前残した最良の歌唱を選んで、フル・オーケストラの伴奏を付けたアルバムで、美しい。
ただ、おいらが何時も聴くカーペンターズのコンピュレーションものゴールド・ディスクは、名演を集めてあることもあり、それと今回の新しい録音曲を聴き比べても、同じナンバーは、もともと完成度が高く、今回のフル・オケ共演には、大きな新味は感じられない。最も、新しいCDは録音は良いし、重複しないナンバーはやはり感動的だ。
特に今度のオケ版CDにはBaby It`s Youが収録されている。最初、聴いた時「おう! ビートルじゃん! 」と思った。
ビートルズでは、どのアルバムにあったかなんて一々記憶はしていない。カーペンターズのライナーを見て、Burt Bacharachとあって「あッそうか!バカラックの曲をビートルズも演っていたんだ! 」と、改めて感動したのだ。思えばカーペンターズは、ビートルズ・フリークだ。Ticket To Rideもカバーして名演だ。カーペンターズはTicket To Rideだけでなくは、プリーズ・ミスター・ポストマンも遣っ演っていて、今でも良く聴かれている。
カーペンターズは、ビートルズのBaby It`s Youを聴く前から、バカラックの曲は、良く知っていたのだろう。
バカラックと言えば、カーペンターズは、Close To Youをカバーしてヒットさせた。この曲もバート・バカラックの曲として、当時から良く知られていた。
カーペンタースが、この曲をカバーする許諾をバート・バカラックに受ける時、原曲にあるイントロのピアノを、原曲通りにするのをバカラック本人から条件にされたと、前にTVでリチャードが話していた。バカラックとカーペンターズは、縁が深いのだ。
ビートルズのベイビー・イッツ・ユーは、デビュー・アルバム、プリーズ・プリーズ・ミーに収録されていたのだ。アルバムのリリースは1963年、東京オリンピックの前年だ。
ビートルズはリバプールとかハンブルグで、バート・バカラックの曲を聴いていたんだろうか。それとも、だれか船員がアメリカからリヴァプールへ持ち帰った、レコード盤で聴いて、いい曲なんで自分たちで演って見たのか。初期にビートルズが演った、スタンダード・ナンバーはどれも、今聴いても良いのだ。
初期、立て続けにリリースされたアルバムには、オリジナルが間に合わなくてスタンダード・ナンバーが多い、と言った評もある。おいらはベイビー・イッツ・ユーの様に、ビートルズの演奏で聴いて知った、スタンダード・ナンバーは少なくない。
ビートルズ演るスタンダード・ナンバーは、今聴いても、イカしている。セカンド・アルバムにあるDevil In Her Heartなんて、1962年のドネーズ-多分黒人女子コーラスだと思うけど-の曲をカバーしていて、とってもポップでイカした演奏だ。
ビートルズは、ロイ・オービソン、プレスリーやバディ・ホリー、チャック・ベリーなど凄く良くロックンロールを聴いていた。
今や、ロイはじめオールディーズ、60年代~70年代のアルバム、コンピュレーションものなど、廉価版CDが容易く入手出来るので、聴き比べも容易に出来る様になった。
確かに、ロイ・オービソンもカーペンターズのCDも、クリスマスから新年にかけての企画に相応しい。クリスマスを家族や親しい友人と過ごす為に、遠くから集まる誰彼と集う時に聴けば、皆の気持ちをホットな思いやりの気持ちにしてくれる。ロイ・オービソンやカーペンターズの曲ならどの曲も、父母から息子や孫まで、全世代の誰が聴いても、違和感なくホットな気持ちに浸ることが出来るものだ。
A LOVE SO BEAUTIFULを聴いてから、感動の余りもとの曲はどんな感じなのか‘The Real…’ロイ・オービソン ザ・ウルティーメイト・コレクションと言う、三枚組CDを入手して聴きまくった。オーケストラを重ねる前のオリジナルも、可成りオーケストラ版に近いことが分かった。ただ、最新のアルバムの方が、ストリングスの音とコーラスの重ね様が、ロイ・オービソンの甘い声を、圧倒的な美しさに盛り上げることに成功している。
こうなると、やはり今聴くならストリングスの入った曲が良い。後に入手したオリジナルのコンピュレーション3枚組は、今は聴かなくなってしまった。
言い忘れるところだった。ロイ・オービソンの第二集UNCHAINED MELODIESには、U2のボーノとエッジがクレジットされたShe's a Mystery to Meやエルビヴィス・コステロThe Comediansのカバーも収録されている。ロイが歌うとこんなに甘くなるのか。
甘いと言えば、Danny Boyは、さすがに感動ものな歌いっぷりだ。つい、思い出すのは、歌謡曲全盛の日本で『ズンドコ節』を小林旭やドリフターズ、氷川きよしまで、それぞれ自前の前歌を付けて歌っていたことだ。ロイ・オービソンのDanny Boyも、ロイ自身用に前歌を付け、圧倒的に盛り上げているのだ。
ロイ・オービソンのDanny Boyには、イーリアン・パイプとかアイリッシュ・パイプと言われる、縦笛が演奏に使われている。多分、ロイ・オービソンは、アイルランド系なのかもしれない。彼の歌を聴いていると、アイリッシュ・トラッドの雄The Chieftainsのパディー・モローニーの歌い振りを彷彿とするからだ。
ロイ・オービソンやカーペンターズの様な、甘いポップスは、近年の音楽界には、居場所が無いかもしれない。それは70年代の様に洋楽が聴かれなくなったことにも、遠因があるのではないだろうか。
Jポップやアイドル全盛の日本では、洋楽ポップスは、余り聴かれないだろう。海の向こうだって、ダンサブルでセクシーなディーヴァ全盛だ。だからこそ、高揚や癒し感覚のある歌唱が、リバイバルされたのが分かるのだ。甘い曲で涙を流すと、精神的緊張が緩みストレスを癒すと言われている。乾いた現実にあってひとは、甘くて、センチメンタルな感覚に飢えているのじゃないか。音楽に依る浄化作用は、格別だ。
さて、調度一年になるだろうか、ダニエル・ラノア『ソウル・マイニング 音楽的自伝』(鈴木コウユウ訳 2013年 みすず書房)のことを述べた直後、ブラッド・トリンスキー&アラン・ディ・ベルナ『エレクトリック・ギター革命史』(石川千晶訳 2018年 リットー・ミュージック)を読んだ。この『エレクトリック・ギター革命史』も『ソウル・マイニング』に劣らず感動的な本だった。ロック系音楽書として、おいらのベスト・ブックに絶対入れたい一冊だ。
『エレクトリック・ギター革命史』は、原題Play It Loud AnEpic History of the Stye,Sound,and
Revolution of the Electric Guitarと言う。日本語版は、B6サイズ、ソフト・カバーのペーパー・バック風ブック・デザインで、いかにもチープな造本だ。こう言う場合「チープ」じゃなく「エコノミーな」と、言わねばならないのだろうが、失敬! 。この本のブック・デザインは、シンプルにも関わらず、本文に脚注と巻末に簡単な年表、細かい活字の索引を含め、何と総頁数540ページにもなり、厚さは驚きの40㎜となっている。エレキ・ギターの開発誌と言うだけではなく、ロック関係の読み物としても、異例な面白さの、ホットな本なのだ。
『エレクトリック・ギター革命史』は、全12章で、第1章でマグネティック・ピクアップの完成を描き、第2章でチャーリー・クリスチャンを、第3章では、ご存じのレスポールやレオ・フェンダー「ビグスビー・アーム」としてその名が残っているポール・ビグスビーらによる、初期の開発史が辿られエレキギターの歴史が、アメリカでのポピュラー音楽の受容と進化の物語が生き生きと誌されている。また、リッケンバッカとビートルズ、ジョージ・ハリスンのエレクトリック12弦のことも、一章をもって語られる。リッケンバッカのエレクトリック12弦に関しては、ギター・マガジンのムックRICKENBACKERやアンディ・バビアック『ビートルズギア』で、既に詳しく語られている。しかし、ムックはリッケンバッカに限定してた、マニアックな内容だった。ビートルズの楽器を丁寧に辿った『ビートルズギア』は、当然ながら楽器の解明に傾き、音楽の考察は読者に任されている。
そんな分けで、ビートルズに就いても『エレクトリック・ギター革命史』で読めば、愛好家的などこか醒めた関わりではない、ギターへの熱情が直に感じられ、われわれを熱くさせる。そして、塞いでいたこころに血が通い、元気になるのだ。

ところで『エレクトリック・ギター革命史』で著者が〈ルシアー〉と言うことばを盛んに使っている。一体〈ルシアー〉ってどう言う意味か気になった。
こんな時、おいらは辞書をひく。最初、英和辞典を見てみたが、それらしい語は見いだせなかった。次いで、仏和辞典をひいた。フランス語の辞典で、バッチリ見つけることが出来た。
luthier [lytje]とは、何と〈弦楽器製造人〉と言うことであった。もとは、リュート-luth [lyt]-から出ているので、現代では正しく〈ギター製造人〉を示すことばと言える。おいらは、以前楽器の業界誌の編集に従事したが、寡聞にして〈ルシアー〉と言うことばは、この本を読むまで知らなかった。
仕事をしている頃は、個人で工房を開いている様なギター製造者は、英語風にギター・ビルダーと言っていた。これからは〈ルシアー〉と言うことばを使わしてもらうことにする。
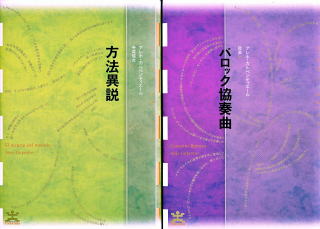
『エレクトリック・ギター革命史』は、読み終えて一年以上経つ。それでも、今もって興奮と感動が去らないでいる。
この本と、例えば、アレッホ・カルペンティエールの『失われた足跡』や『バロック協奏曲』に『方法異説』と言う、音楽が重要なモチーフになっている小説を脇に置くと、まるで異質な世界に感じるかも知れない。大体、カルペンティエールの描く音楽は、彼の小説世界がマジック・リアリズムと言われる様に、渋いと言うか超通人向きの感覚で描かれている。しかし、その突き抜けた音楽への傾倒が「クラシック」とか「ポピュラー・ミュージック」或いは「カリブ海の音楽」と言った、既成のジャンルを超えて音楽の本質を捉えているから面白い。どんなジャンルでも良い、音楽好きなら一度、是非カルペンティエールの小説をお読みいただきたいものだ。
なお、カルペンティエールの『方法異説』(寺尾隆吉訳)は、水声社[フィクションのエルドラード]と言うラテン・アメリカ文学叢書の一冊として、2016年に刊行されている。『バロック協奏曲』も2017年、同叢書に復刊された。昔、サンリオSF文庫に入ってた小説だ。長らく入手困難だった作品が、漸く読める様になったのだ。既に『春の祭典』(柳原孝敦訳 2001年 国書刊行会)も、翻訳されているのだ。
雑誌の特集で良くやる様な-「読む音楽(ロック)」「わたしの○冊」とか言った-想定問答がある。果たして、各自どんな本を選ぶことになるか。何時も、音楽書に関する、想定問答的特集を見て『失われた足跡』や『バロック協奏曲』の様なフィクションが選ればれていないことに、失望して来た。
世の音楽批評家と言われる人の専門的インテリジェンスって、案外読む本に関しては平凡で、退屈な本を選ぶものなのだと知って、いささかならず落胆して来たのだ。しつこい様だが、音楽ファンでカルペンティエールを読んでないなら、この際是、非読んで欲しい。
報告が後になってしまったが、今回もう一つ、一昨年、おいらはVOXのコンボ・アンプ AC30CXX-エイシー・サァーティー・ダブル・エックスと読む-を入手した。そのことをお知らせしたいと思っていたのだ。AC30を入手したとバンドをやっていると言う青年に話すと、最近は、小型アンプも進化して、色んなギターに対応出来ると言う。家でギターを鳴らすなら、わざわざ本格的コンボ・アンプを必要としないと、笑われた。確かに、アンプが自宅に届いて、その大きさにあらためて怯んでしまった。重量32㎏で、一人で二階の自室へ運び上げるのに、大汗をかいた。もともと、おいらはカナダで作られたトレーナーのAC30より一回り小さいアンプが欲しかったのだ。
AC30は12インチ、セレッション・アルニコ・ブルーが二基入っている。目当てのトレーナーは、10インチ程のスピーカーが二基入ったモデルで、90年代半ばには、輸入されていたのだ。輸入代理店に電話で問い合わせると、現在全く入荷していないと言うのだった。おいらは一人で愉しむのが目的だ。それも、老朽化した木造の戸建て住宅で。そんな家で、AC30級のコンボ・アンプを鳴らすのは、変人だと分かっている。しかし、せっかくお気に入りのエレクトリック・ギターだ。ギターに見合ったアンプと言うものがあるのだ。もっとも、現代は他人の音に敏感だ。おれの自宅は近所でも古株の住人なので、音に就いては意識しないでいる。
VOXのAC30は、リッケンバッカのエレクトリック・ギターと共に、初期のビートルズが世に知らしめた。そんなことからも、VOXはリッケンバッカのギターには、相性が良いと言われて来た。ビートルズと共に知れれることとなったVOXだが60年代中盤以降、ビートルズもフェンダーのアンプを使う様になる。ジョージ・ハリスンもギブソンのSGやレスポール・スタンダード、それにストラトキャスターを弾く様になるからとされている。その辺のギターサウンドを知るなら『リヴォルバー』や『ホワイト・アルバム』を聴いてみれば分かる。
おれらの様な一般音楽愛好家は、あれこれ使い比べられる分けでは無い。定評を信じるしかないのだ。何せ、近年ロック系の音楽が時代の流行をリードすることも無くなり、エレキ・ギターへの憧れも薄れて、何につけ〈モノ離れ〉が進行する世界にあって、特殊な趣味や関心に応えは無い。現在、AC30は、伝統的なフル・チューブ(真空管)のアンプだが、配線は基盤により、ソリッド・ステート化されている。かつての様に配線をハンダ付けしている分けではないのだ。昔から言われているのが、ハンダ付けによることで、微妙な歪みを呼ぶとされて来た。一方、ソリッド・ステート化により、個体差が無くなり現代的なサウンドにも対応出来る様になったとされている。
ギター愛好家の間で、現在コンボ・アンプの話題や需要が語られることは、無い。ギターを自宅で弾こうなんて時は、それなりの極小アンプに、場合によればPCを通して音を出すことにもなる。ギターやアンプの種類、それぞれのキャラクターをモデリングしてそれらしく再現すると言うのだ。現在、アンプもギターも目的のブランドを選び演奏すれば、即座にそのキャラクターの音が出る様になっている。あれこれ弾いて、自分のサウンドを探す、手間は無くなった。フェンダーのツイン・リバーブ系が、たまに再生産され市場に出る。ただ、少数生産で高価だ。アマチュアには、とても手が出ない。
今でもAC30が好まれる大きな特徴が、マスター・ヴォリュームを装備していることだ。多くの場合、アンプは音量を上げることで、ギター音を歪ませている。それがマスター・ヴォリュームを搾ることで、歪ませた状態で、音を絞れると言う分けだ。しかし、音を絞っても、それは程度の差で、蚊の泣くような音では、それぞれのギターの個性が分からない。やはり、AC30でなくては出ないギター音を鳴らさなくては、面白くない。リッケンバッカのエレクトリック・ギターは、初期ビートルのサウンドの様な、シャキッとした中音程のトーン・キャラクターのサウンドを出す。乾いた高音のフェンダー系シングルコイルやギブソン系のハムバッカー厚みのある音とも違うリッケンバッカは、現在のギター・サウンドでは、出る幕がない様な気にもなる。
リッケンバッカは、オーバードライブさせずクリーンなトーンで鳴らすと、他のギターに無いリッケンバッカ特有のトーンを感じることが出来る。真空管8本と12インチ・スピーカー二基のアンプで、ギターにより出る音の違いが明瞭に感じらるのだ。特に、クリーン・モードで音量を上げると、リッケンバッカのゲインの定量なプックアップからの音が生き返った。もっとも、それはギター音を聴いた反応で、バンド・サウンドの中で弾いた場合に、果たして個性的な音になるか、分からない。
クイーンが復活したこともあり、ブライアン・メイがAC30を使用していることは、結構知られている。また、U2のエッジやボーノも使用していて、AC30も新しい音楽シーンに対応していることが分かる。今のところ、本来アンプの持つ能力、可能性の間口に立ったところなので、これから発見と感想があったら通信したい。
*
暖かくなり、久々にギターのチューニングを確かめて見た。暖かくなれば弦は伸び、音は低くなり、寒くなると弦が縮み、音は高くなる。季節の変わり目、寒暖差が大きくなると、メーターでチューニングし直す。12弦ギターの副弦は、主弦と太さにかなりの差がある。副弦を調整するには、注意がいる。
そんな副弦のチューニング中に、12弦の四弦の副弦を切ってしまった。後日、新宿に出たので12弦のセット・パックを買うべく、楽器店によった。ところが、エレクトリック12弦のセットが、何故か一つも無い。大体、以前の様にギター弦のセット・パックは、以前の様に多種類店先には出ていないのだ。6弦は、未だ何種か、異なるゲージでセットされているパックが販売されている。驚きなのが12弦ギターのセットが無いことだ。以前は、二~三種類セット・パックが並んでいたのだ。ダダリオとアニーボールの二社がセット・パックを出していた。現在、それが楽器店の店先には無いと言うことなのだ。
個人的においらはアニーボールの方が、ヴィンテッジ感があって好みではあった。しかし、アニーボールの12弦セットは、1弦がコンマ0.9㎜から始まる。おいらは6弦でも12弦ギターでも、一弦は1.0㎜(ないし、1.2㎜)の弦を張っている。普段の感覚からして、0.9㎜では、細いのだ。ダダリオの12弦セットは、一弦が1.0㎜から始まるものがあった。3セット入りパックで購入することが出来た。おいらは6弦も12弦も、このダダリオ製の弦を張っている。なお、フラット・ワウンドのセット-今、あるかは分からない-では、1.1ないし1.2㎜から始まる。おいらはリッケバッカM-660の6弦にフラット・ワウンドを張っている。これは、初期ビートルズのジョン・レノンのサイド・ギターのコード・ワークをコピーする目的があるからなのだ。
以前、良く聞かされたことだが、60年代には、0.9㎜級超ライト・ゲージは、技術的に作れなかったそうだ。誰でも太い弦を張っていたものだ。リヴァプール時代のジョン・レノンは、ピアノ線を引き抜いて、ギターの弦にしたとか、信じられない様な逸話もある。60年代、デュアルモンドの様な中小企業も、ギターからピック・アップから弦まで、せっせと販売していた。日本にコンサートで来て、リッケンバッカのエレクトリック12弦はリースしても、弦は、デュアルモンド製の12弦セットを愛用するギター・プレーヤーのことも聞いたことがある。プロのミュージシャンなら、気に入った弦を買える時に大量に購入しておくだろう。そう言えば、90年代末、リッケンバッカの弦も売っていた。勿論、自社で製造せず、ダダリオとか他社で製造させたものだろう。どうしても拘りたいのなら、そう言う時に大量に購入しておくべきなのだろう。おいらがデュアルモンドに興味を感じるのは、かつて-多分、60年代-リッケンバッカでは、ピック・アップなど部品をデュアルモンド社に下請して製造させていた時期があったと言うことだからだ。テクノロジーの進化でライト・ゲージが製造可能になり、チョーク・ダウンやアップがし易くなり、さらにトレモロ・ユニットも進化した。そこに、種々エフェクターも加わり、エレクトリックなギター・サウンドも随分変わった。もっとも、おいらとしては、ローテクな時代の音の方が、新鮮だ。
新宿では、切れたゲージの弦を単品で買った。単品で一本だけ弦を購入すると、大体、250円程だ。仮にコース全部を単品で揃えると、何と250円×12=3000円になってしまう。以前は確か、12弦セットが1500円程度で買えたはずだ。この際、12弦全部新しく張り替えっても良いと思っていたが、取りあえず切れたまま、他の「コース」-12弦ギターの様に、主弦と副弦が一組に張られる弦の二本一組を、英語ではコースと呼ぶのだ-も全部張り替える積もりだった。
弦を切った時、取りあえず切れた弦のみ外し、他のコースは、そのままの状態にしていた。全コースの弦を外してしまわず、残しておいて良かった。
後日、おいらはパソコンで「12弦ギターの弦」で検索した。すると、何のことはない、以前使ったことのあるダダリオのパックなど、ネット通販で扱っているではないか。一先ず、安心した。それにしても、ギターの弦まで、ネット通販で購入するのかと思うと、嬉しい気がしない。エレキギター関連のパーツも、以前の様に多種類販売していない。最近エレキ・ギターそのものからアンプにいたるまで多様性が感じられなくなっていた。一体、どう言うことなのか。少子高齢化で楽器人口まで激減してしまったのは、随分前の話だ。最近、レコード屋や楽器店をのぞいた印象は、人々の〈モノ離れ〉と言うことだと、思えて来た。
話は変わるが、今度インドへ行く時、おいらは、エレキギターと小さいアンプを、是非とも持って行こうと思っている。アンプは何を持って行くか、決まっている。問題はエレクトリック・ギターの方で、何を持って行こうか、思案しているところだ。 2019年 夏 マンゴーハネダ
トップ・ページに戻る