丂
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僒儖儅儞丒儔僔儏僨傿乕偺怴偟偄彫愢丂亀儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅亁
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂
丂弔傜偟偔側偭偨3寧丄僒儖儅儞丒儔僔儏僨傿乕Salman Rushdie 偺怴偟偄彫愢The Moor`s Last Sigh 丆1995亀儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅亁乮帥栧懽旻栿丂2011擭丂壨弌彂朳怴幮乯傪撉傒巒傔偨丅搑拞丄抁偄拞抐傪嫴傒側偑傜丄堦寧掱偐偗偰撉傒廔偊偨丅
丂崱乽嵟怴偺彫愢乿偲尵偭偨偑丄偙偺東栿彫愢偼丄怴偟偄偲偼尵偭偰傕婛偵嶰擭慜偵姧峴偝傟偰偄偨杮側偺偩丅惓妋偵怽偟忋偘傟偽丄儔僔儏僨傿乕嶌昳偺乽尰嵼偺偲偙傠嵟傕怴偟偄東栿乿偲尵偆傋偒偐傕偟傟側偄丅傢偨偟偼東栿偑弌斉偝傟偰偐傜偙偺弔傑偱丄塈鑸偵傕偙偺彫愢偺偙偲偼丄慡偔朰傟偰偄偨丅乽偦偆尵偊偽丄儔僔儏僨傿乕偺挿曇彫愢偑栿偝傟偰偄偨偼偢偩偭偨両丂乿偲巚偄弌偟丄杮傪庤偵偟偨丅惛乆堦擭埵慜偵弌偨杮偩傠偆偲丄墱晅傪尒偰嬃偄偨丅壗偲2011擭擇寧枛敪峴側偺偩丅憗偄傕偺偱丄娵嶰擭宱夁偟偰偄傞偺偩丅
丂2011擭擇寧偲偼丄3.11偺捈慜偩丅3.11偺偳偝偔偝偵暣傟偰丄杮偺偙偲偼丄偡偭偐傝朰傟偰偄偨偲尵偆偙偲偩丅恔嵭屻偺乽偳偝偔偝乿偲尵偭偰傕丄搶嫗偱偼寁夋掆揹偑偁偭偨掱搙偱丄娭搶偼戝偟偨旐奞偼側偐偭偨丅偦傟偱傕丄偁傟掱偺嵭奞偼丄捈愙旐奞傪旐傜側偐偭偨幰偵傑偱恟戝側塭嬁傪傕偨傜偟偨偺偩丅偦偟偰丄惛恄柺傊偺懪寕偼丄愽嵼揑偵挿偔旜傪堷偒偮偯偗偰偄傞丅
丂嵟傕丄偙偺杮傪怴姧憗乆庤偵偟側偐偭偨偺偵偼丄偦偺庤偺僔儕傾僗側棟桼偑偁傞偺偱偼側偄丅埲慜傎偳儔僔儏僨傿乕偺彫愢傊偺妷朷偑丄柍偄偲尵偆偙偲側偺偩丅彫愢偲尵偭偨傕偺偼丄晠傞條側傕偺偱偼側偄丅偩偐傜偲尵偭偰丄壗帪撉傫偱傕柺敀偄偲偼尷傜側偄丅
丂儔僔儏僨傿乕偲尵偆嶌壠偺偙偲傗丄偦偺彫愢揑摿怓側偳偵娭偟偰丄阒偐帠忣傪抦偭偰偍偄偰傕傜偆昁梫偑偁傞偩傠偆丅戝懱丄嵎傎偳彫愢側偳偵娭怱傪帩偨側偄奆偝傫亅寬慡側庯枴偺曽乆亅偵偼丄儔僔儏僨傿乕偲尵偆僀儞僪宯嶌壠偵丄嫽枴側傫偰偼側偐傜側偄偩傠偆偐傜丅
丂丂
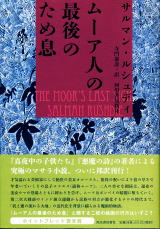
丂偦傕偦傕丄傢偨偟偑儔僔儏僨傿乕偲尵偆僀儞僪宯彫愢壠偺懚嵼傪抦偭偨偺偼丄1981擭A怴暦梉姧偺奀奜暥壔忣曬偲偟偰丄彫偝側婰帠傪尒偨帪偩偭偨丅偦偙偵偼丄僽僢僇乕徿偺崅妟側徿嬥乮堦枩億儞僪乯傪妉摼偟偨丄儃儞儀僀弌恎偺嶌壠偑徯夘偝傟偰偄偨丅婰帠偼庴徿嶌乪Midnight
Children乫傪乽懡嵤側庤朄傪嬱巊偟偰丄嬻憐偲尰幚丄憐憸偲楌巎丄斶寑偲婌寑偑熡慠堦懱偲側偭偨丄寖摦偺僀儞僪尰戙巎乿傪昤偄偨彫愢偲昡偟偰偄偨丅昡敾偺彫愢偱撪梕偑僀儞僪偵娭傢傞偲側傟偽丄傢偨偟偲偟偰偼拲栚偟側偄暘偗偵偼峴偐側偄丅憗懍丄擔杮嫶偺梞彂揦偵晪偒偦偺杮傪拲暥偟偨丅偦偺崰丄嵟弶偺僀儞僪椃峴偐傜婣偭偰丄娫傕側偐偭偨丅
丂偍抐傝偟偰偍偗偽丄傢偨偟偼傔偭偨偵梞彂偼攦傢側偄丅摉慠丄傢偞傢偞拲暥側偳傕偟側偄偺偩丅嬤擭丄傾儅僝儞偵傾僋僙僗偡傟偽梞彂偼丄憲椏傕壗偲徚旓惻偡傜壛嶼偝傟偢丄嵼屔偝偊偁傟偽梻擔偵偼撏偔丅摉帪偼偦傫側曋棙側帪戙偱偼側偐偭偨丅崱偱偼曋棙側僱僢僩丒僔儑僢僺儞僌偑偁傞偙偲傕抦偭偰偼偄側偑傜丄偦傟傕棙梡偟偨偙偲偼側偄丅杮傪攦偆偙偲偼丄尰嵼傛傝愄偺曽偑傓偟傠擬怱偩偭偨偐傕偟傟側偄丅
丂偝偰丄拲暥偟偰悢儢寧屻丄擖壸偟偨巪杮壆偐傜捠抦偑偁傝丄庤偵偟偨偺偼乪Midnight Children乫乮JONATHAN CAPE乯戝敾僴乕僪僶僢僋446儁乕僕偺柍崪側杮偩丅堦墳乽僀儞僪傪晳戜偵偟偨挿曇彫愢乿偲偼暦偄偰偄偰傕丄塸岅斉傪庤偵偟偰傕亅杮暥偺撉傑側偗傟偽亅偦傟傜偟偄僀儞僪晽偺暤埻婥偡傜丄姶偠傜傟側偄丅偙偺杮偼挿偄偙偲亅尰嵼傕亅彂壦偵捔嵗偟偰偄傞亅傔偭偨偵奐偔偙偲偺側偄杮側偺偩丅
丂乪Midnight Children乫偼丄1989擭亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偺僞僀僩儖偱忋壓擇姫杮偵側傝丄帥栧懽旻栿乮亀儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅亁摨條乯偵傛偭偰丄憗愳彂朳偐傜東栿偑弌斉偝傟偨丅憗愳彂朳斉偼丄僇僶乕偺僨僓僀儞傕偦傟傜偟偔寛傑偭偰偄偰丄偙偪傜偙偦庤偵偟偨偔側傞暤埻婥偩偭偨丅峏偵杮暥傪奐偄偨嵺丄巐榋敾300儁乕僕庛偺庤崰側岤偝偱忋壓擇暘嶜偵偟丄偦傟偧傟擇抜慻傒偵妶帤傪偓偭偟傝媗傔崬傫偱偁偭偨丅彫愢岲偒偺傢偨偟偲偟偰偼撉彂梸傪偦偦傜傟偨丅偮偄偙偺東栿杮傕丄峸擖偟偰偟傑偭偨丅抶傟偽偣偵乪Midnight
Children乫偼丄憗愳彂朳斉亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偲偟偰丄擔杮岅偱撉傫偩偺偩偭偨丅
丂亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偼丄1947擭8寧15擔亅僀儞僪偺撈棫偲摨擭亅儃儞儀僀偱惗傑傟偨僒儕乕儉丒僔僫僀偲尵偆庡恖岞偺岅傞丄悢婏側暔岅偩丅撉傒恑傓偵廬偄擛壗偵傕僀儞僪偵嫃偦偆側婱嫠條乆側恖暔偑搊応偟偰暔岅偼揥奐偡傞丅70擭戙屻敿偐傜擬拞偟偰偄偨丄儔僥儞丒傾儊儕僇偺儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉彫愢偺撿傾僕傾斉偺庯傪姶偠偝偣丄旕忢偵報徾揑偩偭偨丅
丂亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偼丄1975擭Grimus偱僨償傿儐乕偟偨儔僔儏僨傿乕偺擇嶌栚偺挿曇彫愢偩丅偙偺彫愢偼丄僀儞僪垷戝棨偲尵偆楌巎偺廳憌偟偨悽奅傪晳戜偵丄閌愩側岅傝傪廳偹偨榖朄傪傕偭偰丄婛偵姰惉搙偺崅偄擹枾側僗僞僀儖傪妋棫偟偰偄偨丅摿偵庡恖岞偺梒彮婜偺夞憐偵偼丄儔僔儏僨傿乕偑幚嵺偵夁偛偟偨儃儞儀僀偺峹奜廧戭抧偵墬偗傞丄拞嶻奒媺偺孅愜偟偨堄幆傪丄旂擏崿偠傝偵尵岅壔偡傞庤榬偼丄擾柉偺嬯擸傗昻偟偝偽偐傝偑尠挊側僀儞僪偺柉廜偺僀儊乕僕傪堦寕偱暐怈偡傞擛偔偩偭偨丅
丂丂
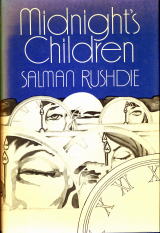
丂丂
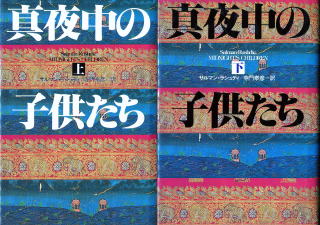
丂亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偺屻丄9儢寧掱偱憗偔傕1983擭姧偺亀抪乮Shame乯亁乮孖尨峴梇栿丂1989擭憗愳彂朳乯偑東栿弌斉偝傟丄憗懍撉傫偩丅偙偺彫愢偼丄僷僉僗僞儞偺撈棫屻偺惌憟偑儌僨儖偵偝傟偰偄傞丅儔僔儏僨傿乕帺恎堦帪婣娨偟偨僷僉僗僞儞傪晳戜偵丄1960擭戙屻敿偵巒傑傞僽僢僪堦壠傪拞怱偵塓傪姫偔惌帯尃椡摤憟傪丄條乆側愭峴嶌昳傗偦傟傜偺暥妛揑庤朄傗儊僞僼傽乕傪嬱巊丄僽儕僐儔乕僕儏偟偰閌愩偵岅傞丅偙傟偵傛傝丄儔僔儏僨傿乕偺僗僞僀儖乮暥懱乯傪寛掕揑偵報徾晅偗偨丅
丂摿偵丄僷僉僗僞儞偼僀儞僪偺惣椬偵崙嫬傪愙偟側偑傜亅偦傟屘偵偲尵偆傋偒偐亅僀僗儔乕儉偲尵偆嫮偄廆嫵怓偵傛傝丄僀儞僪偲懳棫偡傞撈帺側崙偺偁傝曽傕娷傔嫽枴怺偐偭偨丅
丂婛偵憗愳彂朳斉亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偲亀抪乮Shame乯亁偑東栿弌斉偝傟偨崰偵偼丄挊幰儔僔儏僨傿乕偺嵟怴彫愢亀埆杺偺帊亁偑丄僀僗儔乕儉傪朻摢偟偨欓偵傛傝丄儂儊僀僯傪巒傔僀僗儔乕儉尨棟庡媊幰偐傜丄挊幰傊乽巰孻愰崘乿傪敪偣傜傟偨偙偲偑丄僯儏乕僗偵側偭偰偄偨丅
丂
丂偦偺亀埆杺偺帊亁偼丄屲廫棐堦偺栿偱忋姫偑1990擭2寧丄慜怗傟傕側偔姧峴偝傟偨丅懕偔壓姫偼丄摨擭9寧偵姧偝傟傞偺偩偑丄傢偨偟偼忋壓姫偲傕姧峴偲摨帪偵撉傫偩丅偙偺亀埆杺偺帊亁偼東栿杮偺姧峴偐傜掱側偔偟偰丄栿幰偑嬑柋愭戝妛偺僄儗儀乕僞乕撪偱巋嶦偝傟傞偲尵偆惁嶴側帠審偑婲偒偨丅偙偺嶦恖帠審偼丄儔僔儏僨傿乕傊偺乽巰孻愰崘乿偲柍娭學偠傖側偄偲巚傢傟傞偑丄尰嵼傕斊恖偼戇曔偝傟偰嫃傜偢帠審偺夝寛偼嬸偐丄宱堒偡傜暘偐偭偰偄側偄丅
丂傢偨偟偑亀埆杺偺帊亁傪撉傫偩偺偼丄榖戣惈偲尵偆傛傝彫愢壠儔僔儏僨傿乕傊偺擬偄巟帩偑偁偭偨偐傜偩丅偟偐偟丄亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偲亀抪乮Shame乯亁傪撉傫偱丄偦偙偱姶偠偨彫愢偺廩幚搙偲亀埆杺偺帊亁偺姰惉搙偼堎側傞條偵巚偭偨丅偦傟偼亀埆杺偺帊亁偑丄儘儞僪儞偺僀儞僪宯堏柉幮夛傪晳戜偵偟偰偄傞偙偲偲娭傢偭偰偄傞偺偱偼柍偄偐偲巚傢偣偨丅
丂偦傟偵偟偰傕丄僀僗儔乕儉偱偼側偄傢傟傢傟偵偼丄偙偺彫愢偑恄亅傾僢儔乕亅傪旑鎺拞彎偟偰偄傞偲尵傢傟偰傕丄堦岦僺儞偲棃側偄偺偩偭偨丅
丂儔僔儏僨傿乕偼丄儔僥儞傾儊儕僇偵敪偟偨儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺僀儞僪亅撿傾僕傾亅斉偱偁傝丄偙偺撿傾僕傾偺尰嵼傪惗偒惗偒偲昤偔彫愢偺搊応偼丄屄恖揑側偑傜丄儔僥儞傾儊儕僇偺彫愢偺棽惙偵傕斾偡彫愢偺儖僱僒儞僗丄偲尵傋偒報徾傪傕偨傜偟偨丅
丂偦偆偟偨丄婜懸偐傜偡傞偲亀埆杺偺帊亁偺撉屻姶偼丄儔僔儏僨傿乕偺摿挜揑僗僞僀儖偲側偭偨閌愩偽偐傝偑栚棫偪丄憗偔傕儅僫儕僘儉偵捘偪偨姶傪書偐偣偨丅傢偨偟偺暥妛揑僸乕儘乕偐傜丄彫愢偺庡恖岞偑儘儞僪儞偺岼偵亅峲嬻婡偺帠屘偱亅抧崠捘偪偟偨偺偲僔儞僋儘偡傞條偵堦婥偵揮棊偟丄偦傟傑偱偺擬嫸偵堦枙偺堿偑幩偟偰偟傑偭偨丅
丂亀埆杺偺帊亁偺屻1995擭丄僒儞僨傿僯僗僞偵傛傝柉庡嫟嶻壔偝傟偨僯僇儔僌傾扵朘婰亀僕儍僈乕偺旝徫亁乮斞搰傒偳傝栿乯偲97擭抁曇廤亀搶偲惣亁乮帥栧懽旻栿丂暯杴幮乯傕憗懍撉傫偱偼尒偨丅摦婡偼丄偳偪傜偐偲尵偊偽暥妛揑擬嫸偐傜偱偼側偄丅僀儞僪宯彫愢壠偵娭偡傞曌妛揑娭怱偵懀偝傟偰偺撉彂偩偭偨丅側偍亀僕儍僈乕偺旝徫亁偼丄僼儕僆丒僐儖僞僒乕儖亀偐偔傕寖偟偔娒偒僯僇儔僌傾亁乮揷懞偝偲巕栿丂1989擭丂徎暥幮乯偲丄傎傏摨帪婜偵撉傫偩丅擇嶜偼慡偔姶妎偺堘偆暥懱偵傕娭傢傜偢丄僯僇儔僌傾偺僒儞僨傿僯僗僞傊偺岲昡壙偱偼丄廳側傞偲偙傠偑偁偭偨丅
丂
丂尰嵼偺擔杮偱偼丄僀儞僞乕僱僢僩偱撪奜偺彫愢椶偺擖庤偼梕堈偄側偩偗偱偼側偔丄東栿戝崙偲偟偰傕栚妎傑偟偄偲尵傢傟偰偄傞丅妋偐偵丄搒怱偺戝宆彂揦偺暥寍彂偺扞偵偼丄塸丄暷丄暓丄撈丄埳偺傒側傜偢丄儘僔傾傪巒傔偲偡傞僗儔僽岅寳偐傜丄僀儞僪丄僷僉僗僞儞側偳撿傾僕傾偲搶撿傾僕傾拞崙岅寳丄偝傜偵儔僥儞傾儊儕僇亅僕儍儅僀僇傪巒傔僇儕僽奀堟傕娷傑傟傞側偳丄僌儘乕僶儖偵懡條側尵岅丒抧堟偺彫愢傪丄擔杮岅偱撉傓偙偲偑壜擻偩丅
丂東栿偝傟偨嶌昳傗東栿偵朞偒懌傜偢丄塸岅傪墋傢側偗傟偽丄彫愢傕僂僄僽偐傜屄恖偱撉傓暘偵偼搑愗傟側偔庤偵偡傞偙偲偑弌棃傞丅帪戙偼儕傾儖僞僀儉偱丄嫃側偑傜偵偟偰悽奅暥妛傪撉傒摼傞偲尵偆暘偗偩丅
丂偦偺條側儕傾儖僞僀儉側尰戙偵丄東栿彂偑偁傝側偑傜3擭娫傕幐擮偟偰丄嬼慠偺條偵撉傒巒傔傞偲尵偆偙偲偑丄尰嵼傢偨偟偺撉彂儁乕僗偵側偭偰偄傞偺偩丅
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺彫愢
丂
丂偲偙傠偱乽儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉乿偲尵偆偙偲偽偑弌偨偺偱丄怽偟弎傋偰偍偒偨偄偙偲偑偁傞丅偝偒崰乮2014擭4寧17擔乯巰嫀偟偨丄G丒僈儖僔傾丒儅儖働僗偙偦儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺彫愢壠偩偲丄傢偨偟偼妋怣偟偰偄傞偺偩丅
丂婛偵儔僥儞傾儊儕僇偺儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺彫愢偵擬拞偟偰棃偨偙偲傪弎傋偨偑丄2009擭亀惗偒偰丄岅傝揱偊傞亁乮扷丂宧夘栿丂怴挭幮乯偑彂揦偵弌偰偡偖偝傑撉傫偩亅嬤擭丄慺憗偔撉傓側傫偰丄傔偭偨偵側偄亅丅偙偺帪偼婜懸傪忋夞傞撪梕偱丄媣乆偵擬偔側偭偰偟傑偭偨丅傂偄偒嬝偺儔僔儏僨傿乕偺彫愢偼丄愊嬌揑偵撉傑偢丄崱峏側僈儖僔傾丒儅儖働僗偵擬偔側傞側傫偰丄傢偨偟帺恎彮乆堄奜偺姶傕柍偒偵偟傕偁傜偢偲巚偭偨丅儔僔儏僨傿乕偺彫愢偵娭偟偰捠怣偟傛偆偲偟側偑傜丄僈儖僔傾丒儅儖働僗偺杮亅媦傃丄偙傟傑偱東栿偝傟偨儔僥儞傾儊儕僇偺彫愢亅偵廇偄偰岅傞偺傪偍嫋偟婅偄偨偄丅
丂傢偨偟偼70擭戙偵巚弔婜傪夁偛偟偨丅摉帪偺庒幰偵偼弮暥妛傪拞怱偵摨帪戙偺彫愢傪撉傓偙偲偑丄撉彂傊偺擖傝岥偱偁偭偨丅杮棃撉彂偼丄幮夛惈偺柍偄峴堊偱丄幚傕奧傕側偔尵偊偽乽恖惗偱丄壗傕栶偵棫偨側偄乿峴堊偩丅偦傫側杮傪撉傓偲尵偆柍彏偺峴堊丄偦傫側埆暼偵巚弔婜偵愼傑偭偨偺傕丄彫愢傪撉傓夣妝偵愼傑偭偨偐傜偩偭偨丅
丂偦傫側傢偨偟傕丄幮夛恖偵側偭偰偐傜偼丄擬嫸揑偵彫愢傪撉傓偙偲偐傜墦偞偐傞丅80擭戙偵撉彂偺夣妝丄彫愢偺柺敀偝傪慼傜偣偰偔傟偨偺偑丄儔僥儞傾儊儕僇偺儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉亅挿曇彫愢亅偩偭偨丅80擭戙屻敿丄抧壓揝娵僲撪慄偵忔傞偲丄30戙偺僒儔儕乕儅儞晽僗乕僣偺抝惈偑丄愒偄亀儔僥儞傾儊儕僇偺暥妛亁偺堦嶜傪幵撪偱撉傫偱偄偨偙偲傪婰壇偟偰偄傞丅偙偺僔儕乕僘偼丄峀偔撉傑傟傞偙偲傪慱偭偨婇夋偩偭偨丅傢偨偟偵偼偦傟掱偺夁嫀偲傕巚偊側偄偺偩偑丄偦傟偱傕僗儅儂傗僞僽儗僢僩傕搊応偡傞埲慜偺偙偲偵側傞丅偨傑偵揹幵偱搒怱傊弌傞偑丄嬤擭幵拞偱撉彂傪偡傞恖偑偄側偄暘偗偱偼側偄丅偨偄偑偄暥屔杮偐丄幚梡彂偺條偩丅偲偙傠偑扨峴杮偺応崌丄巗塩恾彂娰偐傜庁傝弌偝傟偨杮偑懡偄丅乽壗傪撉傫偱偄傞偐乿偱偼側偔丄帺暘偺杮偠傖側偄偲偙傠偑婥偵側傞丅
丂尰嵼丄挿曇彫愢傕僂僄償偐傜僟僂儞儘乕僪弌棃丄僞僽儗僢僩側偄偟帺傜偺僷僜僐儞偱撉傓偙偲偑弌棃傞偲尵偆丅妶帤慻傒傗杮偺懇乮岤偝偺偙偲偩乯偼丄娭怱偺斖埻偱偼側偔側偭偨偺偐丅妋偐偵丄婘偺廃埻偵杮偑愊傒廳偹傜傟傞亅幚偵丄幾杺偔偝偄亅偙偲傕柍偔丄幚偵傕偭偰恎寉偩丅嬤擭偺暔傪強桳偟側偄儔僀僼丒僗僞僀儖偵僶僢僠儕偲尵偆偙偲偵側傞丅杮傪偄偪偄偪乽幾杺偩両丂張暘偟傠乿偲尵偆丄壠恖偺攍惡傕暦偐側偔椙偄暘偗偩丅
丂椙偄偙偲偢偔傔側偙偲側偺偐丄偦傟偼暘偐傜側偄丅戝懱丄傢偨偟偼幚暔偺杮偑柍偗傟偽丄偙偆偟偰乵捠怣乶偟側偄偩傠偆丅乽暥妛乮彫愢乯丠丂偦傟偼杮偺偙偲偩傠偆両丂乿偲尵偭偨偺偼丄塸崙棳嫵梴恖偱嵟屻偺暥巑丄媑揷寬堦偩偭偨丅
丂
丂80擭戙丄偦傟傑偱儔僥儞傾儊儕僇偺暥妛偲尵偊偽丄婛偵傾儖僛儞僠儞偺儃儖僿僗偑丄椙偔抦傜傟偨懚嵼偩偭偨丅庫嬍偺抁曇傪椙偔偡傞儃儖僿僗偼丄婛偵60擭戙屻敿偵東栿偼側偝傟偰偄偨丅尰嵼丄儔僥儞傾儊儕僇丄儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偵傛傞彫愢偺戙昞嶌偲偝傟傞亀昐擭傕屒撈亁傕1972擭亅僽乕儉偺辍偐埲慜亅婛偵東栿弌斉乮屰丂捈栿丂怴挭幮乯偝傟偰偄偨丅偙偺崰丄枹偩儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偲尵偆偙偲偽偱丄儔僥儞傾儊儕僇偺彫愢慡懱偑拲栚傪梺傃傞偵偼丄帄偭偰偄側偐偭偨丅
丂80擭戙儔僥儞傾儊儕僇暥妛偑僽乕儉偵側偭偨偺偵偼乽儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉乿偲尵傢傟傞暥懱偺挿曇彫愢偵傛偭偰丄撉彂恖傪尅堷偟偨偲尵偆摿暿側帠忣偑偁偭偨偺偩丅愭偢70擭戙屻敿丄偝傝偘側偔僐儞僷僋僩側宍幃偱亀儔僥儞傾儊儕僇暥妛憄彂亁乮崙彂姧峴夛乯偑姧峴偝傟傞丅偙偺僔儕乕僘偵偼丄僇儖儁儞僥傿僄乕儖丄僐儖僞僒乕儖丄僶儖僈僗=儕儑僒丄僾僀僌偺彫愢偑揨傔偰東栿偝傟丄斵傜彫愢壠偺妶摦傪抦傞愗偭妡偗傪嶌偭偨丅
丂杮奿揑偵乽儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉乿偺彫愢偵怗傟傞偙偲偵側傞偺偼丄83擭偵挿曇彫愢傪儊僀儞偵亀儔僥儞傾儊儕僇偺暥妛亁慡18姫乮廤塸幮乯偺姧峴偑巒傑偭偰偺偙偲偩偭偨丅偙偺僔儕乕僘偵偼丄摉帪扨峴杮偱偼梕堈偵東栿弌斉偝傟傞婡夛偑朘傟偑偨偄丄僿價乕側挿曇彫愢偑廂榐偝偰偄偨偺偩丅巐榋敾敔擖傝偲尵偆懱嵸偱丄偦傟偧傟妶帤傪擇抜偵慻傒崬傒丄挿偄嶌昳傕暘嶜偣偢堦嶜偱撉傒捠偣傞偺偩偭偨丅僔儕乕僘拞嵟傕儁乕僕悢偺懡偄彫愢偼丄儉僸僇=儔僀僱僗亀儃儅儖僣僅岞偺夞憐亁乮搚婒丒埨摗栿乯606儁乕僕丅師偄偱僇僽儗儔=僀儞僼傽儞僥亀朣偒墹巕偺偨傔偺僴僶乕僫亁乮栘懞災堦栿乯573儁乕僕丄敔偐傜弌偟偨杮偺岤偝偼38噊掱偵傕側傞丅懠偵傕僶儖僈僗=儕儑僒亀儔丒僇僥僪儔儖偱偺懳榖亁傗僐儖僞僒乕儖亀愇廟傝梀傃亁側偳500儁乕僕媺偺嶌昳偑僔儕乕僘拞嶰暘偺堦傪愯傔偰偄偨丅
丂2000擭傪寎偊傛偆偲偡傞帪婜丄僶儖僈僗=儕儑僒亀悽奅廔枛愴憟亁乮扷丂宧夘栿1988擭丂怴挭幮乯傪撉傫偩丅挷搙丄僇儖僩嫵抍偑擔杮幮夛傪嬃湵偝偣傞帠審偺捈屻偱丄椪応姶偑暲偱偼側偐偭偨丅側偍丄偙偺杮偼丄儔僥儞傾儊儕僇彫愢拞堦嶜杮偲偟偰偺嵟挿乮巐榋敾706儁乕僕丄岤偝45噊乯傪尰嵼傕屩偭偰偄傞丅偦偺屻丄慟偔僇儖儁儞僥傿僄乕儖偺挿曇亀弔偺嵳揟亁乮桍尨岶撝栿丂2001擭丂崙彂姧峴夛乯傕東栿偝傟傞亅543儁乕僕亅丅偦傫側偙偲偐傜丄傢偨偟偵偼乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿偼丄儔僥儞傾儊儕僇偺挿曇彫愢偵墬偗傞尠挊側惈奿偲尵偆堄幆偑挿傜偔偁偭偨丅挿曇偱偁傞偙偲傪乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿嵟廳梫側梫審偲巚偭偰偄傞丅摨孹岦偺彫愢偱傕拞丒抁曇彫愢側傜乽尪憐暥妛乿偲尵偭偨丄捠忢偺僕儍儞儖偱屇傫偱嵎偟巟偊側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂偲傕偐偔丄奺彫愢偺償僅儕儏乕儉姶傪姶偠庢偭偰梸偟偔丄偙偙偱偼嶌昳偺儁乕僕悢傪帵偟偰傒偨丅偙偙偱庢傝偁偘傞彫愢偺敾宆偼丄憤偰巐榋敾偱丄暘嶜偣偢堦嶜偵媗傔崬傫偱偄傞丅摉慠丄儁乕僕悢偑懡偔偲傕丄堦抜慻傒偲擇抜慻傒丄妶帤偺媺悢(戝偒偝)偲峴悢丒帟憲傝偵傛偭偰傕妶帤柺偺枾搙偵堘偄偑偁傝丄摨偠斉宆乮僒僀僘乯偱傕堘偄偑弌偰棃傞偑丄偙偙偱徯夘偟偰偄傞挿曇彫愢偼丄暥嬪側偔幙検偑廩幚偟偰偄傞偙偲傪尵偄偨偐偭偨偺偩丅
丂2008擭丄僶儖僈僗=儕儑僒亀妝墍傊偺摴亁乮揷懞偝偲巕栿丂壨弌彂朳怴幮乯傪撉傫偩丅偙偙偵帄偭偰乽悑偵乿偲尵偆傋偒偐丄儔僥儞傾儊儕僇偺挿曇彫愢偡傋偐傜偔乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿嶌昳偲尵偆昁梫偼柍偔側偭偨偙偲偵丄抶傟偽偣偵巚偄帄偭偨偺偩偭偨丅乮仏乯
丂亀妝墍傊偺摴亁偼丄19悽婭偺彈惈夝曻壠僼儘乕儔丒僩儕僗僞儞偲報徾攈偺夋壠偱僑僢儂偺柨桭丄棟憐偺抧傪僞僸僠偵媮傔惱偭偨億乕儖丒僑乕僊儍儞亅僼儘儔偺懛偵偁偨傞亅丄擇恖偺惗奤傪昤偔彫愢偩丅
丂僼儘乕儔丒僩儕僗僞儞偼1803擭丄僼儔儞僗恖彈惈偲儁儖乕恖抝惈偲偺娫偵僷儕偱惗傑傟傞丅巐嵨偺帪丄晝恊偑朣偔側傝壓憌偺惗妶傪梋媀側偔偡傞丅1821擭丄摥偄偰偄傞愇斉岺朳庡偲寢崶偡傞傕丄戞嶰巕偺擠怭拞偵弌杬偟丄埲屻彈惈偺帺桼偲帺棫傪慽偊傞崲擄側惗奤傪憲傞乮1844擭杤乯丅堦曽丄僑乕僊儍儞偺惗奤偼丄僑僢儂傪巒傔懠偺報徾攈夋壠丒奊夋偲嫟偵椙偔抦傜傟偰偄傞丅崱偱偙偦抦傜側偄恖偼柍偄丄嬤戙奊夋偺嫄彔偩丅偛懚偠偺條偵惗慜偼亅僼儘乕儔丒僩儕僗僞儞摨條亅崲擄偵枮偪偨惗奤偱偁偭偨丅
丂偙偺彫愢偱偼僼儘乕儔丒僩儕僗僞儞偲僑乕僊儍儞偺擇恖傪儌僨儖偵丄揱婰揑側帠暱傪婎偵帺桼偵憿宍偟丄擇恖岎屳偵岅傜傟揥奐偡傞丅偦偺岅傝岥偼僗僩儗乕僩偱丄儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉彫愢偺摿挜偺堦偮偲偝傟傞堦庬偺嶖憥姶偺條側暥懱忋偺崬傒擖偭偨峔惉偼側偄丅巐榋敾堦抜慻傒486儁乕僕亀儔丒僇僥僃僪儔儖偱偺懳榖亁傗亀悽奅廔枛愴憟亁掱偺償僅儕儏乕儉偵偼撏偐側偄偲偼尵偊丄廩暘偵挿曇偺廩幚姶傪傕偨傜偟丄傑偨彫愢偺姰惉搙偱傕挿曇傜偟偄峀偑傝偲鉱枾側揥奐傪尒偣偰偔傟傞丅桪傟偨彫愢偱偁傞偲尵偊偽廩暘偩傠偆丅偙偙偵帄偭偰乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿偲昡偡傞傑偱傕側偄偲姶偠偨偺偩偭偨丅
丂僶儖僈僗=儕儑僒偵偼丄僼儘乕儀乕儖亀儃償傽儕乕晇恖亁傪榑偠偨昡榑亀壥偰偟側偒嬂墐亁乮岺摗梖巕栿丂1988擭丂拀杸憄彂乯偑偁傝丄偦偺拞偱帺傜偺暥妛揑歯岲傪昞柧偟偰偄傞晹暘偑偁傞丅偦偙偱丄帺傜偺彫愢傪偳偆彂偄偰偄傞偺偐丄岅偭偰偄傞丅
丂
丂亙僪僗僩僄僼僗僉乕傛傝僩儖僗僩僀偑丄尪憐揑側傕偺傛傝傕尰幚揑側憂嶌偺傎偆偑岲偒偱偁傝丄傑偨旕尰幚側傕偺偺側偐偱偼丄拪徾傛傝傕嬶徾偵嬤偄傕偺丄偨偲偊偽僒僀僄儞僗丒僼傿僋僔儑儞傛傝偼億儖僲僌儔僼傿乕傪丄夦婏彫愢傛傝偼娒偭偨傞偄戝廜暥妛傪岲傓亜
丂
丂婛偵乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿偑儔僥儞傾儊儕僇彫愢丄偝傜偵嵟怴偺尰戙彫愢偺摿挜揑側乽庤朄乿偲尵偆偙偲偱偼柍偔側偭偰偄傞偲丄抶傟偽偣偵妎偭偨偺偩偭偨丅
丂
丂亀妝墍傊偺摴亁傪撉傫偩梻2009擭丄東栿弌斉偝傟偨僈儖僔傾丒儅儖働僗偺帺揱揑側夞憐亀惗偒偰丄岅傝揱偊傞亁傕丄偦偺岤偝亅堦抜慻傒側偑傜丄偧傠栚偺666儁乕僕偵媦傇亅偼丄擹枾側廩幚姶傪傕偨傜偡丄杮偩偭偨丅
丂偙偺杮偼帺揱揑夞憐偲偼尵偄側偑傜丄儁乕僕悢偐傜傕戙昞嶌亀昐擭偺屒撈亁傗亀懓挿偺廐亁偲斾傋偰丄偄偝偝偐傕尒楎傝偟側偄杮側偺偩丅奆偝傫丄帺傜偺敿惗傪夞憐偡傞僲儞丒僼傿僋僔儑儞偲尵偆偙偲偵側傟偽丄暯慺偺恎偺忋傗彫愢偺傕偲偵側偭偨弌棃帠傪弴彉棫偰偰丄夞憐偝傟傞傕偺偲巚偆偺偱偼側偄偩傠偆偐丅惓偵偦偺捠傝偱偼偁傞偺偩偑丄杮恖偺暯慺偺懱尡傗宱尡偑儔僥儞丒傾儊儕僇傜偟偔擬偔擹枾丄撿暷偺帺慠偺條偵僼傽儞僞僗僥傿僢僋側偺偩丅彫愢摨條丄撉傒庤傪儅儖働僗偺悽奅偵堷偒崬傫偱曻偝側偄丅柺敀偝偼丄彫愢偲斾傋懟怓側偄傕偺偩偭偨丅乽杺弍揑乿偲尵偆偙偲偱傕丄惗拞側彫愢偵偼媦偽側偄夞憐側偺偩丅
丂側偍丄偙偙偵徯夘偟偨埲奜偵傕丄傢偨偟偼儔僥儞傾儊儕僇偺彫愢傪撉傫偱偄側偄暘偗偱偼側偄丅僇儖儁儞丒僥傿僄乕儖亀幐傢傟偨懌愓亁偼丄幐傢傟偨柉懎妝婍傪媮傔偰墱抧偵擖傞榖偱丄斵愱栧偺壒妝揑憿寃傕斀塮偟偰偄偰丄嫽枴怺偄丅傑偨摨挊幰偺亀岝偺悽婭亁乮悪塝曌栿丂1990擭丂悈惡幮乯偼丄僇儕僽奀抧堟偵墴偟婑偣偨僼儔儞僗妚柦偺忥棎傪丄忣姶擹偔昤偄偨挿曇乮擇抜慻傒337儁乕僕乯偩偭偨丅峏偵塮夋揑側庤朄偱抦傜傟傞亀抴鍋彈偺僉僢僗亁偺儅僰僄儖丒僾僀僌傕朰傟偑偨偄丅
丂傕偭偲傕乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿偲尵偭偰傕丄屄乆偺彫愢偱岠壥偺掱偼摨偠偱偼側偄偲尵偆偙偲偵婥偑晅偔丅摨帪戙偺儔僥儞傾儊儕僇嶌壠僈儖僔傾丒儅儖働僗偲僶儖僈僗=儕儑僒丄擇恖摨偠偔椡嶌彫愢傪悽偵憲傝弌偟偰偄偰傕丄嶌壠偦傟偧傟屄惈傗惈奿偑堎側傞偲尵偆偙偲偑丄崱峏側偑傜椙偔暘偐傞偺偩偭偨丅儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺彫愢偲尵偊偽丄傗偼傝丄僈儖僔傾丒儅儖働僗偑偦偺戙昞偲偟偰丄嵟傕憡墳偟偄嶌壠偲巚偭偰偄傞丅
丂乮仏乯僶儖僈僗=儕儑僒偼丄90擭儁儖乕偺戝摑椞慖嫇偱傾儖儀乕儖丒僼僕儌儕偵攕杒丅屻偼儓乕儘僢僷偱彫愢偵愱擮偟偰偄傞偲尵偆丅2003擭敪昞偝傟偨亀妝墍傊偺摴亁偼丄08擭丄壨弌彂朳怴幮乽悽奅暥妛慡廤乿拞偺堦姫偲偟偰姧峴偝傟偨丅彂揦偺儔僥儞丒傾儊儕僇暥妛偺扞偵偼側偄偐傕偟傟側偄丅摨偠僶儖僈僗=儕儑僒亀儔丒僇僥僪儔儖偱偺懳榖亁傗僐儖僞僒乕儖亀愇廟傝梀傃亁傕弶傔偼70擭戙屻敿暿側悽奅暥妛慡廤偺堦姫偲偟偰東栿姧峴偝傟偨偺偩偭偨丅偦偆偟偨斕攧宍幃偼偲傕偐偔丄偙傟傜扨峴杮偟偰撉傑傟側偄偲丄敾抐偝傟偨偺偩傠偆偐丅
丂彉偱側偑傜怽偟弎傋偰偍偔偲丄81擭偵東栿乮栘懞災堦栿乯偝傟偨僶儖僈僗=儕儑僒擇嶌栚偺挿曇彫愢亀椢偺壠乪La casa verde乫亁偼丄95擭丄怴挭暥屔偵側偭偰撉傫偩丅壗偲杮暥679儁乕僕丄夝愢傪娷傓偲700儁乕僕嫮丄岤偝26噊丄杮懱壙奿777墌丄偳偭偟傝偟偨暥屔杮偩丅亀椢偺壠亁偼丄尰嵼娾攇暥屔偵擖偭偰偄傞偑丄娾攇斉暥屔偼擇暘嶜偵側偭偰丄暲偺岤偝偱姧峴偝傟偰偄傞丅側偍丄嵟嬤偼偁傑傝尒偐偗側偄偑亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁傕丄暥屔壔偝傟偰偄傞丅
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亀儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅亁
丂
丂偝偰丄儔僔儏僨傿乕偺亀儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅亁乮帥栧懽旻栿丂1989擭丂憗愳彂朳乯傪徯夘偡傞慜偵丄僈儖僔傾丒儅儖働僗傗儔僥儞傾儊儕僇偺彫愢傊偲榖偑旘傫偱偟傑偭偨丅儔僔儏僨傿乕偺偙偺彫愢偑偳傫側僗僩乕儕乕偐丄傗偼傝怗傟偰偍偒偨偄丅慡懱偼戞1晹丂撪椫傕傔偺壠丂戞2晹丂儅儔僶乕儖丒儅僒儔丂戞3晹丂儃儞儀僀丒僙儞僩儔儖丂戞4晹乽儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅乿偵暘妱偝傟丄彫偝側岅傝乮僄僺僜乕僪乯傪廳偹偰揥奐偡傞丅偙偺彫愢偼100儁乕僕掱亅偦傟偱傕4暘偺1掱偺暘検偩亅変枬偡傟偽寛偟偰挿偝亅亀埆杺偺帊亁偺條側掆懾姶亅傪姶偠偝偣傞偙偲偺側偄彫愢偩丅挷搙丄儔僥儞傾儊儕僇偺儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺彫愢偲庯岦偼摨偠偩丅
丂偙偺彫愢偼亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁摨條丄撈棫屻偺僀儞僪恖亅媽壠偺恖乆亅傪昤偄偰偄傞丅偦偺媽壠偲偼丄億儖僩僈儖峲奀幰偺枛遽偱丄働儔儔廈僐乕僠儞偱崄椏彜傪偟偰偄傞丄儉乕傾恖偺寣傪宲偖僟丒僈儅壠丅傕偆堦偮偼丄儐僟儎恖偲偟偰僗儁僀儞丒傾儞僟儖僔傾偐傜扙弌偟偰丄儃儞儀僀偵棳傟拝偄偨僝僐僀價乕壠偩丅偙偺擇偮偺媽壠丄僝僐僀價乕壠亅僄僀僽儔僴儉丒僝僐僀價乕亅偲僟丒僈儅壠偺堦恖柡亅僆儘乕儔丒僟丒僈儅亅偑丄堶愂娭學傪側偡偙偲偱丄堦憌偺嶖憥傪尒偣丄恖偺娭學傕暋憌偟側偑傜丄巚傢偸揥奐傪側偡丅
丂岅傝庤偼丄僆儘乕儔偲僄僀僽儔僴儉偲偺桞堦偺拕巕儌儔僄僗偵愝掕偝傟偰偄傞丅斵偺垽徧偑儉乕傾乮恖乯偲偝傟乽偨傔懅乿偺庡偼斵偺偙偲偵側傞丅曣恊偼揤嵥揑側夋壠偲尵偆愝掕丅奊夋嶌昳偺儌僨儖偵懅巕傗壠懓傪丄徾挜揑偵攝偟偨尪憐揑偩偑堄枴偁傝偘側乽儉乕傾奊夋乿亅僗乕僷乕丒儕傾儕僘儉丠丂亅傪昤偔夋壠偲偟偰抦傜傟傞偙偲偵側傞丅
丂曣恊偺僆儘乕儔偼丄懠幰傊偺昡壙偵墬偄偰傕摿堎側惈奿偩丅傕偭偲傕丄僆儘乕儔偵廤傑偭偰棃傞幰傕嬌抂側惈奿偺幰偵尷傜傟偰偄傞丅僆儘乕儔偼乽彈恄乿揑側亅暥拞偱偼傎偺傔偐偝傟偰偄傞偩偗偩亅懚嵼偺條偵傕巚偊傞丅懠幰傪埑搢偡傞惈奿偲尵偆偙偲偱偼丄傑偝偟偔亅僀儞僪傜偟偄恄亅僇乕儕乕揑懚嵼偲尵偊側偄偙偲傕柍偄丅僆儘乕儔傪昤偔偙偲偼丄僀儞僪偺儔僔儏僨傿乕棳偺媅恖壔偐傕偟傟側偄丅
丂傕偺岅傝偺慜敿偼丄僆儘乕儔偺堦懓丄僐乕僠儞偱偺崄椏栤壆偑昤偐傟傞丅崄椏栤壆偼丄帪戙偺悥惃偱孹偒丄僆儘乕儔偼僄僀僽儔僴儉丒僝僐僀價乕偲寢崶偡傞丅寢崶屻丄偦偺屄惈揑側奊夋偱慡僀儞僪揑偵抦傜傟傞夋壠偵側傞丅屻敿丄夋壠偱挻僙儗僽偵側偭偨僆儘乕儔堦壠偺儃儞儀僀曢傜偟偵堏傞丅
丂岅傝庤偲偝傟傞懅巕亅屄惈揑側巓払偺拞偺枛偭巕亅偼丄堎忢偵惉挿偑憗偔曅庤偑晄帺桼偵傕娭傢傜偢丄曣恊偺庢傝姫偒偐傜儃僋僔儞僌傪揱庼偝傟丄晧偗柍偟偺儃僋僒乕乮僗僩儕乕僩丒僼傽僀僞乕乯偱傕偁傞丅偦偟偰庡恖岞偩偗偱偼側偔丄彫愢拞偺抝払偼丄堦尒奆偍偲側偟偄偔丄僆儘乕儔偺彈惈揑僷儚乕偵東楳偝傟傞丅抝偑庴梕揑偵昤偐傟偰偄傞偺偼丄擛壗偵傕僀儞僪揑偩偲巚偆偺偼丄傢偨偟偽偐傝偱偼側偄偲巚偆丅
丂拞斦曈傛傝儔僔儏僨傿乕偺儂乕儉丒僞僂儞偩偭偨丄儃儞儀僀傪晳戜偵丄僆儘乕儔堦壠偺廃傝偵婏偭夦側恖暔偑廤傑傞丅偦偆偟偨偁傝偦偆偵柍偄丄婏偭夦乮儅僕僇儖乯側惈奿偺搊応恖暔偲偺傗傝庢傝偵傛傝丄僗僩乕儕乕偑揥奐偡傞丅
丂慜敿偺僐乕僠儞偱偺暔岅偼丄撿奀傕偺偺朻尟塮夋揑亅傢偞偲捠懎惈傪慱偭偨亅側嬻婥姶傪忴偟偰偄傞丅傑偨丄拞斦埲崀丄儃儞儀僀傪晳戜偵偟偨僗僩乕儕乕偼丄斊嵾塮夋傗SF僗僷僀傕偺塮夋偺僷僗僥傿僢僔儏傔偄偨揥奐傪偟偰偄傞丅
丂暔岅偺拞崰丄堎忢偵憗偔惉挿偡傞庡恖岞偺慜偵丄撲偺旤恖夋壠僂儅丒僒儔僗償傽僥傿乕偑尰傟傞丅僂儅偼岻柇偵庡恖岞傗僆儘乕儔偺壠懓偵庢傝擖傞丅旤杄偱庡恖岞傪桿榝偡傞偑丄懱偼嫋偝偢埀偄堷偒偺応強偵丄壗帪傕壗屘偐儃儞儀僀丒僙儞僩儔儖墂偺儕僞僀傾儕儞僌丒儖乕儉傪慖傇丅傢偨偟傕偐偮偰椃偺搑忋丄塸崙摑帯帪戙偺墂偺儕僞僀傾儕儞僌丒儖乕儉偵懌傪摜傒擖傟偨偙偲偑偁偭偨亅偦偙偼帪戙偑偐偭偨晄巚媍側嬻娫偩偭偨亅丅偦偙偼乽尵偆傑偱傕側偔乿偲尵偆偺偐丄摉慠側偑傜埀偄堷偒偵憡墳偟偄応強偱偼側偄丅
丂傗偑偰丄僂儅偼壠懓偵晄榓偺庬傪嶵偄偰丄庡恖岞傪姩摉偵捛偄崬傫偩忋丄庡恖岞傪撆嶦偟傛偆偲寁傞偑丄偁偭偗側偔幐攕偟偰丄搨撍偵帺暘偑巰傫偱偟傑偆丅僂儅偼挷搙丄僆儘乕儔偵懳偡傞塭偺條側懚嵼偲尵偭偨偲偙傠偩傠偆偐丅
丂傢偨偟払偼僀儞僪塮夋偵傛傝丄昤幨傪宱側偔偲傕梕堈偵僀儞僪旤恖偑擼棤偵弌棃忋偑傞丅尰戙偺僀儞僪旤恖偲偼丄僗乕僷乕丒儌僨儖晽偱丄恖岺揑偱柇偵僐働僥傿僢僔儏丄偦傟偱偄偰偄傗偵僄儘僀旤恖偺偙偲偩丅壗偲傕恖岺揑側偦偺僄儘偝偑丄僀儞僪恖彈桪偺枺椡偲尵偊側偄偙偲傕側偄側偄偩傠偆丅偙偙偩偗偺榖丄傢偨偟偼丄寢峔僀儞僪旤恖偺嶌傝暔傔偄偨乮儕傾儕僥傿乕偺柍偄乯僄儘偝偑岲偒偩丅
丂彫愢偺屻敿偼媫揮捈壓丄岅傝庤偵巰偺庤偑怢傃傞丅庡恖岞偼丄撆嶦偺斊恖偲偟偰丄儃儞儀僀偺抧壓悽奅偵廁傢傟傞丅偦偺娫偵僆儘乕儔偑丄偙傟傑偨帠屘偱搨撍偵巰朣偟丄塭偺敄偡偐偭偨晇偺僄僀僽儔僴儉偑丄幚偼尰戙僀儞僪幮夛傪媿帹傞嫄戝帒杮偺夦暔揑側崟枊偱偁傞偙偲偑暘偐傝丄庡恖岞偼晝恊偺婇嬈偵廍傢傟傞丅
丂峏偵儃儞儀僀偱偺暔岅偼丄廔斦傊岦偐偭偰僋儔僀儉丒僒僗儁儞僗偐堦庬傾僕傾宯丒斊嵾塮夋偺忢搮丄棤愗傝偲曬暅偺楢嵔偐傜丄惌帯儃僗偺埫嶦偲敋抏僥儘傑偱婲偙傝丄彫愢偼堦婥偵僋儔僀儅僢僋僗偲尵偆偺偐丄僇僞僗僩儘僼傿乕傊岦偐偆丅廔斦偺傾僕傾宯丒斊嵾塮夋晽偺僇僞僗僩儘僼傿乕傕儃儕僂僢僪晽捠懎塮夋偺忢搮傪僗僷僥傿僢僔儏偟偰偄傞偲尵偆偺偐丄埆憦偄傑偱偺捠懎惈傪堄幆偟偨彂偒曽傪偟偰偄傞丅
丂抁偄嵟廔復偼丄摨帪懡敪僥儘偺崅憌價儖曵夡偝側偑傜偺僇僞僗僩儘僼偺枛丄屘抧傾儞僟儖僔傾乮彫愢朻摢乯傊栠傞丅嵟廔復偼僑僠僢僋丒儘儅儞僗偺摴嬶棫偰偱丄挿偄偙偺彫愢偼掲傔偔偔傜傟傞丅
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儐僟儎恖偺僐乕僠儞
丂
丂傢偨偟偺庤尦偵偁傞擔杮岅斉儘儞儕乕丒僾儔僱僢僩乮戞10斉2003擭8寧乯働儔儔廈僐乕僠儞偺崁傪尒傞偲丄僔僫僑乕僋乮Pardesi Synagogue乯偺夝愢拞丄偦偙偺彴偵巊梡偝傟偨18悽婭拞梩偺拞崙惢庤昤偒桍柾條偺愼傔晅偗摡惢僞僀儖偑丄儔僔儏僨傿乕偺偙偺彫愢偵乽搊応偟偰偄傞乿偲亅傢偞傢偞亅拲婰偟偰偄傞丅
丂傢偨偟屄恖偺椃偵尵媦偟嫲弅偩偑丄傢偨偟偼挿偄椃偵杮傪帩偭偰峴偔偙偲偑側偄丅桞堦偺撉傒暔偲尵偊偽丄僈僀僪丒僽僢僋偺傒偲側傞丅峴偔梊掕偺搚抧偵娭偡傞婰弎偼栜榑丄峴偔梊掕偺側偄応強偵娭偟偰傕丄撉傓傕偺偑柍偄偺偱丄僈僀僪丒僽僢僋傪傂偨偡傜撉傓偙偲偵側傞丅偙偺戞10斉儘儞儕乕丒僾儔僱僢僩擔杮斉偼丄傢偨偟偑2008擭偵峴偭偨僀儞僪椃峴摉帪丄嵟怴斉偩偭偨丅偙偺帩偪曕偒偵晄曋偙偺忋側偄暘岤偄亅偪側傒偵丄1000儁乕僕嫮亅僈僀僪丒僽僢僋拞乽彫愢偵昤偐傟偨乿偲尵偆婰嵹亅幚嵺偺彫愢偵尵媦偝傟傞亅偼丄婰壇偡傞尷傝儔僔儏僨傿乕偺偙偺杮偑桞堦偩丅僈僀僪丒僽僢僋偑傢偞傢偞尵媦偡傞彫愢偲偼丄梋掱廳梫側嶌昳偲尵偆堄枴偱傕偁傞偺偩傠偆偐丅椃偺嵟拞偵巚偭偨丅
丂偙偆偟偰10擭埲忋傕宱夁偟偨尰嵼丄擔杮偱儔僔儏僨傿乕偺摉奩嶌昳傪撉傫偱巚偆偵丄廳梫嶌昳偲尵偭偨堄枴崌偄偱偼柍偄條偩丅偁偔傑偱僈僀僪丒僽僢僋偺扴摉幰偺丄昅偺惃偄偐傜偺偙偲偺條偵巚偭偨丅偙偺嵺偩偐傜丄僐乕僠儞偑偳傫側偲偙傠偐愢柧偟偰偍偙偆丅Cochin乮Kochi乯偼丄撿僀儞僪傾儔價傾奀娸乮儅儔僶乕儖乯偵柺偟偨乽僶僢僋丒僂僅乕僞乕乿偲尵偆塣壨傗撪奀丄儔僌乕儞偑暋嶨偵擖傝偔傫偩揤慠偺峘挰偩丅崄椏杅堈偺惙傫側帪戙偐傜抦傜傟偨働儔儔廈亅廈偺拞掱亅偺峘挰偵偁偭偰丄嬤擭偼廈搒僩儕償傽儞僪儔儉偵傕彑傞偲傕楎傜側偄斏壺側亅娤岝抧壔偺恑傫偩亅峘榩搒巗偩丅
丂僐乕僠儞偺拞怱偼丄揝摴墂偺偁傞僄儖僫僋儔儉丅儃乕僩忔傝応偐傜鋢偱峴偒棃偡傞丄僼僅乕僩丒僐乕僠儞偑丄崄椏杅堈偑惙傫側帪戙偺尨僐乕僠儞偲尵偆傋偒応強偩丅偙偙偵偼丄億儖僩僈儖恖偵傛偭偰戱偐傟偨挰傜偟偔丄屆偄嫵夛亅St
Francis Church傗Santa Cruz Basilica偑偁傞丅偙偙偺撿懁偼Mattancherry偲尵偄丄偐偮偰億儖僩僈儖恖偺嫃廧抧嬫偩偭偨僄儕傾偩丅尰嵼Mattancherry抧嬫偵偼丄Palace亅1633擭丄僆儔儞僟恖偵傛傝夵廋偝傟偨偺偱暿柤Dutch
Palace偲尵傢傟傞亅偑偁傝丄嬤偔偵僔僫僑乕僋傕巆偝傟丄嫟偵岞奐偝傟偰偄傞丅彫愢拞偺奩摉売強傪堷梡偟偰傒傛偆丅
丂
丂乗亙佱擇偮偲偟偰摨偠傕偺偼側偄佲丅僉儕僗僩楋1100擭偵僄僛僉僄儖丒儔價偵傛偭偰桝擖偝傟偨栺12僀儞僠×12僀儞僠偺峀搶嶻僞僀儖偑彫偝側僔僫僑乕僌偺彴丄暻丄揤堜偵挘傝弰傜偝傟偰偄偨丅偦偺僞僀儖偵偼揱愢偑晅偒傑偲偄巒傔偰偄偨丅帪娫傪偐偗偰扵傞偲惵偲敀偺惓曽宍偺堦偮偵帺暘偺暔岅偑尒偮偐傞偲尵偆恖偑弌偰偒偨丅僐乕僠儞偺儐僟儎恖偺暔岅傪揱偊傞偨傔偵丄僞僀儖偵昤偐傟偨奊偑悽戙傪宱傞偛偲偵曄傢傝摼傞偟丄曄傢傝偮偮偁傞偐傜偱偁偭偨丅僞僀儖偼梊尵側偺偩偑丄偦偺堄枴傪夝偔尞偑嵨寧傪宱傞拞偱幐傢傟偰偟傑偭偨偺偩偲怣偠偰偄傞恖傕偄偨丅亜乮P79乯
丂偳偆傕丄偝掱堷梡偵抣偡傞堦愡偱偼側偄姶偠偑偡傞丅偣偭偐偔丄堷偒幨偟偨偺偱丄徚嫀偡傞偺傕傕偭偨偄側偔巚偄丄偛棗偵偄傟偨偗偳丅擛壗偵傕儔僔儏僨傿乕傐偄偲偙傠傪愗傝庢傠偆偲巚偆偲丄寢峔側暘検傪彂偒弌偝偹偽側傜側偄丅傢偨偟偲偟偰偼丄奆偝傫帺傜撉傫偱梸偟偄偺偩丅
丂偝偰丄傢偨偟偼80擭戙枛僔僫僑乕僌傪朘傟偨偗傟偳丄僞僀儖傪尒偨婰壇偙偦偁傞偑丄偳傫側恾暱偱偁偭偨偐偼丄妎偊偰偄側偄丅彫愢偱偼丄僞僀儖偵廇偄偰僝僐僀價乕壠偺塀嫃晈恖偑彴傪攪偄夞偭偰乽惵偄僞僀儖偺拞偵枹棃偑尒偊傞乿偲偐丄偦偙偵昤偐傟偨奊偵乽梊尵揑偵彫愢偺搊応恖暔偑昤偐傟偰偄傞乿側偳偲丄庡恖岞偺曣恊偺婰壇偲偟偰丄壗搙傕尵媦偝傟傞偙偲偵側傞丅
丂丂

丂丂

丂僈僀僪丒僽僢僋偵傑偱丄儔僔儏僨傿乕偺偙偺彫愢偺偙偲偑怗傟傜傟偰偄傞偙偲偼尵偭偨丅幚偼僐乕僠儞偺崁偵偼乽僐僠偺儐僟儎恖乿偲尵偆丄埻傒夝愢傑偱憓擖偝傟丄偦偙偱偼撿僀儞僪偵墬偗傞儐僟儎恖偺懚嵼偵廇偄偰抁偄側偑傜夝愢偑慻傑傟偰偄傞偺偩丅偦傟偵傛傞偲丄儐僟儎恖偑嵟弶偵偙偺抧偵棃偨偺偼丂乗亙僶乕僗僇儔丒儔償傿丒償傽儖儅儞1悽乮962乣1020擭乯偺帪丄儐僟儎恖彜恖僕儑僙僼丒儔僶儞偵Anjuvannam乮僐僪僁儞僈儖乕儖嬤峹乯偺懞傪儐僟儎墹偺崙偲偟偰摑帯偡傞偙偲傪彸擣偟偨亜乗丂偙偲偐傜巒傑傞偲丄婰嵹偝傟偰偄傞丅傑偨丄僐乕僠儞偺儐僟儎恖壒妝偼丄僶價儘僯傾偺塭嬁傪庴偗偨傕偺偩偲尵偆偙偲傕彂偐傟偰偄傞偺偩丅
丂偙偙傑偱彂偄偰乽僶價儘僯傾乿偺塭嬁偑偳傫側傕偺側偺偐丄夝愢偟偰偄側偄偲偙傠偑丄偄偝偝偐側傜偢丄婥偵側傞偲偙傠偩偱傕偁傞丅偦偟偰丂乗亙僐乕僠儞偺儐僟儎恖僐儈儏僯僥傿乕偼丄2002擭4壠懓14恖亜乗丂偲偁傞丅偔偦岤偄僈僀僪丒僽僢僋拞丄撿丒杒僀儞僪傪捠偠偰儐僟儎恖偵娭偡傞婰弎偑偁傞偺偼丄僐乕僠儞偺傒偩丅儓乕儘僢僷偺搶偺奜傟偺姶妎亅億儖僩僈儖亅傗儐僟儎恖偺棳楺偺寣偡傜暔岅偵拲偓崬傓偙偺偵側偭偨偙偲傕尵偭偰偍偐偹偽側傜側偄丅
丂姫枛丄栿幰偼夝愢偱乽偁傞儃儞儀僀偺椃峴埬撪彂偼偙偺彫愢傪儃儞儀僀傪抦傞偨傔偺嶲峫彂偲偟偰偁偘偰偄傞丅乿偲尵偆偑丄偦偺乽椃峴埬撪彂乿偲偼丄偳傫側杮偱偳傫側撪梕側偺偩傠偆丅摨偠條偵戞堦晹偺僐乕僠儞偱偺暔岅傪嶲峫偵丄幚嵺偺僐乕僠儞傪娤岝偡傞偺傕丄壜擻側條偵昤偐傟偰偄傞偺偩傠偆偐丅
丂幚嵺偺僐乕僠儞偵娭偟偰丄彫愢偺婰弎偱偼丄巹尒側偑傜娤岝埬撪偵偼側傜側偄偩傠偆丅偲尵偆偺傕2007擭丄僶僗偱撿偵崀傞嵺僄儖僫僋儔儉傪捠夁偟偨帪偺嫮楏側報徾偑偁傞偐傜偩丅
丂尰嵼憤徧偝傟傞僐乕僠儞偼丄奜奀Lakshdweep奀偲僶僢僋僂僆乕僞乕Vembanad屛偺弌夛偭偨奀悈堟偲扺悈擖傝岎偠傞抧曽搒巗偩丅撪奀偵偼丄償僅儖僈僢僥傿乕丒僷儗僗偱抦傜傟傞Bolgatty搰傗Vypeen搰偑悈偵晜偐傫偱偄傞丅側偍丄僟丒僈儅壠偺娰亅暿搹偼丄僀儞僪偱偼僠儍儞僨乕僈儖偱抦傜傟傞儖丒僐儖價儏僕僃偺愝寁偲偄偆憐掕亅偼丄偙偺償傽僀僺乕儞搰偵岦偒崌偆乮丠乯乽僇僽儔儖搰乿亅僈僀僪丒僽僢僋偵偼尒偁偨傜側偄亅偵側偭偰偄傞丅
丂僼僅乕僩丒僐乕僠儞傊偼丄僕儑僢僥傿乕偐傜鋢偱峴偒棃弌棃傞丅奀娸晅嬤偵僇僞僇儕丒僟儞僗偺幚墘応偲鋢忔傝応偑偁傝丄壗帪傕婫愡奜傟亅僆僼丒僔乕僘儞亅偺條偵丄奜崙恖娤岝媞偑偪傜傎傜偄傞偩偗偩偭偨丅僶僗掆晅嬤偐傜丄嶶曕偑偰傜曕偄偰丄搑拞偺僀儞僨傿傾儞丒僐乕僸乕丒僴僂僗偱儈儖僋丒僐乕僸乕傪堸傫偩傕偺偩丅
丂幚嵺偺僐乕僠儞偵娭偟偰丄彫愢偺婰弎偱偼丄巹尒側偑傜娤岝埬撪偵偼側傜側偄偩傠偆丅偲尵偆偺傕2007擭丄僶僗偱撿偵崀傞嵺僄儖僫僋儔儉傪捠夁偟偨帪偺嫮楏側報徾偑偁傞偐傜偩丅擬懷僕儍儞僌儖偺崙働儔儔廈偺帄傞強丄楌巎偺曅嬿偵朰傟傜傟偨応強傑偱丄90擭戙埲崀偡偝傑偠偄嬤戙壔偲尵偆偺偐丄奐敪偵傛傝寖曄偟偰偄傞偐傜偩丅
丂僐乕僠儞偲偰椺奜偱偼側偄丅僄儖僫僋儔儉偺拞墰僶僗掆偼丄栚敳偒捠傝偐傜堦嬝擖偭偨強偵偁傞丅偟偐偟丄僶僗掆偙偦摨偠応強偵偁偭偨偑丄廃曈偼姰慡偵曄傢偭偰偄偨丅傑偨丄僄儖僫僋儔儉偺儊僀儞丒儘乕僪偼丄偐偮偰峴偒岎偆尰抧恖傕傑偽傜側抧曽搒巗偺戝捠傝偩偭偨丅尰嵼丄嬥惢昳傪埖偆曮忺揦偲崅媺儗僗僩儔儞偑啻傔偄偰丄働儔儔偺乽嬧嵗捠傝乿偲壔偟偰偄傞丅傢偨偟偑峴偭偨80擭戙弶傔丄僼僅乕僩丒僐乕僠儞偺儂僥儖偵偼丄壗帪傕枮幒偱攽傑傟側偐偭偨丅椬挰儅僞儞僠僃儕乕偵偼丄摉帪僶僢僋丒僷僢僇乕岦偒偺廻偑堦尙偁偭偨丅偙偙傕枮幒偱丄壗帪傕攽傑傟側偐偭偨丅朘傟傞娤岝媞偑懡偔偰丄儂僥儖偑庢傟側偄偺偱偼偄丅傕偲傕偲廻偑偑擇尙偟偐側偔丄嬌抂偵晹壆悢偑彮側偔攽傑傟側偄丄偲尵偆偙偲側偺偩丅巇曽側偔丄僄儖僫僋儔儉偵廻傪尒偮偗偨丅
丂僈僀僪丒僽僢僋偱偼丄尰嵼乽偍抣懪偪側儂僥儖偼丄僼僅乕僩丒僐乕僠儞偲儅僞儞僠僃儕乕偵廤拞偟偰偄傞乿偲偁傞丅偐偮偰偺偙偲傪巚偊偽丄偦傟亅儂僥儖偑廤拞偟偰偄傞亅偼丄斵偺抧偑寖曄偟偨偲尵偆偙偲偩丅尰嵼偺僐乕僠儞偵偼丄彫愢偱尵偆偲偙傠偺僉儞儅傗僋儘乕僽丄惵層灒丄偺嬯崄偼丄崱傗攔婥僈僗偵偐偒徚偝傟偰丄幟傇偡傋傕側偄丅乽彫愢偲尰幚偼丄堘偆乿偲僋乕儖偵偆偦傇偔偵偼丄働儔儔廈傪抦偭偰偄傞傢偨偟偵偼丄條乆側婰壇偑擼棤偵晜偐傃丄壐傗偐偱偼偄傜傟側偄丅
丂偙偺彫愢偼丄暔岅偺巒傔偵僐乕僠儞傪晳戜偵慖傫偩偙偲偱丄偙偺彫愢偵僀儞僪揑側偩偗偱偼側偄儓乕儘僢僷搶抂偺姶妎丄僀僗儔乕儉傗儐僟儎恖偺棳楺偺寣偡傜丄拲偓崬傓偙偲偵側偭偨丅
丂偙偙偱丄撿僀儞僪偺儐僟儎恖偲尵偆偙偲偑弌偰偒偰丄偁傞偙偲傪巚偭偨丅偦傟偲尵偆偺偼丄僐儘儞僽僗乮僋儕僗僩僶儖丒僐儘儞乯偵傛傞僀儞僪峲楬敪尒傊偺峲奀偲丄僀儀儕傾敿搰偐傜偺儐僟儎恖捛曻亅1492擭亅偑丄婏偟偔傕帪傪摨偠偔偟偰偄偨偲尵偆丄楌巎偺揮姺揰偵娭傢傞偙偲偩丅僐儘儞僽僗偲儐僟儎恖偵娭偟偰徻偟偔偼丄摽塱鷔亀償僃僯僗偺僎僢僩乕偵偰丂斀儐僟儎庡媊巚憐巎傊偺椃亁乮1997擭丂傒偡偢彂朳乯丄憹揷媊榊亀僐儘儞僽僗亁乮1979擭丂娾攇怴彂乯偺擇挊偑偁傞偺偱丄惀旕偛棗捀偒偨偄丅
丂偦偺亀償僃僯僗偺僎僢僩乕偵偰亁偵傛傟偽丄8悽婭乣15悽婭僀儀儕傾敿搰偵斏塰偟偨僀僗儔乕儉丒僗儁僀儞亅儉乕傾恖偺亅丅偙偺帪婜僗儁僀儞丒僀儀儕傾敿搰偙偦惣墷嵟戝偺儐僟儎恖抧堟偩偭偨偲尵偆偺偩丅僗儁僀儞偺挿擭偵榡傞乽崙搚夞暅塣摦乮儗丒僐儞僉僗僞儞僪乕儖乯乿偵傛傝丄1492擭僌儔僫僟偑娮棊偟丄悑偵敿搰偐傜僀僗儔乕儉惃椡偑堦憒偝傟傞丅摨帪偵僀僗儔乕儉暥壔偺扴偄庤偩偭偨儐僟儎恖傕丄僀儀儕傾敿搰偐傜捛曻偺桱偒栚偵偁偆丅
丂摨偠擭丄僐儘儞僽僗偼嶰鋤偺慏偱丄僀儞僪峲楬傪戱偔栚揑傪懷傃僕僃僲償傽傪弌峲偟偨丅偁傢傛偔偽乽墿嬥偺崙僕僷儞僌乿偵摓払偟傛偆偲偡傞栚榑尒偩偭偨丅偦偺峲奀偵傛傝丄傾儊儕僇戝棨傪敪尒偟丄偦偺晉偼丄儖僱僒儞僗傪巒傔惣墷偺暥壔傪巟偊傞宱嵪揑婎慴偵側偭偨偲丄楌巎偱偼岅傜傟偰偄傞丅僐儘儞僽僗偺峲奀傪宱嵪揑偵巟偊偰偄偨偺偑丄摉帪偺儐僟儎帒杮偩偭偨偲尵偆偺偩乮憹揷亀僐儘儞僽僗亁乯丅儐僟儎恖捛曻傪夞旔偡傞偨傔偐丄傕偼傗抶偒偵幐偟偨僾儘僕僃僋僩偩偭偨偺偐丄枹偩偵丄撲偑懡偄丅
丂傑偝偐丄崱擔僐乕僠儞偵巆傞儐僟儎恖偑丄斵偺帪乮1492擭乯偺枛遽偩偲偼巚偊側偄偑丄偦傟偱傕崄椏傪巒傔偲偡傞奀梞杅堈傊偺堄梸偑丄斵傜傪偙偺抧偵棃偝偟傔偨偙偲偼丄斲掕偱偒側偄偩傠偆丅1961擭傑偱丄億儖僩僈儖椞偩偭偨僑傾偼丄僼儔儞僔僗僐丒僓價僄儖巒傔僀僄僘僗夛偲偺娭傢傝偑怺偄挰偩丅杅堈傕偝傞偙偲側偑傜丄晍嫵妶摦偺堦戝僙儞僞乕偩偭偨丅僑傾偼擔杮偲楌巎揑宷偑傝傕偁傞応強偩丅偦偺僇僜儕僢僋丒僉儕僗僩嫵偺僑傾傪岝偺摉偨傞応強乮乽墿嬥偺僑傾乿乯偲偡傞側傜丄僐乕僠儞偼儐僟儎恖偵傛傞丄堿偺擹偄楌巎傪懷傃偰偄傞偲尵偊偦偆偩丅
丂側偍摽塱偵傛傟偽丄僀儀儕傾敿搰偺撍抂丄尰嵼億儖僩僈儖偵墬偗傞僔僫僑乕僋偺巆懚偼丄桞堦拞晹偺僩儅乕儖偵妋擣弌棃傞偩偗偲尵偆丅偦偟偰丄偙偺僩儅乕儖偺柤暔偑尰嵼丄壗偲僠僉儞丒僇儕乕偩偲尵偆偙偲側偺偩丅
丂丂

丂丂

丂丂

丂儔僔儏僨傿乕偑昤偔応強傕丄扨偵愝掕偝傟偨応柺傗攚宨偱偼側偄丅彫愢偺晳戜偲尵偆傕偺偼乽僎僯僂僗丒儘僉乮抧偺楈乯乿傪嫮偔堄幆偟偰昤偐傟傞丅儔僔儏僨傿乕偺嵟傕嫮偔堄幆偟偰偄傞悽奅丄尵偆傑偱傕側偔僀儞僪垷戝棨偩丅梒彮婜傪夁偛偟丄婰壇傪夞屭偡傟偽朰傟傜傟側偄挰偲尵偆偙偲偵側傟偽丄偦傟偼儃儞儀僀偩傠偆丅偦偟偰丄嶌壠偲偟偰戝惉偟丄僄僋僓僀儖偟偰峴偔悽奅丄儘儞僪儞傪巒傔僯儏乕丒儓乕僋側偳墷暷偺搒巗偑偮偯偔丅儔僔儏僨傿乕偺彫愢偼丄屘嫿憆幐幰偺暥妛偐傕偟傟側偄丅巚偊偽僀儞僪恖傎偳丄壺嫛偺條偵僀儞僪傪棧傟側偑傜丄棧傟偰峴偗偽峴偔掱丄僀儞僪揑側傾僀僨儞僥傿僥傿乕傪嫮偔偡傞恖乆側偺偐傕偟傟側偄丅
丂儔僔儏僨傿乕偺屄恖揑巚偄傪撉傒夝偔側傜丄庡恖岞偑惉恖偟偰儃儞儀僀傊弌偰偐傜偼丄傕偲傕偲儃儞儀僀巕偩偭偨儔僔儏僨傿乕偼丄庡恖岞偺偙偲偽傪庁傝偰丄儃儞儀僀傊偺巚偄傪岅傜偣偰偄傞偲尵偊傞偩傠偆丅幚嵺僗僩儕乕僩傗抧嬫偺柤慜傪楍嫇偟丄偦傟傜傪乽傢偑幐傢傟偨奨乮儅僀丒儘僗僩丒僔僥傿乕乯偺岾偣側儅儞僩儔傛丅偙傟傜偺応強偼塱媣偵巹偐傜摝偘嫀偭偰偟傑偭偨丂P266丂乿偲丄弎夰偟偰偄傞丅偍偦傜偔儃儞儀僀偺昤幨偵偼丄亀恀栭拞偺巕嫙偨偪亁偵傕偁偭偨條偵丄儔僔儏僨傿乕偺乽挰偭巕乿揑姶妎偑敪業偟偰偄傞偺偩傠偆丅挰偵堢偭偨傢偨偟偵偼丄暘偐傞婥偑偡傞丅
丂丂

丂側偍亀儘儞儕乕僾儔僱僢僩亁儃儞儀僀偺崁傪丄堦捠傝亅僓僢偲亅撉傫偱傒偨丅儔僔儏僨傿乕偵娭偡傞尵媦偼丄慡偔尒偄偩偣側偐偭偨丅傑偨丄儃儞儀僀偵娭偟偰丄抁偄懾嵼偟偐宱尡偟偰偄側偄偺偱丄巆擮側偑傜屄恖揑偵偼丄彂偔傋偒偙偲偑側偄丅億僕傪惍棟偟偰儃儞儀僀偺幨恀傪敪尒偟偨偺偱丄偛棗偵擖傟傞偙偲偵偟偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
東栿偺擔杮岅丂
丂僈儖僔傾丒儅儖働僗亀惗偒偰丄岅傝揱偊傞亁傪撉傓偲丄儅儖働僗偺壠懓傗夁嫀偺弌棃帠偑乽偁傝摼偞傞乿姶妎偵枮偪偰偄偨偑屘偵丄偦傟傪岅傞偵偼丄僼傿僋僔儑儞乮亀昐擭偺屒撈亁乯偺懱嵸傪庢傜偞傞傪摼側偐偭偨偙偲偑暘偐傞丅儔僔儏僨傿乕偺応崌偼丄偳偆偩傠偆偐丅
丂巐榋敾擇抜慻傒449儁乕僕偺亀儉乕傾恖偺嵟屻偺偨傔懅亁傪撉傒弌偟偰丄嵟弶偦偺閌愩偵晅偄偰峴偔偺偑恏偐偭偨丅棊偪拝偄偰彫愢偺悽奅偵杤摢弌棃傞條偵側傞偺偼丄慟偔100儁乕僕掱撉傒恑傫偩曈傝偐傜偩偭偨丅搊応恖暔払偼扤傕斵傕丄擛壗偵傕僼傿僋僔儑僫僽儖側報徾偩丅儔僔儏僨傿乕偑昤偔偐傜偐丄埥偄偼搊応恖暔偑僀儞僪恖乮堦墳乯偲尵偆偙偲偐傜偩傠偆偐丅撉傒恑傔傞偵廬偄丄彊乆偵丄恖暔偲偟偰偺懚嵼姶傪姶偠偝偣傞丅偁傝摼側偄偙偲偑暘偐偭偰偄偰傕丄擛壗偵傕僀儞僪側傜偁傝摼傞僉儍儔僋僞乕側婥偑偟偰棃傞偺偩丅偙偺曈傝丄儔僔儏僨傿乕偺嶌昳偑乽儅僕僢僋儕傾儕僘儉乿偺彫愢偲尵傢傟傞丄強埲側偺偐傕偟傟側偄丅
丂戝懱丄僗儁僀儞傪娮傟偨儉乕傾恖偺枛遽偲僄僋僓僀儖偲崄椏杅堈偺枛丄撿僀儞僪惣奀娸偵掕拝偟偨儐僟儎恖偲偺寢崌偲尵偆愝掕偑丄堄昞傪撍偔丅惵偄層灒傗僋儘乕僽丄僉儞儅偺崄傝堷偒婲偙偡丄嫮楏側僄僋僝僠僘儉偼丄儔僔儏僨傿乕偺慱偄偺條偩丅傑偨丄壥偨偟偰偦傟偑僀儞僪偭傐偄偐偲偄偊偽儅僕僇儖亅杺弍揑亅偲尵偊側偄偙偲傕柍偄丅傕偭偲傕丄偄偝偝偐僀儞僪傪抦傞幰偲偟偰傒傞偲丄僼傽儞僞僗僥傿僢僋偱偼偁傞偗傟偳丅偙偆側傞偲丄償傿僇乕僗丒僗儚儖乕僾偺彫愢亅堦庬偺償傿儖僪僁儞僌僗丒儘儅儞偲尵偆偺偐乽彮擭彫愢乿偺懁柺偑偁傞亅偺曽偑丄慺捈偱撍僢婲傗偡偄偩偗偱偼側偔丄僀儞僪偺尰幚傪傛傝斀塮偟偰偄傞偲傕巚偊傞偺偩偭偨丅
丂偟偐偟丄儔僔儏僨傿乕偵偲偭偰僀儞僪偭偰壗側偺偩傠偆丅偦傟偵偼丄儕傾儖側僀儞僪摨條偺枺椡偑柍偄偱偼側偄偺偩丅
丂儔僔儏僨傿乕偺挿曇彫愢偼丄婏偭夦偐偮朞偔側偒閌愩偺彂偩丅擔杮岅偱撉傫偱偄偰傕丄孅愜偟偨儗僩儕僢僋傗僐僲僥乕僔儑儞偑嬱巊偝傟丄嵶晹傑偱栚偑峴偒撏偐側偄丅偦傟傪巚偆偲丄東栿幰偺嬯楯偑幟偽傟丄擔杮岅偱撉傔傞偙偲偵姶幱偟偨偄偺偩丅
丂堦偮婥偵側偭偨偺偼丄僐乕僠儞偺晽暔Chinese Fishing nets偲尵偆偺偑偁傞丅偙偺乽僠儍僀僯乕僘丒僼傿僢僔儞僌丒僱僢僩乿傪傢偞傢偞乽拞崙晽偺曅帩偪椑幃嫏栐乿偲嬯擏偺栿偑側偝傟偰偄傞偑乽僠儍僀僯乕僘丒僼傿僢僔儞僌丒僱僢僩乿偱丄偦偺傑傑捠偠傞偩傠偆丅
丂慜偵亀G.僗僞僀僫乕帺揱亁乮岺摗惌巌栿丂1998擭丂傒偡偢彂朳乯偱傕丄僇儞儃僕傾偺乪Killing field乫亅僋儊乕儖丒儕儏乕僕儏偵傛偭偰嶦奞偝傟偨恖乆偑孈傝弌偝傟偨傝廂梕偝傟偰偄偨応強偺偙偲偩丅偦傟偑乽傾僂僔儏價傿僢僣乿乽僸儘僔儅乿偲嫟偵乽僉儕儞僌僼傿乕儖僪乿偲偟偰丄僕僃僲僒僀僪偺尰応偑曐懚偝傟偰偄傞偺偩丅
丂嬤擭丄塸岅偑晛媦偟偰塸岅傪偦偺傑傑晛捠柤帉偲偟偰捠梡偝偣丄傢偞傢偞栿偟偰偟傑傢側偔偰傕椙偄丄屌桳亅摿掕亅柤帉壔偟偨塸岅偑偁傞偺偩丅
丂乽僠儍僀僯乕僘丒僼傿僢僔儞僌丒僱僢僩乿偼丄奀娸増偄偵抾偺榞偵僱僢僩傪挘偭偨嫏栐偩丅抾娖偱捿偝傟偰偄偰丄偦偺傑傑悈拞傊偍傠偟丄傗傗偁偭偰堷偒忋偘傞偲丄彫嫑傗彫崀傝偺儚僞儕僈僯偑彫愇傗奓妅偲堦弿偵忋偑傞丄僐乕僠儞偺晽暔揑側尨巒嫏朄偺偙偲偩丅
丂僄儖僫僋儔儉偵懾嵼偟偰偄偨帪丄廻偺嬤偔偺拞壺儗僗僩儔儞偱奍嬍僗乕僾傪怘偟偨丅偦偺奍嬍僗乕僾偺奍偼丄僠儍僀僯乕僘丒僼傿僢僔儞僌丒僱僢僩偱忋偑傞丄堥梀傃偺偍憡庤媺僒僀僘偺奍偐傜恎傪僗僾乕儞偺暱偱憕偒偩偟偰偄傞偺偐偲巚偆偲亅堦恖慜偺僗乕僾偵堦懱丄彫奍壗旵暘偑巊傢傟偰偄傞偺偐丠丂亅壗偲傕嬉戲側僗乕僾偲姶偠偨傕偺偩丅
丂怘帠拞婥偑晅偔偲丄挷棟応偐傜彫暱側拞崙恖偲偍傏偟偒敀敮摢偺傾僕傾恖偑丄鎎偟偘偵傾僕傾恖偺傢偨偟傪尒偰偄偨丅摨偠條側晄巚媍側娽嵎偟偵僇儖僇僢僞偱夛偭偨偙偲偼乽僇儖僇僢僞徚懅乿偱彂偄偰偍偄偨偑丄拞崙恖偲側傟偽丄僇儖僇僢僞偼偠傔撿僀儞僪丄儅儔僶乕儖丄僐儘儅儞僨乕儖椉増娸晹偺搒巗偱弌夛偆婡夛偑側偄偱偼側偄丅壗屘偐丄偐偮偰偺峲奀帪戙偺枛遽偺條側婥偑偟偰棃傞丅僀儞僪偲拞崙偲偺庢傝崌傢偣偑僉僋僝僥傿僢僋偩偐傜偐傕偟傟側偄丅偲傕偐偔丄撿僀儞僪増娸晹偺奺強偼丄峲奀帪戙偺愄偐傜條乆側崙偺恖乆偺峴偒棃偑偁偭偨偲尵偆偙偲偩丅
丂丂

丂丂

丂儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偺彫愢偲尵偆偙偲偱丄僈儖僔傾丒儅儖働僗偵尵媦偟偨偑丄儔僔儏僨傿乕傪撉傒巒傔偰娫傕側偔乮2014擭乯4寧丄僈儖僔傾丒儅儖働僗偑朣偔側偭偨丅朣偔側偭偨儅儖働僗偺怴暦婰帠偼丄妱偲挿偄傕偺偩偭偨丅挿偄偲偼尵偊怴暦婰帠偩丅寙嶌偑啻傔偔儔僥儞傾儊儕僇彫愢傗儅僕僢僋丒儕傾儕僘儉偵娭偟偰徯夘偼側偝傟偰偼偄側偄丅嬤擭偼婛偵廃抦偺帠幚偲尵偆偙偲偱丄榖戣偵忋傜側偄偺偩傠偆偐丅撉彂丄杮偺悽奅偱傕丄堦斒偺擔杮恖偼丄奜崙暥妛傪撉傑側偔側偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅擔杮偺摨悽戙恖偵傛傞尰戙彫愢偼丄偦傟側傝偵撉傑傟偰偄傞偙偲偼丄暘偐偭偰偄傞偄傞偺偩偑丅
丂21悽婭偼丄塸岅偺傒側傜偢懡尵岅偺悽奅偱偁傞丅儔僔儏僨傿乕偼僀僗儔儉宯僀儞僪恖偱丄尰嵼塸崙恖偲偟偰塸岅傪曣崙岅偵彫愢傪彂偄偰偄傞嶌壠偩丅僇僘僆丒僀僔僌儘偺條偵擔杮恖偲偟偰塸崙偵搉傝丄塸岅偱彫愢傪彂偔嶌壠傕摿暿偱偼側偔側偭偨丅塸岅偵姮擻側擔杮恖側傜丄暥屔杮傛傝懡暘埨偔儁僀僷乕僶僢僋偑丄嵼屔偑偁傟偽梻擔擖庤弌棃偒丄姧峴偲摨帪偵撉傓偙偲傕弌棃傞丅東栿傪懸偮傑偱傕側偄偐傕偟傟側偄丅
丂80擭戙枛丄僂儞儀儖僩丒僄僐亀錕錘偺柤慜亁偑丄悽奅揑偵昡敾偵側偭偨偙偲偑偁傞丅偁傞挊柤側昡榑壠偑丄憗乆偵塸岅斉偱撉傫偩偙偲傪昞柧偟偰偄偨亅姶憐偼側偐偭偨偑亅丅傢偨偟傕丄擔杮嫶偺梞彂揦偱丄埫偄僑僠僢僋晽奊夋傪僨僓僀儞偟偨僴乕僪丒僇僶乕戝敾偺塸栿杮傪尒偰偄偨丅堦懱偳偺傛偆側恖亅宱嵪揑側梋桾偲塸岅偱彫愢傪撉傓偙偲偵巟忈偑側偄亅偑攦偆傕偺偩傠偆偐偲巚偭偨丅梫偡傞偵傢偨偟偲偟偰偼丄僀僞儕傾恖偺挊幰亅僄僐偼婰崋妛幰偱傕偁傞亅偑僀僞儕傾岅偱彂偄偨彫愢側偺偩偐傜丄僀僞儕傾岅偱撉傓偐亅壜擻側傜亅偐丄東栿偑弌偰偐傜偱傕抶偔偼側偄偺偱偼側偄偐丅僀僞儕傾岅偐傜偺塸岅栿傛傝丄僀僞儕傾岅偐傜捈偵擔杮岅偵栿偝傟偰撉傓曽偑丄椙偄偺偱偼側偄偐偲巚偭偨偺偩丅
丂偦偺屻丄傢偨偟偼僔儑乕儞丒僐僱儕乕偑亀錕錘偺柤慜亁偺庡恖岞傪墘偠傞丄僼儔儞僗丒傾儊儕僇偺崌嶌塮夋傪丄尨嶌彫愢偵愭傫偠偰丄娤偰偟傑偭偨丅嬤擭丄尨嶌偺彫愢偑東栿偝傟傞偙傠偵偼丄塮夋壔偺岞奐偑摨帪側傫偰偙偲傕愭偢傜偟偄偙偲偱偼柍偔側偭偨丅幏昅拞偵東栿弌斉傕宊栺偝傟丄東栿偺弌斉偲塮夋偺岞奐傑偱寛傑偭偰偄傞偙偲偁傞條偩丅僈儖僔傾丒儅儖働僗亀僐儗儔偺帪戙偺垽亁偼丄東栿偲塮夋偺岞奐偼傎傏摨帪偩偭偨丅
丂彫愢偐塮夋偐丄奜崙岅偱撉傓偐丄擔杮岅乮東栿乯偱撉傓偐丄偳偪傜偑愭偐偼丄崱偱偼嵎傎偳廳梫側偙偲偱偼柍偔側偭偨婥偑偡傞丅傑偟偰丄東栿偑尨岅斉偵懳偟偰丄傑偑偄暔偺條側懚嵼偲尵偆偙偲偱傕丄柍偔側偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂
丂傢偨偟偼彂昡壠乮傾儅僠儏傾偲偟偰傕乯傪帺擣偡傞偮傕傝偼丄傕偆偲偆側偄丅傑偟偰丄杮傪撉傓偙偲傪巇帠乮偺條偵乯偵偡傞側傫偰丄峫偊傜傟側偄丅弌斉偝傟傞偲摨帪偵撉傫偱丄偦偺撪梕偵廇偄偰僐儊儞僩偡傞側傫偰丄弌棃側偄榖偩丅堦曽丄撉傫偱柺敀偐偭偨杮偵娭偟偰丄偙偆偟偰捠怣偡傞偙偲偼丄桖偟偄偲尵偆偺偐丄壗偐惗偒峛斻偡傜姶偠側偄偱偼側偄丅
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2014擭丄壞丂儅儞僑乕僴僱僟丂
僩僢僾儁乕僕偵栠傞
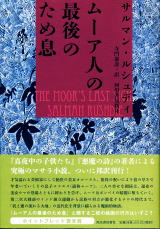
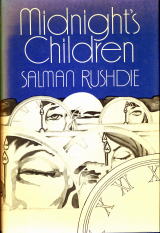 丂丂
丂丂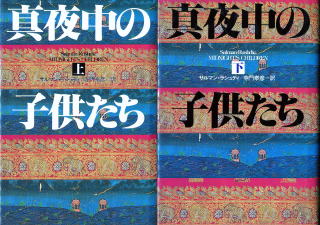
 丂丂
丂丂

 丂丂
丂丂

 丂丂
丂丂