[インド食紀行]
「南インド式カリー」に就いて
ここで「カリー」と表記したのは、他でもないわたし達の良く知る食べ物、カレーのことだ。
日本でカレーは、子供は言うまでもなく、若者から年配者、男女を問わず広く愛されている。インド起源の食物であることも、一応良く知られている。日本全国津々浦々の家庭に行き渡り、日常的に食される味噌汁と同様、それぞれ家庭の数だけカレーの味もあり人気は高い。カレーは、既に日本の民衆食-ソウル・フード-と言っても良いだろう。その様なカレーを、わたしがわざわざ「南インド式カリー」と表記したのは、多くの家庭で食されるカレーとは、趣の異なるカレーだからなのだ。 「南インド式カリー」と、わざわざことわって書いたからには、一般家庭で食される様なジャガイモ、にんじん、肉が、カレー・ルーと共にシチュー風に煮込まれた、モッテリとしたカレーではない、と言いたいのだ。今回、それを皆さんに紹介しようと思う。
つい、大見得を切ってしまったが、近年、わたしが居住する東京郊外、私鉄沿線のありふれた町にまで、インド・レストランが店開きしている。それも、調理・経営など南アジア-ネパール人やバングラデーシュ人-出身者が行っている店なのだ。そうしたインド・レストランによって、多くの日本人は、居ながらにして既に本格的なインド料理を、食しているかもしれない。インド経験者が詳しく語らなくとも、取り立ててインドに関心がない方でも、一言「インドカレー」と言われ、それがどんなカレーか、またその味わい、美味しさや匂に至るまでイメージすることは、今日たやすいことであろう。何を「今更、カレーなど」と、思うかもしれない。しかし、その違いは食べてみなければ、お分かり頂けないだろう。
 80年代末、シュリ-ナガルの食堂で
80年代末、シュリ-ナガルの食堂で
インドにいながら、味わえなかったカレー
インドとカレーが話題になると、思い出すことがある。
1978年のことだ。インド旅行を思い立ったは良いが、現地の事情は全く分からなかった。旅の実際を知りたく「つて」を頼り、添乗員の経験もあると言う人に会いに赴いた。序でに言えば、70年代後半は未だ「バック・パッカー」と言うことばも、殆ど使われていなかった。夏場に北海道へリュックを背負い、民宿を泊まり歩く若者を「かに族」と言っていた、そんな時代だったのだ。有楽町のビル内にある勤務先で件の人は、口を開くが早く「若者が一人旅でインドに赴くなど、無謀だし第一危険だ」と、言い切った。当然そう言う考えもあるかと、驚きはしなかった。その後の一言「現地での食物は、日本人の口には合わない代物だ」と付け加えたのには、少なからず面食らった。
その時、インドカレーの話こそ出なかったが、その人は中華料理の例にして、現地(香港、台湾)で食べる中華料理は「脂っこく、食べられたものではない! 」とまで、言い切ったのだ。旅の経験皆無のわたしは、その語気の尋常なさにこそ驚かされた。余程、旅先で嫌な目に遭っているのだろうと。食べ物の恨みは、怖い。現地の情報を得ようと話を聞いて「行くな」と言われても「はい、そうします」と言う分けには行かない。最もそれから幾らも経たず、カルカッタに降り立った際には、腰を抜かさんばかりに驚き、かつ呆然としたのだったが。当然、人は現地に驚愕したからと言って、飯を食わない分けには行かない。食欲は、一刻も早くオリジナルなカレーを食べたいと欲していた。カルカッタでは、インド人と外国人旅行者で混雑しているストリートに足がすくんだ。結局、不味い中華料理店へ行ってしまったりして、数日が経過した。その間、カレーは愚か、インド名物のチャイも味わっていなかった。ともかく、何所へ行けばそれらしい食堂があるのかも、皆目分からない。ホテルの人か誰か現地の人に、食堂を訊ねれば良さそうなものだ。
カレーの前にチャイの洗礼を受けたことを申し述べよう。紅茶-チャイ=ミルク・ティー-もインド名物だ。紅茶の世界的な産地として知られているダージリンやアッサムなど、インドにあると言うことは、わたし達にも常識だった。チャイと言えば、安宿のある路地の出口角、サダル・ストリートに茶店がある。道ばたに縁台風の腰掛けを出し、長髪に髭の白人旅行者が、現地人に混じってチャイを喫している。最初は気安く腰掛けられなかった。産まれてこの方、インド人や白人旅行者に混じって、道ばたでチャイを飲む様な機会はなかったからだ。初めてチャイを味わったのは、タージ・コンチネンタルと言う、インド人旅行者向きの大衆レストランだった。以来、ここがカルカッタで気に入りの店になった。タージはいやしくもコンチネンタル-文字通り大陸風と言うのか、大英帝国風-なレストランだ。チャイもカップ&ソーサーで饗される-茶店など、粗製ガラスのコップで飲む-。タージのチャイは、サダル・ストリート界隈で最も熱く、濃厚なミルクの味わいが利いていた。80年代末、ここで決まって朝一番のチャイと朝食を摂った。ノン・ベジタリアンの店なので、朝方は店先でオムレツを焼く。チキン・カレーもあって、味は悪く無い。もつとも最初から、味の善し悪しが分かったわけではないのだが。
そんな驚愕のインドに、繰り返し訪れる様になった、80年代末。五月のカルカッタは、日ごと熱気が上昇する。熱気は夜になっても冷めやらず、人々は屋外にベッドを出して眠る。酷暑の日々でも日没後は、幾らかほっとした気分になれるものだ。寝付けないとき、就寝間際にチャイを飲みに行くこともあった。すっかり、お客を仕切る中年ウエイター氏や年長の給仕少年と仲良くなり、彼らと店仕舞い前のリラックスした時間を共にすることが街の愉しみだった。店の者が店じまいの片付けをする傍らで、勝っ手知った風にチャイを飲むのは、最もカルカッタらしい経験に思った。
昼間無理を言って、一度だけタージの厨房を覗いたことがあった。内部は壁、天井と言わず全て黒々と煤け、髭ずらの年老いたおっちゃん-一応、シェフだと思う-が、一人で厨房を取り仕切っていた。裏口の脇、石炭かコークスの燃える七輪に、学校給食で使いそうな大きな薬缶が乗っかり、何時もチャイを切らさぬ様、沸かしていた。
*タージ・コンチネンタルは、1997年に訪れた際閉店していた。10年後の2007年、カルカッタに立ち寄ると、経営者、従業員も替わり再開していた。店の名も場所も同じだが、チャイもカレーの味も、以前とは全く違っていた。
インド人は果たして、朝昼晩三食なのか?
思えばインドには、定番の朝食-日本の様な朝ご飯、納豆や生卵、味噌汁と言う様な-が無い様なのだ。
都市のインド人は多分、チャイの一杯も飲んで出勤し、10時のティー・タイムに何かつまむのかもしれない。ボンベイには、近年映画で有名な弁当の配達サービスを行う人々がいると言うことは、昼食に弁当を食す人が、少なからずいると言うことだ。それでも、三食きちんと摂ることは、無いのではないか。
カルカッタのオフィス街は、舗道に茶店やスナックを揚げる仮設店舗が賑わっていて、出勤前にサモサの二つも、囓りつく人もいるだろう。昼飯も困らない。ティー・タイムには、そこからティーの出前が行き交う。わたしの知る限り、インド人男性は、夕食を家で食べる。最も、家族揃って一緒に食事はしない。主婦は台所で女性だけで食す。
旅行者にとっても食事は大問題で、中でも朝食は重要事だ。カルカッタなら、早朝から店を開いているレストランがある。また、土地勘のあるところなら何とかなるかもしれない。観光と縁の無い地方都市で、食事に困ることが多い。
現地食のカレーを食べたいと思い、最も迷うのが首都デリーのメイン・バザール、パハルガンジだと言うのは、皮肉だ。デリーで正式のインド料理となると、モーティマハルとかクオリティーとか、本格レストランは確かにある。それらはオールド・デリーの方だったり、或いはコンノート・プレースまで、わざわざオート力車で出張らなくてはならない。実はメイン・バザールには、外国人旅行者相手のレストランや食堂は多数ある。インド式も無い分けでは無いが、落ち着いて食事をするところではないのだ。そんなインド式の、味も値段も納得し難い。パハルガンジで落ち着いて食事が出来るのは、結局無国籍化したレストランになってしまうのだ。パハル・ガンジのホテルには、レストランが併設されている。ビリヤードの台などあって、ネパール人のウエイターが、忙しげに行き来している。インドらしからぬ雰囲気なのだ。朝はそこでコーヒーにトースト、オムレツなどと言った日本の朝食と代わり映えのしない、定番になってしまう。思えば、ヴァラナシだって毎朝カフェ・モナリサ-前にも申し上げたが、日本の70年代喫茶店風でわたしのお気に入り店だ-へ行って、お定まりの朝食だった。
昼食はその日のスケジュールによって摂ったり摂れなかったりする。チャイやコーヒーを飲みながら、つまめるものだったり。夕食は、出来るだけインド料理にしたいのだが、これまた相性の良い食堂が、宿の近くにあるかどうかで決まる。今では、北インドの地方都市にも、南インドのコーヒー組合が経営するインディアン・コーヒー・ハウスがある。わたしはここを良く利用した。それでも、南インド式の朝食-プーリーやイッドリーなど-を摂るのは、やはり旅の半ば、南インドに足を踏みしめてからになる。
インドに於けるカレーの食べ方
インド初心者のわたしも、旅行者の間で「現地のカレーは、日本で食べている様なカレーと違う」と言われているのを知らない分けではなかった。汁っぽいだけで、肉は愚かジャガイモやにんじんが入っていない「過激に辛いだけのカレー汁」と。
最初のインド旅行で、一月程して漸く、北インドの有名なガンジス河畔の都ヴァラナシに辿り着いた。町に着いて早々、現地の庶民が利用してる様な、屋外に椅子とテーブルを並べた食堂に遭遇した。
早速、食事をしようと何が食べられるのか、竈の上に三つ鍋がのせられていた。並べられたそれぞれの鍋の中を見せてもらった。一つは、赤黄色いカレー汁、第二の鍋は黄色いカレー汁、三つ目の鍋は、緑黄色いカレー汁が確認出来た。
今なら、器それぞれのカレーがおおよそ分かる。赤黄色のカレーは、多分トマトを煮込んで赤いのだと思う。緑黄色のカレーは、ほうれん草か青菜により緑色になっているに違いない。黄色の汁は、最も普通のカレーと言うことになる。
そのカレー三種とも食すことにして、椅子に腰掛けた。確か、チャパティも注文したはずだ。鍋から器に取り分け出てきたカレー汁には、日本のカレーの様な具は入っていない汁だけだ。汁を口にしても、強烈にスパイシーで、汁の色以外三種の違いすら分からなかった。
今でこそ当たり前に思っているが、カレー汁をそのまま直に口にしても、スパイスが濃厚すぎ、旨味が分からないからだったのだ。これらカレー汁は、チャパティを浸して食べ、その後ご飯をもらい、ご飯にぶちまける様にかけ、素手で良くまぶし食べてこそ、マサラの味加減が丁度良くなるものなのだ。どの器のカレーも、半分程も食べられなかった。
普段インド人は、先ずダルと言う豆をスープ状に煮た汁を、冷めたご飯にザットばかりかけ、素手でまぶし一口サイズにして口に放り込む。その間、おかずがあればそれに越したことはない。日常的には、時々塩とか漬け物-「アッチャール」レモンや青いマンゴーをチリと一緒に漬込んだ、日本の梅干し的機能の食品-を囓り、ご飯を沢山食べる。
外食する場合、カレー汁-場合によっては豆(ダル)のスープも-にチャパティーを2枚位を、汁に浸して食した後、ご飯をもらいカレー汁をまぶし、塩、或いはアッチャールを囓りながらご飯を食べるのだ。インドでは、肉とジャガイモ、ニンジンを一緒に煮込まない。野菜が欲しい場合「サブジー」と言う、野菜の煮付けがある。このサブジーは、日本のカレーの具になるジャガイモやニンジンなど野菜を、単体またはタマネギ、青菜などと共に、マサラ・味で煮付けたもで、カレー汁とは別個におかずとして食べる。材料はジャガイモがポピュラーだが、野菜の旬に合わせ茄子やインゲン、オクラ、カリフラワーだったりする。
カリフラワーと言えば、思い出すことがある。最初の旅で、タージ・マハルで有名なアグラに滞在したおり、現地の食堂でサブジーを注文すると、カリフラワーが出てきた。その時は、それを食した。ところが滞在時、アグラの町のあらゆる食堂で、サブジーと言えば、カリフラワーばかりが出て来るのだった。遂に食傷してしまった。わたしは今に至るまで、カリフラワーが嫌いなのだが、それはアグラでのサブジー体験がトラウマになっているからなのだ。ともかく、インド料理で最もスタンダードなおかずと言えば、サブジーと言うことになる。サブジーをチャパティで挟んだり、カレー汁のまぶされたご飯のおかずにつまんだりしながら食す。こうしたところが、北インドの一般的なベジタリアン料理だ。
続いて、一般的なノン・ベジタリアン・カレーを説明しておこう。最も普及している、チキン・カレーを注文すると、拳の3分の1程の鶏肉のかたまりが一個、汁に浸かる様に出て来る。エッグ・カレーなら汁の真ん中にゆで卵が一個、時にゆで卵一個を立てに二分した状態で汁に浸かって、目の前に運ばれるのだ。先ずカレー汁をぱさぱさのご飯に、全部かけ、ご飯を混ぜて鶏肉ないしゆで卵は、おかずとしてご飯の合間につまむも良し、砕いてカレー汁と共にご飯に混ぜ込んで食べる場合もある。家庭でも、おかずにサブジーがあれば、なかなかのごちそうと言うもので、更にチキンやエッグカレーになると晴れの食事と言うことになる。インド人は夕食を、家の外でやたらに食べることはない。
チキン・カレーが出たので、日本でも有名なタンドリ・チキンに就いて述べておこう。タンドリ・チキンのタンドールとは、竈のことで、今では日本の都心にあるインド・レストランでは、ウインドゥ越しに、髭のインド人がナンを焼いている、あの竈で焼く鶏肉のことだ。こうした鶏など肉の一品料理は、良くヨーグルトにスパイスを混ぜ込んだ、調味ソースに鶏肉をつけ込み、それを竈で焼いて饗される。インドでは近年までブロイラーは無かった。普通鶏は、放し飼いされていたものを食した。飼料らしい餌も与えられず放し飼いされ野性的な鶏だ。インドで鶏肉と言えば、大抵われわれが普段食している鶏肉より、筋っぽく歯ごたえがあった。後に、南インド式のカレーを紹介する際にも申し上げるが、ヨーグルトの調味ソースは、味-ヨーグルトの酸味-もさることながら、乳酸菌の働きで肉質を柔らかくすることも、考慮されているに違いない。
今、日本各地のインド・レストランでは、食事時セット・メニューを注文することが多い。インドでも食事時には、ターリーと言うセット・メニューがある。ターリーには、ナンとかライスにおかずが2品程付き、ヨーグルトやチャイもセットされている。
更に、豪華なターリーもあり、おかずの種類が増え、パーパル-或いはパッパッドと言う、豆の粉を練り乾燥したものを揚げたせんべい。このまま食べても良いが、砕いてご飯にかけると、サクッとした食感が良い-に、ラッシー-ヨーグルト飲料-やチャイ、甘いお菓子のデザートまで付くものもある。
こうしたセット・メニューは、料金に応じておかずやスイートなど品数が増える。当然、インドでも都会のしゃれたレストランに行かないと無い。ターリーに複数コースがあるレストランは、インドでも贅沢な食事になるのだ。
過剰な恐怖
わたしは、ある時期まで現地食を評して、後年の「3K」をもじり「辛い、脂っこい、汚い」と言う、 <食の三K>をもって言い表したものだ。現地の、文字通りオリジナルなカレーを<食の三K>なんて、随分、傲慢な上から目線な評価とも思えるかもしれない。それは何より、わたし達が未だインドの「食べ方」を知らなかった、無知から来ているのだった。かつてインド旅行者が食べることに積極的になれなかったのには、食べ方を知らなかっただけではなく、病気への恐怖があったことも大きい。もう一つ過去の経験を述べさせて頂く。
80年代インド旅行においては、コレラやマラリア、赤痢の罹患を危険視するのが常識だった。当時、東京周辺在住の旅行者は、東京都品川-船員を主に海外渡航を職業柄する人向けに東京都が行っている-に、コレラの予防接種を受けに行ったものだった。熱帯病だけではなかった、インドではA型急性肝炎の危険性が強く言われていた。わたしも、その予防に有効とされるγ-ガンマ-グロブリンを有楽町交通会館内の診療所に赴き、接種-尻に注射-したのだった。
今でも憶えているが、接種の後インドで注意しなければいけない病気に就いて、医師(女性だった)に質問すると「帰国したら、寄生虫の有無について検査して見る様に」と言われたのだった。医師は、多分東南アジアとインドをごっちゃにしていたのだろう。ご存じの様に、インドでは普段一般に魚介類は食さない。食べても、日本人の様に生で-刺身で-食すことはない。また、大根やキュウリを囓ることはあるが、肥料に人糞を使うことはタブーだ。後は、生水に気を付ければ、寄生虫に感染するなど、常識的には考えられない。
欧米や日本が先進国なら、インドは当時「第三世界」と称された、後進国だった。インドの実際に就いて、普通の日本人には知識は愚か、興味や関心すら無かったのだ。近代になってこの方、インドのイメージに貧困は付きものだった。その関心のなさに合わせる様に、未だインドを旅する日本人も僅かで、当然現地の情報も乏しかったのだ。そこからインドの衛生環境への恐怖が、旅行者に強く印象づけらたのだろう。まるで空気からすら感染するかのごとき、病気に対する過度な恐れも広まったのもその為だ。
その中でも最も恐れられていた病が、急性肝炎だった。感染源は水や食物からと言われ、飲料水や現地食堂での飲食に関して、過度に警戒されたのだった。食堂で出されるコップの水は、現在でも余程のことが無い限り、旅行者は口をつけない。亜熱帯のインドにおいて、容易に水が飲めないとすると、命の保証が無いと言うことにもなりかねない。わたしも1998年以前の旅行で、その頃未だペットボトルの飲料水が出回っていないこともあり、生水-衛生状態に確信が持てない水を-口にしなければならない時、恐る恐る最小限を口にするだけにしていた。
80年代後半、最も暑い時期にデリーに滞在せざるを得ないことがあった。この季節を「酷暑期」と言う。シャワーの水も蛇口を捻ると、お湯になって出る。しばらく出しっぱなしにしていないと、火傷までには至らないにせよ、かなりの熱さになるのだった。さすがこの季節、飲み水を制限して、瓶詰め清涼飲料水だけを飲んでいることは出来なかった。デリーのメイン・バザール、パハルガンジでは、氷入りの冷たいラッシーが飲め、渇きをいやした。それでも、使用されている氷のもとの水の清潔度や製氷の仕方、衛生状態に関しては、考えないことにしていた。
現在、インドでも普及した、ペット・ボトル入りミネラル・ウォーターも、果たして衛生基準がどの様にクリアされているものか、わたし達には、一切分からない。近年のことだが、ある人が「インドでは、腹をこわす」と言うので、ミネラル・ウォーターがあると応えると、中身の水が「信用できない」と言い、「ミネラル・ウォーターを飲んですら、インドでは腹をこわす」と言っていた。鋭い指摘ではないかと思った。ついでに、わたしの兄は、所用で以前一度、ゴアに滞在した。ところが、到着早々、腹痛-下痢-を起こし、滞在中ホテルのベッドに横たわって過ごしたと言うのだ。国を出て、呼吸する空気が変わるだけで、既に不調に見舞われる人もいると言うことである。
2007年、帰国を控えたカルカッタ滞在時、再開したタージ・コンチネンタルで、一人食事をしていると-わたし以外客はいなかった-、老年の白人婦人が金属製カップを持って店先に現れた。「まさか、白人の物乞い? 」とは思わなかったが、店のインド人に頻りとカップをかざし、話かけ様としている。
その婦人が何を言っているのか聞いてみると、何のこはない「ティーが飲みたい」と言うのだ。カップを手にして来た理由と言えば「店の食器では、ばい菌に汚染されているかもしれないから」と言う分けなのだ。「まあ、中に入って腰掛けたら」と言うと、客がいることで安心したのか、老婦人はにこにこ笑って腰掛けた。
カルカッタは近年、マザー・テレサの町として知られるに至った。多くの外国人が、マザー・テレサの施設でヴォランティアを志し、訪れる様になった。カルカッタを訪れる外国人は、特別インドへの感心とは別に、ヴォランティアのみを目的にカルカッタまでやって来る人も居る。その白人婦人もヴォランティアが、目的で来たのだろう。インド式レストランを利用するのは、初めての様だった。確かに、一時期、そして現在も時々、白人の旅行者が現地レストランの食器を不潔がるのを目撃しないこともない。
そう言えば、わたしもかつて、自分のスプーンを持って旅行した。それは、何もスプーンから感染するのを恐れてでは、なかった。インド人の様素手で食べると、飯粒が鼻に入って、はなはだ食べ辛いからであった。それに、ウエイター氏に一々スプーン-現地語で「チャマッジ」と言う-をいちいち頼むのは、面倒だ。店の匙は、大抵アルミのちゃちなスプーンを持って来る。確かにその場合、不潔感がないではない。ともかく、気兼ねなく使うことが出来ないものだ。
1983年 ヒマチャール・プラデーシ州、ダラムサラ

昔は、自炊までしたものだ
インドではカレーは不味いし、病気も怖い。要するにインドに行って、人はしつこいし、街も宿も食べ物も不潔で嫌だと言う「インド恐怖症」が、現地で一層嵩じる人もいたのだ。それはともかく、現地に慣れた頃、わたしも電氣コイル式湯沸かしを入手し、茶を自ら煎れ、インスタント料理も試みた。そして、二回目のインド旅行においては、到着早々現地で石油式コンロを調達し、旅行中は自炊に励んだ。当時は半年余り、インド各地を徘徊していたのだから、茶の一杯も飲みたい時、自分で煎れたかった。
調理器具があると、朝起きると同時に、自由にティーが煎れられるだけではない。何時でも、カレー味でないものを調理することが可能だ。朝食なら、ゆで卵、トマトとオニオンのオムレツ、レモン・ティーに薄い-厚切りのパンはない-バター・トースト。夕食なら、ジャガイモを茹で、塩とニンブ-ライムの様なレモン-をかけて食べられる。何か青菜を入れた、マギー印のインスタント・ヌードルなど、簡単に作ることが出来る。
自炊をするとなると、食材を調達する必要がある-それと、時々燃料の石油も-。どうしても食材を求め、現地のマーケット、バザールに地元の人に交ざって-何時も混雑しているのだ-徘徊することになる。そうしたバザールは、観光客が集まるメイン・ストリートにはない現地の人々の生活感に、直に触れることが出来るのだ。町中では、博物館や観光スポットも悪く無い。中でもバザールこそ、庶民の日常生活を知るには、好適な場所だ。
1983年 ポンディシェリー近郊のビーチ 地引き網を引く地元民

フランスの旧植民地だったポンディシェリー近郊のビーチで、小屋を借りたことがある。
ポンディシェリーの中心は、統治時代の町並みが整然と遺っている。旧市街の中心は、現在も瀟洒な植民地風住宅を高い塀が囲んで、路上にインドらしい賑わいはない。そんな町にも、バザールに赴けば人々の賑わいがあり、魚市場には近海で捕れた魚類が売られていた。借りていた椰子の葉葺き小屋は、市街から2㎞程椰子林を抜けた浜辺にあった。ビーチから市街へ、サイクル式力車に乗り、行き来した。浜辺には、ゴアの様なビーチ・リゾートとは異なり、それらしいレストランは無く、茶店が店開きしている程度だ。こんなところで自炊するのは、インド旅行の醍醐味らしく思われた。
ある時、市場でイカを買って戻り、イカのチリ・ソース煮を作ってみた。二杯のイカは、一度に食べ切れなく、残り一杯は、保存すべく一夜干しにすることにした。何と、イカを狙うカラスの襲撃に遭遇した。小屋に地元の少年が、生きた伊勢エビを売りに来たこともあった。買ったは良かったが、エビを小さい鍋で茹でるのには、苦労した。生きたエビは湯の中で暴れるし、厚い甲羅を通して、なかなか身まで充分茹だらなかったからだ。普段、わたし達は、肉や魚など食材をスーパーで調達する。肉や魚は手ごろな大きさに切り分けられ、パックから出せば後はガス・コンロで、焼くか煮るか炒めるか調理するだけだ。インドで料理を一品作るとなると、食材を買うべく市場へ赴き、持って帰るとそれを切りさばき、コンロの炎一つで調理し、食べるまでに一仕事だ。魚類など買おうものなら、生ものを持って帰るのも骨だが、さばくとなれば大仕事。料理が出来る頃には、すっかりくたびれ果て、空腹感を忘れて食欲が減退してしまうことも経験した。以来、ゴーギャンと言う画家が、インドとタヒティとの違いはあるが、一層偉く思え好きになったしまった。
インドでの食物から自炊へと語り出すと切りがない。それに就いては、何れ語る機会を作ろう。少し先を急ぎ、南インドの食べ物について書いて行きたい。
インドで魚を食す
自炊の話から、浜の香りを思い出した。ここで、概略ながら魚のカレーに就いて書いておきたい。さすがに北インドで魚は食したことはない。魚料理は以前から、ゴア、やマドラス近郊のマハバリプラムなど、ビーチ・リゾートを意識した、外国人旅行者向けレストランで饗せられて来た。それ以外で、魚が食べられるのは、南インドの海岸地帯になる。
南インドで魚が食べれているとは言え、漁民や漁業は、日本のそれの比較にはならない。海岸線に沿って西から東へ移動して、海辺や浜で見られるのは、手漕ぎで精々幌を張る程度の舟ばかり、日本の漁船の様なエンジンの付いた船は、見たことがない。漁民は浜から海に漕ぎ出し、沖で幌を使うにしても、それでは近海の魚しか捕らえることは出来ないだろう。そんなインドで唯一、ケララ州海岸域の人々が、長い海岸線を有する州と言うこともあり、日常的に魚を食べている。
ケララ州である時、地元の人に昼食のミールスに連れていってもらったことがあった。一般住宅の庭の様なところにテント風仮設屋根を設けた定食屋で、決まりのミールスに10㎝程の魚-鯵のよう-フライが付いて来る。香辛料を振り、フライにされた魚で、頭と背骨以外、丸ごと食べられた。
また、ケララとタミル・ナドゥの州境、動物保護区のあるペリアール付近で、地元の農家で、魚を味見させてもらったことがある。農家の主人は、イスラム教徒だった。それもあり、魚を食していたのだと思う。その家では、頭を取った10㎝程の鰯か鯵の様な小魚を、はじめ揚げるか炒めるかし、カレー味の汁で煮たものだった。一尾味見をさせてもらったところ、魚特有の臭みもなく、カレー風味の佃煮と言えないこともなかった。今思うのだが、もしかしたら彼が食べていた魚は、淡水魚かもしれない。味見させてもらった農家がある地域は、海岸部から内陸部に入り、周囲はジャングルに囲まれている。また、保護区内には、雨季の後、湖が出現する。海岸部から運び上げるより、近所で捕れたフナの様な淡水魚ではないかと思えないでもないのだ。
われわれからして、食すに適当な魚となると、海辺の外国人向けレストランで出会うことになる。大抵一尾丸ごと、香辛料と小麦粉を振り、焼かれるかフライにされ饗せられている。インドでは、魚は焼くより、フライにした方が美味く食べられる気がする。
一応、魚のカレーも食したことはあるが、その場合、小口切りされた魚が汁に浸かっているだけで、揚げるとか炒めた様子はなく、生臭みが残りうまいものではなかった。また、干し魚も目撃したが、食品としては、最もランクの低い食べ物とされ、レストランなどで食べる機会はない。
南インドの米食
近年のカレー・ブームで、日本では主食のご飯に対して、ナンやチャパティの人気が高まった。それは近年、日本の食習慣において「お米離れ」を来していることと、関わっているのではないだろうか。
わたしとしては、南インドのカレーは、ご飯との相性が良いと思っているのだ。それは、北インドのお米より、南で食されるお米(ご飯)の方が、僅かではあるが、日本で食されご飯の食感に近く、それに伴いおかずの野菜、煮付けなどのカレー味にも、日本の味を思い起こさせないではない、味わいが感じられるからだ。
後で、南インド式カレーをご紹介したいと思っているが、南インド式カレーの場合、是非ご飯で召し上がって欲しいのだ。
教科書的には、北インドは乾燥地なので、小麦などからチャパティを作るなど、粉の食域とされ、一方、南インドは、年間を通じ米の栽培に適することから、米飯を主とする食域とする見方がある。そうは言っても、北インドの人々の主食は米だ。また、南のインド人も日常的にプーリーやパロータなど、小麦や豆の粉を練り薄く焼いた、パン的なものを好んで食べている。チャパティやナンの原料になる小麦の栽培は、西方パキスタン国境までつづくパンジャーブ州で、主に栽培されているそうだ。
一方、米を栽培している地域は遙かに広く、おおよそ東のベンガル州から西ネパール国境へと広がる、北インド平野部全域。更に、ベンガル州南隣オリッサ州から、内陸のマディア・プラデーシまで広がる。南インドの西東両平野部は、稲作地帯だ。インド全体では、小麦の栽培より稲作の方が、遙かに多いとされている。
ポンディシェリー近郊 ビーチへの道すがら


お米のことが出たので申し上げておきたい。北インドのお米は、いわゆる米粒が細長いインディカ米が主で、普通それを食している。
自分でご飯を炊こうと、現地でお米を買ったことがある。米や豆、油を扱う店の米びつには、何種類か精米したお米が並んでいた。中に見るからに日本のお米の様なのもあった。わたしは、それを欲しいと言うと、店の主人は、それは上等ではないから「止めろ」と言う。店の主人が強く勧める一番上等な米とは、数種ある長いインディカ種米の中でも最も長細く米の両端が尖った米なのだった。主人は、絶対細い米が良いと、頑強に言い張るので根負けし、仕方なく1㎏程、その最も細長いお米を買った。宿で、かなり長く水に漬け、炊く際には日本で炊く時より、これまたかなり大目の水を入れ、炊いてみた。それでも、わたし達の食べる様なご飯には-案の定-炊き上がらなかった。食感もご飯と言うより、ココナッツの細かく砕いた白い果肉-味のない-と言った感じだ。翌日、残りのお米は、店に持って行き買い取ってもらった。
その後、インドでご飯の炊き方を、目の当たりにした。その際、日本式との決定的な違いは、お米は炊くと言うより煮る感覚に近い。米が煮上がると、鍋からご飯をざる状の容器にあけ、湯分をすっかり切って、一気に冷やしていた。もともと水を吸わないインディカ米なので、湯を切らず蒸したとしても、粘りけは全く出ない。ぱらぱらな状態で食すことになる。そこからも、北インドの現地カレーが、日本や南インドのカレー汁より、一般的にスパイス味濃厚で油気が濃い-北インドが乾燥していることもある-理由も分かる。粘り気のないご飯に、まぶして食べるからだと思った。
南は水稲耕作により、ジャポニカ米に近種の米も見られ、南インド西海岸に細長く伸びるケララ州では、大粒の米粒に一部赤みのある米が、ポピュラーに食されていたりする。南インドもお米は、ぱらぱらの状態で食されるが、北インドのお米より、やや丸みを帯びているので、より日本のご飯の食感に近い気がする。そこから、北インドと南インドでは、お米とおかずになるカレーの味に、特徴的な違いがあると言えないでは無いと言うことも分かる。
インドでも地域によりカレーに特色がないでは無い。特に北インドでは、シュリナーガルが標高の高い、モスリムの土地と言うことで、肉を使うカレーや野菜のカレーの場合も濃厚な味わいのカレーが食される。また、シーク教徒が多く、パキスタンと国境を接しているパンジャーブ州では、良く肉のカレーも食され、チャナ(ひよこ)豆の煮付けなどポピュラーで、どれもスパイシーで濃厚な味付けになっている。
また、レストランによっては、トマトやホウレン草など青菜の「野菜カレー」がある。その場合、野菜は、スパイシーなカレー汁に入っていて、時によって煮込まれた状態で、饗される。こうした野菜カレーを、インド人が日常的に食べて居るところは、見たことがない。ひょっとしたら、外国人旅行者向けかもしれない。
ゴアの南ゴカルンのレストランで、白人が注文したトマト・カレーを目撃した。そこには、カレー汁の中に輪切りにされたトマトが見えた。どんな味なのか、試してみたい気持ちはあったが、食欲が言うことをきかなかった、残念。
南インドでは、肉も食すが、北インドより魚を食す機会が多い。その場合、カレー汁で魚を煮たカレーではなく、魚をヨーグルトにスパイスを調合した調味液をまぶし、油で揚げたり焼いたものを、おかずとして食べる。西海岸に位置するケララ州では、割と良く魚が食されている。多分、最初は海浜民が、後にイスラーム教徒が、食す様になったのだろう。海浜民は、ヒンドゥー教徒の場合も、海辺で暮らすカーストがあり、独特のライフ・スタイルもある様だ。
南インドでは、ダルを始めサンバルやバターミルクが、汁気を補う。濃厚な北インド風カレーに対して、南インドは、全体に酸味やさらっとした味わいを重視しているのだ。近年、日本では雑誌などで、南インドのカレーが紹介される機会増えている。映画の都としてムンバイ(ボンベイ)やインドのシリコンバレーと称されカルナタカ州バンガロールが紹介される中、町のホテルやレストランを紹介する、雑誌の記事を見た。そこで、南北のカレーの違いを見ておくことにしよう。北インドでは‘ターリー’南インドでは‘ミールス’と言う、定食形式のセット・メニューがある。それを例に解説してみよう。
北インドのターリーは、ステンレスのお盆に、やはりステンレスの小鉢に野菜のカレー、サブジー、ダル、ヨーグルトやスイート系デザートを小分けして、チャパティー、ご飯、パーパル-パッパドとも言う、豆の粉を練って薄く平にしたせんべいで、軽く焼いたり揚げて、パリッとした食感を愉しむ-が、セットされる。
南インドのミールスは、普通バナナの葉を引き、その上にご飯とプーリーを手前に盛り、葉の上に野菜のサブジー、豆のサブジー、ステンレスの小鉢にダル、バターミルク、サンバル(タマリンドで作った酸味のあるスープ)が付く。ココナッツ果肉とミルクで作ったチャトニィ、マンゴーのアチャール(ピクルス)、にパーパル-細かく砕きご飯に混ぜても食感が良い。パーパルを揚げるのは、中華の「油状」の様な感覚かもしれない-が付く。
もう一つ紹介しておきたいのは、スナック系食品だ。北インドでは、サモサにパコーラが、その代表だ。サモサは餃子の皮風の中にジャガイモとタマネギを混ぜた、肉なしのコロッケの具風のものを入れ、揚げてある。パコーラは、タマネギを小麦粉を水で練り、一口大に油で揚げたスナックだ。
一方、南インドでは、マサラドサと言う、豆(ウーラット)の粉をやや発酵させ、クレープ風に薄く焼き、サモサの具と同じ様なジャガイモとタマネギのカレー風味の具を挟んだ食品が、良く知られている。チャパティーも食べるが、全粒粉を丸く伸ばし油で揚げ、中の空気が丸く膨らんだ状態で食すプーリーが、ポピュラーだ。わたしは朝食に、プーリーに蜂蜜やバナナを挟んで食べる。
また、豆の粉を発酵させた液を型に流し込んで蒸す、一種の蒸しパン、イッドリーがある。殆ど日本の蒸しパンと同じだが、粉のとろみと蒸し具合によって、中華まんの皮の様なモチッとした食感のものに出会うことがある。それ自体プレーンな味わいなので、取り合わせによって、ご飯(主食)の代わりになる。
また、豆の粉を小さなドーナツ状にして揚げ、堅く締まった「がんも」風食感のボンダ-Vadeとローマナイズされるが、発音は<ボンダ>なのだ-も、南インドのポピュラーなスナックだ。これらには、サンバルとココナッツのチャトニィが、付きものになっている。南ではこれらが、朝食はじめ軽食として普通に食されている。
90年代、画廊の店員をしていた際、知人の写真家-彼はインドを始めアジアの国々を歩き、写真と文章による本を刊行していた-の写真展を開催した。彼はインドよりタイを始め、東南アジア地域を好んでいた。その理由を訊くと、東南アジア地域の、食べ物の豊富さと言っていた。インドは食べ物が限られているので、長期滞在は辛いのだと言う。わたしもタイを訪れた際に経験したが、彼の地は肉に魚、甲殻類に中華風ソーセージ、麺類、日本のカッパえびせんもあるのだ。確かに、食の豊富さは日本と比べ、勝るとも劣らないのだった。
しかし現在、インド旅行者にとっては、特に長期滞在型ではない旅行の場合、食種が限定されていることは、旅の困難さの要因ではないかもしれない。日本の都会の様に、あらゆる種類の食べ物が得られる方が、特別だろう。それに、日本国内でも三日も泊まり歩けば、外食に飽きるものだ。何より、インド人以外にカレー好き国民と言えば、日本人しかいない。日本でインド・レストランがこれだけ繁盛しているのだ。インドでは、現地のカレーを上手く食す様にすれば、旅の食事情は、かなり良くなるはずだ。
チキン・コルマ
チキン・コルマとは、わたしが言う[南インド式カリー]のことだ。「コルマ」が何かと言えば、あるインド料理本によれば「“コルマ”とは小さい切り方のこと」とあった。他に「マトン・コルマ」と言うカレーも、紹介されていた。普通にチキン・カレーと言えば良さそうにも思うが、その場合、別の手順で作る北インドで普通に食される、スタンダードなチキン・カレーがあるのだ。名称はともかく、わたしの紹介するチキン・コルマとは、カレー・スパイスのベースにヨーグルトを多用した、さわやか風味な南インド式のチキン・カリーと言うことなのだ。
【作り方-約5~6人前-】
[手始め]先ず、鶏肉500㌘程準備する。鶏肉はおおよそ600~700㌘を用意し、皮や余分な脂肪、筋を丁寧に取り去って大体500㌘程になり、それを目安にしている。処理した鶏肉は6~7㎝角に切り、軽く塩と胡椒を振っておく。肉は煮てしまうと縮んでしまうので、大きめに加減して切り分けよう。なお、鶏肉の皮は焼き付けても煮込むので、ぱりぱり感が出ない。わたしはとることにしている。始めから皮なしチキンもある。また、チキンは豪華さを狙い骨付き肉も良いが、煮て行くと骨と肉が分裂し、肉がフレーク状になりやすい。
ショウガ30㌘程、ニンニク3カケ-30㌘程-を、すり下ろすし、ボールに入れる。残ったかけらは、みじんに切って一緒のボールへ入れる。ショウガとニンニクのすり下ろしを、わたしはおろし金でする。特にショウガは、繊維が絡みつき、きれいに下ろせないかもしれない。その場合、すり鉢とすりこぎで砕いても良い。繊維も残さず一緒にボールへ入れる。すり下ろしの際、奥様愛用のフード・プロセッサーを使わないのは、インドでは、もともとサドルカーンと言う、錐坊状の石杵と板状の石臼で、香料-ターメリック<ウコン>やショウガなど-を、少量の水と共に挽きつぶしていた。インド式カレーは、洋食のシチューの系譜にあるカレーの様に、小麦粉などでとろみを付けない。そこで、ウコン、ショウガなど植物の繊維も、カレーの要素として生かすのが「こつ」になって来る。
すり下ろした、ショウガ、ニンニク、とプレーン・ヨーグルト200㌘-わたしはB・ヨーグルト1パック450㌘を準備する。200㌘は半分弱の量-をボールであわせ、そこへターメリック、コリアンダーを小さじに2杯ほど入れ、全体を良く混ぜる。そこへ、先程のチキンを入れ、肉に良くまぶし、つけ込むようにし、ラップをして冷蔵庫内で4~5時間寝かせておく。
[煮込みⅠ]
鍋に油を入れる。鶏肉を炒めるのだが、分量を参考にしようと見たインド料理本で油は、大さじ3やカップ半量と言う様、わたし達の感覚では大目の油を使う。わたしの経験では、4~5人前の分量なら、大さじ1強で良いと思う。わたしは、カレーにピーナッツ・オイルを使う。ピーナッツ・オイルは、東京では、英国製品が2種ほど入手可能だ。香ばしく、軽くさらっとした味わいが良い。最近、注目のココナッツ・オイルはどうかと言えば、やはり独特の癖が気になる。またオリーブ・オイルは、煮込むので、粘度が気になる。ピーナッツ・オイルが無い場合は、普通のサラダ油でも良い。
鍋に油を入れ、シード状のクミン、アジョワン、マスタードを、一つまみ入れる。クミンかアジョワンは、是非、入れること。マスタード・シードはなければ入れなくとも良い。なお、油が熱いと入れたシードは、直ぐ焦げ爆ぜるので、必ず油が熱くなる前に入れること。油が熱くなるに従い、油に気泡とシードが湧き上がり出す。この頃合いで漬け込んだ鶏肉を、付け汁もろとも入れ炒める。ボールについた付け汁は捨てず、水少量で洗い、取っておく。
鶏肉の表面が炒まったところで、ボールに付いていた漬け汁と、1パックの残り分ヨーグルト、更に水カップ1.5~2-鶏肉が完全に浸る程度-を入れ、唐辛子3個を入れ煮込む。
[煮込みⅡ]
タマネギ大2個を千切りにする。出来るだけ野菜の繊維を生かす。千切りにしたタマネギを、フライパンで褐色になるまで丁寧に炒め-この時、炒め油は焦げ付かぬ程度少量で良い-全体が粘る状態にする。これを鶏肉を煮込んでいる鍋に入れ、火を弱火にして、じっくり煮込んで行く。ここで、鶏肉、タマネギが浸る様、水が足りなければ補う。材料を一緒にして20~30分ほど、煮込む。おおよそ肉に火が通った頃合いで、予め調合しておいたガラム・マサラ-調合済みが市販されている-を入れ、塩加減など、味を確かめておく。この時、より黄色みが欲しい場合は、パウダー状のターメリックを足しても良い。更に1時間程煮込む。この後、直ぐ食しても良いが、ガスを止めそのまま数時間から半日寝かせて置くと、スパイスが融合して奥深い味わいになる。
今回、カリーの作り方を紹介するに就いて、分量など料理本を参照した。普段、料理をする場合、おおよその見当で作っているからだ。ここに示した数字も大体の分量と思って欲しい。一応、ヨーグルトを使うカレーを料理本で確認したが、分量など詳しく出ていなかった。普通ヨーグルトは、鶏肉を漬け込む際に使用するだけのだが、わたしのカリーは、煮込むさい1パックの残りも鍋に入れてしまう。それと言うのも、ヨーグルトがカリーの旨味-いわゆる「だし」-を、構成してくれるからなのだ。例えば、このカリーの場合、トマトは使わないが、インド料理でトマトは良く使われる。トマトはグルタミン酸をもっていて、その料理に旨味をもたらす。このカレーの場合トマトや「だしの素」は一切加えず、ヨーグルトの酸味だけで旨味をを利かせる。
なお、ここで重要な指摘をしておく。煮込んでいる最中も、またどの段階においても、インド料理では、鍋の中の「あく」は、取らない。
日本料理は「だし」が命と言われ、丹念にすくい取るように言われる。インド式カレーを煮込む際「アク」は、取らない。カリーと日本料理では「ご飯の炊き方」にしても、料理の常識は異なる。何に由来して、どうして、こう言う違いがあるのか、未だわからないでいる。
【香料-スパイス-】
カレー粉と言えば、何種かの香辛料を調合して作られていること、今では良く知られている。本場インドのカレーには、わたし達が思うほど、多くのスパイスを使っている分けでは無い。インド風にカレーを作ろうとするなら、この際以下のスパイスを揃えて欲しい。
先ず、ターメリック(ハルディ)-日本ではウコンと言えばお分かりだろう。日本で健康ドリンクにもなっているので、薬効があることは良く知られている。日本では、黄色いパウダー状の瓶詰めが売られている。カレー料理の黄色は、ターメリックがもとなので、大目に買っておくと良い。
次いで、コリアンダー(ダニア)-タイ料理に付きものの香菜-シャンツァイ-パクチーだ。葉は消化を促進し、精力増強にも良いと言われている。シードは咳止め、解熱効果があり、カレーには、シードとパウダー両方を使う。
そして、クミン(ジラ)は、これもパウダーと種(シード)二種あり、シードは必ず揃え、パウダーもあると良い。体力回復に効果的だと言われる。シードは良く、インド・レストランのレジ横、皿に入れておいてある。一つまみかみ砕くと、口内に清涼感が広がり、胃腸の薬とも言われている。チャーハンを作った際、何気なくこのクミンのシードを、一つまみ入れ、炒めたことがある。すると、他にカレー粉など一切入れないにも関わらず、チャーハンがうっすらとカレー風味になったのだった。
本格カレー用に、12種或いは24種程、スパイスをセットにして販売している。セットには、クローブ(ラワング-丁字)やシナモン(ダルチニィ)、カルダモン(イラエチィ)など、スパイスの定番でカレー以外にも利用できる香料も揃っている。最初はセットでスパイスを揃えるのも良い。セットされたスパイスを調合して、ガラム・マサラを作っておくと、ドライカレーなど他のカレー味料理に応用できる。商品化されているカレー粉は、ガラムマサラと合わせて使ってみると良い。こうしたスパイスがあれば、本格南インド式カリーが可能だ。
カレーの辛さ、赤みは、レッド・ペッパーのパウダーで調節するが、わたしは普段、普通の鷹の爪を三本ほど入れる。なお、鶏肉を炒めるに際して、油を熱しながら入れた、クミン・シードと共に入れた、アジョワンは、ヨーロッパでは良く知られたハーブ-ロベージ-の一つ、消化を助ける効果があるそうだ。マスタード・シードは辛子の種子だが、特に辛みはない。マスタードは、殺黴-サツバイ-難しいことばだが、カビを生えなくする効果だそうだ。カレーに入れると黒いつぶつぶになり、噛むと香ばしい味わいがする。サブジーやサンバルに入っていて、インド料理以外にも使える。
もう一つ、近年注目のスパイスに、南インドが原産のスパイスにカルダモン(イラエチィ)がある。パウダーとしてスパイス・セットにも揃えられている。シードは、調度夏みかんの種の様な形でうっすら青い。カルダモンは脂肪を落とす効果があるとされ、日本でなら「ダイエット効果」があるとされるところだと思う。
1997年のインド旅行で、わたしは初めてマディア・プラデーシ州を歩いた。知らない土地で、バスの下車地を間違え、名の知らぬ町に降り立った。町の明かりが輝き出す夕刻、宿を探すしかなかった。バスを降りチャイを一服してと思い、屋台で一杯注文した。カップを渡す直前、屋台のおっちゃんが木製のレモン絞りを台にパンとばかり一打ちした。一瞬、動作の意味が気になった。
渡されたチャイを一口飲んで、その動作で何をしたのか分かった。そのチャイは、普段飲むミルク・ティーにはない独特な香ばしいような香りが、口に広がったからだ。チャイには、一粒何か種か何かが浮いていた。台に打ち付け砕いたのは、カルダモンの種子だった。紅茶やコーヒーにカルダモンの種子を軽くつぶし入れてみると、独特な苦香がする。カルダモンは、脂肪を落とす効果もあると言う。ダイエット好きの奥様方にお勧めだ。
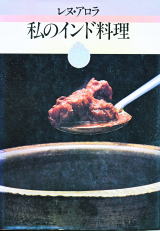 レヌ・アロラ著(1983年 柴田書店)インド人女性(ボンベイ出身)による料理本
レヌ・アロラ著(1983年 柴田書店)インド人女性(ボンベイ出身)による料理本
思えば食べたことのない料理を、料理本の記述だけで作ると言うは、無理があるのだ。多分、それを補うべく、料理本には如何にもそれらしく、美味そうな写真が添えられているのだろう。ルーを使ったカレーを食べた味の感覚からすると、何度も言うが、南インド式カリーは違う。
今、作り方を説明した、南インド式カリーと同じ味のカレーに、長らく現地南インドでも食べる機会が無かった。漸く同じ味に出会ったのは、1997~98年、OOTY(Udhagamandalam)で、旧友から地元のパーティーに誘われた時だった。パーティーのメイン・ディッシュに饗せられたカレーが、わたしの作る味と全く同じだったのだ。ただ、カルダモン(シード)と三つ叉枝状のクローブが多数入っていること。食べながら、それら種子を皿の縁に寄せなければならなかった。そんなスパイスを惜しげ無く使うことが出来るのは、さすが南インドらしいところと言えた。
現地の友人もメイン・ディッシュは、カリーだ。1998年 OOTY
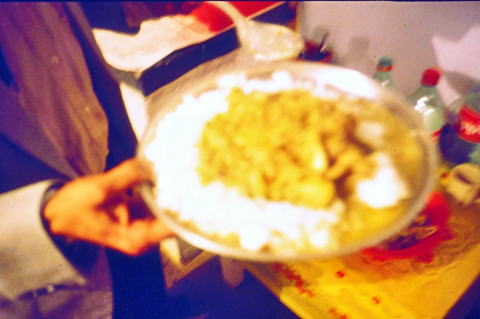
OOTYには旧友・知人が多く、食事に呼ばれることがある。最初、食事に誘われても、丁寧に断っていた。それでも再三誘われ、断り切れず誘いを受けると「肉は、チキンかマトンか、どちらが良いか」と訊かれた。食べ慣れた「チキン」と応えたが、インドではマトンの方がチキンより肉としては、やや格上になる。
夕方、招かれた家庭を訪ねると、奥さんと子供達、祖母ら一同、喜んで迎えてくれる。しかし、食事は一家全員揃って食べる分けではない。わたしと家長の二人だけで食し、子供や女性陣は、気にする風もなく傍らでテレビを見たり、談笑している。食事を誘われても、初めは気を使うのが嫌で、断っていた。しかしお誘いは、素直に受けておくものだ。長年インドと関わっていても、一般の人々と親しくなる機会は、決して多くない。特に、普通の家庭に迎え入れてもらえる機会は、とても貴重だ。地元の人と親しくなり家庭を訪れるのは、良いものだ。子供達と親しくなると、後の再会も楽しみになる。再び訪れた時、成長した彼らと再会できるからだ。
T先生のこと
カレーと言えば、わたしの作る南インド式カリーを、是非とも食べて欲しい方がいるのだ。その方とは、T先生なのだ。先生と出会ったのは、37年前、わたしが初めてインド旅行を思い立った頃のことになる。
T先生-竹原あき子氏-は、工業デザイナーとしての仕事を経てフランスへ留学、現地でデザインの仕事を経験し、帰国後わたしの通う大学の教壇に立たれていた。先生が教壇に立つたその同じ年に、わたしも大学生になったのだった。しかし、先生のことは最終学年まで、同じ校舎に通いながら、存知あげなかった。当然、先生の授業やゼミはもとより、習う機会は無かったと言うことだ。
それが、大学生活も最後の年、学内の雑用を言いつかったことで、ことばを交わす機会を得たのだった。当時、インド旅行を決心したのは良いが、そもそも「インドって、どんな国なのか」実は、何も考えていなかった。何かの弾みでインドへ行こうと思っていることを話すと、インドを紹介する映画が上映されていることを、教えてくれた。その後間もなく、インド旅行を「精神世界への旅」と言い変え、ブームを迎える。その直前だった。先生には映画だけでなく、わざわざ現地インドを体験して帰国した人まで紹介して頂き、会に行き話を聞くことにもなったのだった。
卒業間際、旅費を稼がねばならず、アルバイトをし直ぐ出発とは行かなかった。ぐずぐずしているうち卒業し、わたしはインド旅行の計画だけを抱えた、無為の人になってしまった。漸く周囲が忘れた頃出かけ、旅から帰ると直ぐ、渋谷の画廊に就職した。以後、極限られた学友以外、学生時代の交友は切れてしまった。
既に8~9年前になるだろうか、療養中の学友を見舞う機会があり、当時の旧友と卒業以来の再会を果たすこととなった。その折、T先生が、退職間際大きな病気に罹ったことを人づてに聞いたのだった。小柄で細い体にも関わらず、何時も活動的なT先生のことが頭をよぎった。
 竹原あき子 『縞のミステリー』(2011年 光人社)
竹原あき子 『縞のミステリー』(2011年 光人社)
T先生のことが気になっている時、先生の新しい本-『縞のミステリー』(2011年 光人社)-を偶然書店で手にした。この本は、江戸期、唐桟<トウザン>として、インド東海岸からもたらされた縞が、当時の人々に爆発的に流行することから書き出されている。唐桟に代表される布地に織られた縞は、東西交易の船により、東南・東北アジア及び日本ばかりでなく、アラビア海を越えアフリカ・ヨーロッパにまで渡る。縞が織り出された布が、世界各地にもたらされなのは、何故なのか。縞の何が、人々を魅きつけたのか。工芸・デザイン誌の余白を埋めるエッセーだ。
江戸時代流行した生地に織られた縞の伝播を温ね、柔軟で細やか、瀟洒な筆遣いは、遙か遠く平安時代にあった随筆の伝統を思い起こさせる。更に読み進むに従い、遺された布とその意匠から、遠い時代の隔たる地域で人々が、布とその意匠に魅惑された不思議-ミステリー-を読み解く、知的な謎解きが試みられ奥行きのある物語が展開されるエッセーなのだ。読む者を刺激する、知的なエンターテインメントにもなっている分けだ。「だって、タイトルにミステリーってあるじゃないの! 」と言われてしまえば、漸く気が付くわたしが迂闊だった、と言うことになるのだが。
それはともかく、わたしが本を読んで、熱くなったことがあった。それと言うのは、海外からもたらされた布地の縞を、安土・桃山時代の武士から町衆が、また江戸の粋な女性も好み、それは江戸時代に浮世絵にまで描かれ、人気を博した。何とその縞の布地の生産地が、まさにインドだったと言うことだ。
長らくわたしは、ジャワやルソン島からの伝来とされた、名物布や古渡り-外国からもたらされた-の更紗の、その大半がインドで作られた布地であることを知って、衝撃と興味を押さえられずにいたところだった。縞の布地の輸出拠点こそ、ベンガル湾に面する東海岸一の港湾都市マドラスだったのだ。
既にT先生は、そのマドラスへ赴くことまでしている。先生は、たまたまインドの映画や、インド旅行の経験者を知っていたのではなかった。縞を通してインドへの関心を持っていたことを、わたしは漸く30年以上経過して、知ったのだった。
先生のこの著書を、わたしは3.11の直後「計画停電」の合間を縫って読むことになった。それも、何かの巡り合わせの様にも感じた。ともかく、本をお書きになっていることから、元気でいらしていることが分かり、一安心した。
先生の新しい本の完成を祝し、かつ感動をもって読み終えたことを知らせたく、手紙を差し上げた。しばらくして、わたしの手紙は、住所不明で戻って来た。まさかとは思ったが、わたしが卒業してから30年以上経っているのだから、同じところにお住まい方が、希なことだ。手紙は、大学宛てに出し、現在の住所に回送してもらった-個人情報保護があり住所は、教えてもらえないのだ-。
ややあって-海外に行っていたとか-、T先生からお返事に『そうだ 旅にでよう』と言う、先生自らの旅と出会いを、短い文章て綴り自ら刊行した本-ピンクの見返し、表紙はピンクの縦縞で、ジャケットの下3分の1にも、白地との境をうっすらグラデーションにしてピンク色が使われている-が、送られて来た。便りには、原発に関する本-多分、『原発大国とモナリザ』(緑風出版)だろう-を執筆中とのことだった。
直ぐT先生に本のお礼と、一度是非ともわたしの南インド式カリーを召し上がって頂きたい旨を伝えた。昨年、カレーの勧めへの返事の絵葉書が届いた。何とT先生は、カレーと言うものが、余りお好きでないと言うことなのだ。
そう言えば、先生の著作には食物に関する話題が、無いことに思いあたった。先生がコーヒー好きなのは、知ってはいたが、ものを食べると言う、本能的な姿はそぐわないことにも、思い至ったのだ。
そこで、わたしはあることがひらめいた。T先生もそうだが、一般的にカレーと言うと、日本のルー(インスタント)を使った、ジャガイモとにんじんがごろりと入った、如何にもねっとりドテッとしたカレーをイメージされているのではないかと。
先生とわたしが、奇しくもインドへの関心を共有していたことから、カレーを召し上がって欲しく思ったと言うだけではない。重い病から治癒したT先生に、敢えて南インド式カリーを勧めたのには、わたしのインドでのある体験があってのことだった。
左 2007年、ケララ州の民家で 右 カルダモン


2007年、南インド西海岸に位置するケララ州を旅して、コタヤムで自宅-居間兼ベッド・ルーム-を宿に貸す家に、滞在した時だ。家の主人は、天井からぶら下がる扇風機(バンカー)の強弱三段階を常時最強に設定していた。一人の時、わたしは「弱」に設定し、就寝の際は必ず切った。それが、翌朝目が覚めると、何時の間にか「最強」になって、回っているのだ。亜熱帯のインドでも南インド、ケララ州はアラビア海に面し一年中熱帯らしい暑さと湿気のある地域だ。そこの住人は、終始扇風機に当たりつづけも体調に別状がないのだろうか。
ある夕方、宿の主人が仕事-日中、オート力車のドライバーだ-から帰ると「わたしの為に買って来た」と、中身が凍りついたミネラル・ウォーターのペット・ボトルを差し出した。
この旅でわたしは、飲料水は市販のミネラル・ウォーター以外口にしない様心がけていたのだ。たまに、ぎんぎんに凍りついたボトルに当たるとラッキーとばかり、冷え切った水をボトルから直に飲むのは格別美味い。夕食後は決まって、宿の近所の雑貨屋で冷えたボトルを買い、寝る間際思うさま冷たい水を飲んで寝った-冷蔵庫など備わっていないから、翌朝を待たず一気に、ボトルの水は部屋の温度と同じに暖まってしまう-。冷たい水を飲んで一日を終える、それが旅の後半、南インドでの習慣になった。
旅も最終盤北インドに戻り、最終地ヴァラナシで突然腹痛に見舞われた。この旅は、インド入国20日程で免疫力が切れ、下痢に苦しめられ、体のことを嫌っと言う程思い知らされていた。だから、この腹痛が「腹をこわす」と言うより、明らかに冷えによるものであることを直感した。
わたしが寝る時、扇風機を必ず切ることは、言った。それだけではない、掛け布団代わりに現地で買ったシーツ大の布を、就寝の際は必ず腹部辺にかけて寝ている。そこから、明らかに寝る前に飲む、冷たい水によって胃腸を冷やしたせいで、腹痛を起こしたのが分かったのだ。その時、カレーに就いてよく言われる、その薬効のことが具体的かつ、身をもって理解出来たのだった。
カレーの素になるスパイスが、どれも薬効のあるものばかりだと言うことは、今では常識になっている。特に、酸化を防止する効果が、顕著の様だ。暑い国だから腐敗の防止に効くスパイスがあると言うのは、神の配ざいと言うことか、インドらしい知恵を感じさせられないではない。
その時強く頭に浮かんだことは、自ら作るカリーの作り方でも紹介した、カリーのベースにショウガが多用される、と言うことだ。ショウガと言えば、その頃日本で女性の冷えに効果的と評判になり、様々な飲み方、摂取り方が各所でブームになっていた。また、ショウガだけでなく、ニンニクは細菌に対する殺菌力やエネルギーが豊富だ。ショウガもニンニクも体の内部から暖め、血行や代謝を助け免疫力を強化する作用の植物とわれている。
そのショウガや生姜化の植物は、ケララ州の熱帯雨林で自生したもが良く見られる。第一、カレーの黄色の素、ターメリック(ウコン)にしてから、黄色い粉を吹いた様なかたち以外、生姜そっくりな植物の根なのだ。それにしても、暑い国の人々が、体を温めるに適した植物や種子を、何故積極的に摂取するのか。
暑い国では、人は当然自らの体を冷やす必要がある。特に水は命に関わるので、頻繁に飲まねばならない。インドでは客人を迎えるに際して、一杯の水を振る舞う-日本の、茶でもてなす様に-。それは、水が貴重だと言うことでもある。インドは、大河ガンジスで知られる国だが、あれ程の大河があっても、水は貴重視されている。水の豊富な日本では、恵まれ過ぎていて、その貴重さを忘れがちだ。
幾らインドの様に暑い世界の住人でも、人の皮膚の内側、特に内臓はデリケートだ。また、幾ら生命の維持に水は不可欠だからと言って、年がら年中頻繁に水を飲み体の内部から、冷やして健康に良いことはない。日々必要な水を摂取しても、内臓の血行や体温は、下げたくない。そこで、血流を良くし体温を保つ、冷え防止の食品を摂ることが、古来から行われていたのだ。
季候が暑く体を冷やす必要や、水分を多く摂らざるを得ないことから、内蔵の血行を良好に保つ食品を摂ると言う発想は、何と合理的かつ、賢いことか。インドに比べ遙かに恵まれた環境に暮らすわれわれには、容易に気が付かないことに、初めて、そして漸く気が付いた次第なのだ。それも、自らを検体にして。
最近、カレーや素になるスパイスの薬効に関して、日本でも関心が高まっている。カレーと言う食品が健康、特に免疫力の向上に、良いことが認識されて来た。カレーは食べて美味いだけではなく、繰り返し食べても飽きない。作り慣れれば、比較的安価だ。
わたしは老母と同居しているので、出来るだけ魚を食べさせる様心がけているが、新鮮な魚はなかなか手に入りにくいし、あっても、なかなか良い値段だ。和風の味付けは、飽きやすい。カレーならば、他に新鮮な野菜を補いさえすれば、バランスのとれた食事が可能だ。スパイスの薬効成分を、美味く食事で摂ることが出来れば、免疫力の向上に最適だ。日々摂取する食事こそ、健康を維持する最大の好機でもある。
勿論、カレーを一皿食べたからと言って、一気に免疫力が向上する分けでは無い。しかし、美味しい食事は、人を元気にしてくれる。先生を始め友人、そして読者諸兄に、是非とも南インド式カリーを食べて欲しいと思っているのだ。
ポンディシェリー近郊のビーチ 中央腰掛けている男性が小屋の大家 右端白シャツにルンギーの若者は力車マン 1983年頃

2015年4月 マンゴーハネダ
トップページに戻る





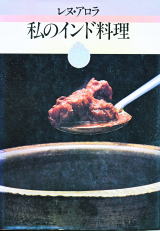 レヌ・アロラ著(1983年 柴田書店)インド人女性(ボンベイ出身)による料理本
レヌ・アロラ著(1983年 柴田書店)インド人女性(ボンベイ出身)による料理本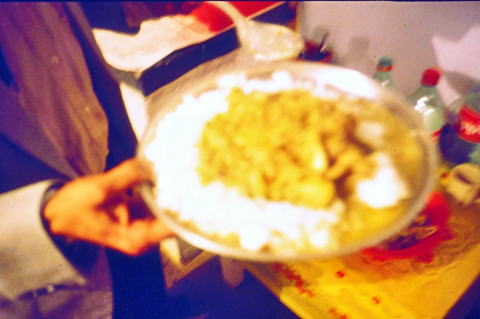
 竹原あき子 『縞のミステリー』(2011年 光人社)
竹原あき子 『縞のミステリー』(2011年 光人社)

