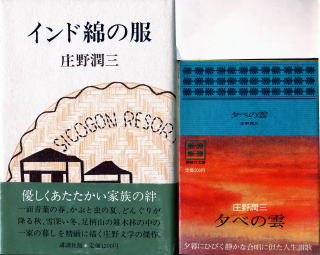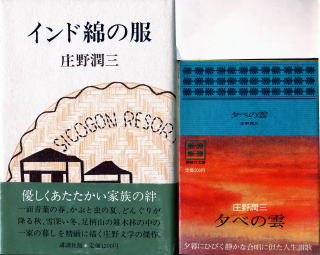[東京・建築・遊歩]後編
郊外の文学
今春、[東京・建築・遊歩]を書いた。思い半ばでアップした。何か大切なことが、のど元まで出かかっていながら、上手くことばにならずにいた。その思いに切りをつけ、後半と言うのか「纏め」を書きたいと考えていた。
何時もながら、本に就いての話題で恐縮なのだが、この春、庄野潤三『インド綿の服』(1988年 講談社)を読んだ。著者、庄野潤三は2009(平成21)年9月、88歳で亡くなった。この本も随分前の著作と言うことになる。庄野は『インド綿の服』の後も、コンスタントに小説を書き続けた。わたしは、その後書き継がれた小説を読んでいない。この先、本に出会えれば読んで行きたいと思っていたところだ。
先ず、26年経過した古い作品を読んだのは、題名に「インド綿の服」とある様にインド趣味のわたしとしては、一応読んでおきたかったことがある。しかし、この小説は国としてのインドとは、直接の関係は何もないのだ。この小説集の題名に就いて最初に説明しておこう。この小説集は、郊外に住む老夫妻(庄野)と神奈川県南足柄に家庭を営む長女との交流を描いた短編が6編収録されている。本の題名「インド綿の服」とは、老夫妻の母親が、店先にインド綿の、着やすそうで雰囲気の良い服を見つけ、足柄山に住む娘に「似合いそう」だからと送る話から由来している。他にインドと関わる話題がある分けではない。この本も庄野のこれまで書いて来た、一連の家庭の些事を暖かく描く小説の一冊だ。
この小説の様に、普通の家庭生活を描く庄野の作品に就いて、今どれ位知られているだろう。わたしが庄野潤三に就いて解説するのは、おこがましい限りだが、庄野がどんな作家であるのか、わたしの読書体験も交え、簡単に述べておきたい。
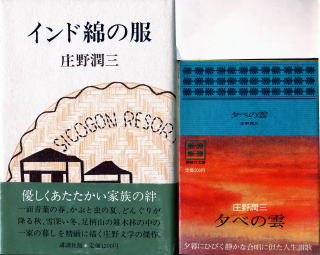
70年代、読書の楽しみ知ったわたしには、大体、年に一二冊本になる庄野潤三の著作を読むことは、他の作家では得難い喜びがあった。その頃、庄野は「第三の新人」と評され、同じ芥川賞作家にあっても、既に成熟した作風として高く評価されていた。
庄野の新刊は、扱いは地味ながら必ず、新聞等読書欄で採り上げられてもいた。庄野の本が出れば、必ず読むと言う様なファンも少なからずいたはずだ。当然ながらわたしは、そこまで腹の据わった読者ではなかった。70年代は純文学の時代だった。戦前の世代も元気だったし、今は亡き安部公房、倉橋由美子と言う様な方法を意識した作家も多数活躍していた。そうした戦後派純文学作家に対して庄野は、戦前の教育を受け、当時既に大人の風格が備わり、高校生のわたしが読むのは、知的な意味とは別の背伸びが必要だったのだ。
庄野潤三は、大正十(1921)年、大阪に生まれた。父は帝塚山学院の校長、童話作家庄野英二は、次兄。昭和14(1939)年、大阪外国語学校英語部に入学、その頃中学時代の恩師伊東静雄と文学的な交流する。昭和17(1942)年、九州帝国大学文学部に入学、1年上に島尾敏雄がいた。
戦後、大阪で島尾らと同人誌を創刊するなど文学活動をし、昭和28(1953)年、東京練馬に転居する−なお、文庫の解説によれば、生田に居住する前、練馬から上石神井に転居した時期もあったと言う−。昭和30(1955)年「プールサイド小景」で、第32回芥川賞を受賞している。同時期に芥川賞を受賞した、小島信夫、吉行淳之介、安岡章太郎、らと共に、以降「第三の新人」と呼ばれ注目をされる様になる。「第三の新人」と言われた作家達は、戦中に学業を終え戦後、作家として60年代以降、旺盛に仕事を始める。彼らは、戦後派の純文学の中で、私小説的なスタイルを採った小説が印象的だった。わたしの場合「第三の新人」のうち、庄野の他に安岡章太郎を断続的ながら、比較的近年まで読みつづけて来た。
庄野潤三と言う小説家を知る切っ掛けは、高校生の初めに伊東静雄の詩を読んでいたことによる。当時、手近な新潮文庫に『プールサイド小景・静物』があった。手元に奥付を見ると、文庫化されたのは、昭和40(1965)年、わたしの文庫は70年10月六刷とあり、ほぼ1年に一度増刷されていたことになる。この文庫に収録されている短編は、どれもおおよそ家庭生活の一情景を描いた短編小説だ。若者好みの小説にある様な、非日常的内面や、心の奥の狂気や恋愛など無頼派的な文学性からは遠い作風だ。当然、当時の純文学にある西欧の近代小説を範に仰いだ、言語的方法意識が顕著な作品でもない。収録されたどの作品も、普通の高校生でも分かる日常の情景を採り上げていて、それがかえって、新鮮だった。
『プールサイド小景・静物』を読んで間もなく(1971年)『夕べの雲』が、当時創刊早々の講談社文庫から刊行された。早速読んで、庄野潤三と言う作家は、家族や家の近所のことを描く特別な存在だと、高校生ながら思ったのだ。以来、新刊が出ると手に取る様になった。
大学生の二年目、現在も親しくしている友人Sと本の話をする切っ掛けに、庄野の『夕べの雲』のことが話題になったことがある。Sも庄野の小説に好感を抱いており『夕べの雲』を切っ掛けに、それ以後、学内で本を話題にことばを交わす様になった。以来、今日まで交友がつづいている。
そんなこともあり『夕べの雲』と庄野潤三と言う作家は、今日まで忘れられない存在になっている。わたし個人にとって重要な『夕べの雲』−この文庫には、70年までの簡単な年譜が付いている−は、庄野潤三にとっても一つの区切りになる作品の様だ。付属の年譜によれば、庄野は大阪から東京に居を移し、そこで『プールサイド小景・静物』を纏める。その後石神井公園に移り、次いで更に自然環境を考慮して、東京と神奈川県川崎市に隣接する生田丘陵に住居を移す。そこを舞台に書かれた連作長編−新聞小説として発表された作品−が『夕べの雲』だ。以後、この地で自らの家庭から題材を採る小説が、描かれることになる。
わたしの母校の大学は、小田急沿線の町田市にある。通学には、新宿から多摩川を越え、生田の丘陵を縦断し、更に柿生の先だ。70年代半ば、多摩川を渡ると、一気に多摩丘陵の緑が迫って来た。当時、生田丘陵辺に途中下車する機会があった。駅前こそ商店があったが、そこを外れると家屋はほんのまばらに点在するだけの起伏のある里山だった。そこは「郊外」と言うより、明らかに「田舎」の趣だった。その頃、語り合った記憶はないが、友人のSは生田と柿生の中程、百合ヶ丘に自宅があった。殆ど『夕べの雲』の舞台と同じ丘陵に居住していたことになる。
もう一つ、学生時代の偶然がある。現在母校で教鞭を執っている先輩のM氏の御尊父は、良く知られた中国文学者で、戦前九大で中国文学を講じていた。その関係で、在学中先輩のM氏に尊父が庄野潤三と交流があったことを聞いた。庄野の九大時代の交友は、小説『前途』(1968年 講談社)に描かれていて、M氏から話を聞いて本を開いたことがあったのだった。
79年10月インド旅行に出た。インド旅行は、調度卒業旅行と言った趣だった。帰国後、80年4月から渋谷の画廊の店員として、社会人の生活を始めた。
80年代、社会人として生活に追われ、戦後文学など日本の文芸書からは、急速に遠ざかった。その時期、それまで読んで来た小説類を整理してしまったが、小説類が古本屋に好まれず、庄野と大江健三郎など、他にもまとまって手元に小説本が残った−そうした当時の小説を時々、読み返してみるが、多くの場合かつての様な感動は覚えない−。今、わたしの所には、『インド綿の服』とさきの文庫二冊を加えて、庄野潤三の本は20冊ある−なお、この稿を書く前、ネットで検索した。庄野の刊行された著作は、50冊を少し超える−。『インド綿の服』以降の小説、80年代後半から手にすることのなかった庄野の本を、今後再読してみたいと思った。
そんな気持ちになったのには、2003年、川本三郎『郊外の文学誌』(新潮社)を読んだのも、切っ掛けの一つだった。川本三郎の『郊外の文学誌』は、都市の文学の関わりを辿る文学論だ。その本の最終章に「郊外に憩いあり 庄野潤三論」と言う、小さな庄野論を置いている。川本の『郊外の文学誌』を読んで、久々に庄野潤三を読んで見たくなったのだった。
現在『プールサイド小景・静物』や『夕べの雲』を読むと、主人公の父親は、執筆していた庄野と同じ、未だ中年に成り立て位の、今のわたしより若い年齢であることが感じられる。作品中、子供と映画に就いて会話がある。その映画では、ニューヨークの貧しい移民が、自分のアパートの壁に家を持つまでナイフで印を付ける。しかし、子供が出来ても、アパート暮らしがつづく、と言うものだ。映画のストーリーを語りながら、著者の家族と家に対する意識が強く表れている様に思えた。庄野にとって、妻と子供ら皆が生活を共にする家は、家庭や家族と同義なのかもしれない。
文庫の諸作品での家族とのやり取りに於いて、子供達は未だ幼い様子が文章から分かる。それが、70年以降80年代初めのまでに出された小説本−例えば、1972年「岩波少年少女の本16」として刊行された『明夫と良二』−の頃にはは、子供達の反応は、少年らしい如何にも大人びて来た様子が読み取れる様になる。著者も、また彼の描く子供達も、時代を追って成長している様子が読者にも伝わって来るのだ。
庄野は70年代から、年間二冊程度コンスタントに小説を上梓していた。一つは、市井の庶民の人生を聞き書きするスタイルの作品−例えば『屋根』(1971年 新潮社)や『水の都』1978年 河出書房新社)など−そして自らの家庭生活から取材し、庄野独自のスタイルになった小説があり、『インド綿の服』もそれに連なる作品だ。川本も言っている。
<庄野潤三は、九六年単行本として出版された『貝がらと海の音』を皮切りに、以後、『ピアノの音』(97年)『せきれい』(98年)『庭のつるばら』(99年)『鳥の水浴び』(00年)『山田さんの鈴虫』(01年)『うさぎのミミリー』(02年)と毎年のように、この東京の郊外に静かに暮す老夫婦の日々を綴った連作を書いてきている。>
88年刊行の『インド綿の服』は、足柄山に家庭を持つ様になった長女から届く便りを紹介しながら、話が展開する。深刻なストーリーが、あると言う分けじゃない。家庭菜園の野菜が届いたり、老夫婦からこまごましたものを送ったり、その間、娘家族の暮らしの様子や子供達(孫)のことが語られるのだ。そして、老夫婦の夫(庄野)は、脳溢血のリハビリも順調に、娘を誘い杖をついて日比谷まで、宝塚歌劇団のレビューを観劇しに行く。観劇の後、レストランで食事を奢ったり、円熟した父親の暖かさが読者の気分を暖める。
川本三郎『郊外の文学誌』−最終章「郊外に憩いあり 庄野潤三論」
ここで川本三郎『郊外の文学誌』に就いて、少々触れておきたい。近年、大部な評伝を上梓して円熟した評論を書いている、川本三郎の著作に関しては、戦後日本映画で描かれた女性像を追った『今ひとたびの戦後日本映画』(1994年岩波書店)など、何度か触れて来たことがある。わたしは、川本の評論を1977年のデビュー作『同時代を生きる「気分」』以来、読んできた。1990年『大正幻影』(新潮社)を上梓する辺りまで、少年文学やサブカルチャー、マンガなど、時代の流行を敏感に読み取るライトなエッセーで健筆を振るった。現在は文藝評論家の風格すら感じさせるまでになっている。それでも、昔を知るせいか「批評家」と言った、わたしには堅苦しい存在ではない。
『郊外の文学誌』は、そんな川本の長年研鑽の「町歩記」が功を奏した『大正幻影』に連なる長編エッセーだ。明治文学が江戸から東京へと、町の変遷を導いたとするなら、大正時代の東京は、郊外へと広がり、文学の背景にも郊外が採り込まれる。川本は、大正末から戦時期昭和、戦後復興期の東京まで文芸作品や映画から郊外の情景を読み解いている。「『大正幻影』に連なる」と言うのは、この本の序を除き13章のうち、10章余り昭和初年から戦後の復興の時期に亘る文芸作品が、主要だからだ。本の半ば辺りから大久保、中野、荻窪、高円寺、阿佐ヶ谷、そして荷風と葛飾周辺まで、大凡戦後の早い時期までが語られる。高度成長期以降となるのは、最終章までの3章で扱われることになる。
その3章の始めは「武蔵野の広がり−小金井界隈」で、ここでは三浦朱門、黒井千次が、次いで「多摩川沿いのサバービア」では、村上龍『テニスボーイの憂鬱』が採り上げられ、最終章として「郊外に憩いあり 庄野潤三論」が置かている。漸く本の後半を迎える残り3章辺で、扱う時代が昭和から平成と言う、現在に追いついて来た感がある。川本が文芸作品から現在の「郊外」の営みを、どう読み取っているのか、わたしなりにかいつまんでおきたい。
この本の<書き下ろし序章>は、石井桃子『ノンちゃん雲に乗る』を持って語り出される。戦前、軍国主義の暗雲が垂れ込め始めた時代に現れた、秋空の様に軽やかな児童文学から始まるのだ。最終章「郊外に憩いあり 庄野潤三論」により結ばれる、文学的「郊外」論は、この種の評論として明るい−肯定的な−著作として終始している。この文章を書くにあたり、現在の小説が扱われた3章だけでなく、ざっとながら初めから目を通して見た。2003年刊行当初の、わたしの個人的な読後感と、現在の「郊外」の印象には、明らかな違いが生じていることに気がつかないでは、いられなかった。
当時、川本の作品と郊外に対する、肯定的で明るい評価に、何の違和感も抱かなかった。それが、現在読み直して見ると、その後、3.11を経験し、また既に庄野潤三も世を去った現在、とうてい当時と同じ、明るい肯定感は抱けないのだった。川本は「郊外」を英語のSuburbiaに比す。カポーティーやアーヴィングの訳書もある川本は、英文学の造詣も深いのだ。長年郊外暮らしをしているわたしとしては、川本が思い浮かべるアメリカのサバーブに、現代東京の郊外を比するのは、無理があると思う。やはり、非なるものだと言いた気持ちになった。
大体、東京に暮らしてるわれわれとアメリカ市民とでは、気持ちも暮らし向きも異なりる。日本の郊外とアメリカのサバーブを重ねるのは、文学的な思い入れが過ぎた見方ではないだろうか。
また「武蔵野の広がり−小金井界隈」は、わたしの居住区域にもかかり、文中の地名は実際に知っている場所だ。例えば、RCサクセッション忌野清志郎の唄にも名高い「たまらん坂」も、学生時代から行き来した経験がある場所だ。そうした地域を変貌を、三浦も黒井も違和感として、明らかにしている。―「郊外のこの変貌をもはや嘆くのではなく、所与の現実として受け入れるしかない。」―と、クールに川本は章を結んでいる。しかし「所与の現実」として受け入れたわれわれは、更に生きて行かねばならない現実があるのだ。
続く「多摩川沿いのサバービア」でも、村上龍『テニスボーイの憂鬱』を採り上げ、小説の主人公−彼は横濱市内陸部から、町田辺に生活圏を持っていると想定される−の時代と地域への愛着のなさを採り上げ、その感覚を川本は、現代のやり手青年の時代や地域から自らに反射する「憂鬱」と言う感覚に解釈し、その「憂鬱』を大正期佐藤春夫が『田園の憂鬱』に描いた「憂鬱」に重ねている。
わたしには大正期の「憂鬱」が、現代の東京近郊で生きる者の日常感覚にある「憂鬱」と、とても同じには思えない。大正期の小説で置き換えるのではなく、現代人の抱く「憂鬱」の読解が無くてはならないはずだ。
今にして思うのだが、中央線沿線の町で育ち、その後も町に居住する川本には、郊外生活者の「憂鬱」や切実感は薄いのではないだろうか。
それと言うのも、川本も言う様に郊外−現在では、中央線沿線の荻窪辺など−へ意識的に居住した初期の人々は、作品から明かしている様に、小説家や文化人など比較的裕福な知的階層の人々だった。調度、中央線沿線に居住する、川本自身を想定することも可能な気もする。川本が採り上げる大正時代から戦前にかかる文学作品の舞台となる郊外は、そうした作家や知的富裕層の生活する場としての郊外なのだ。
川本の得意とする戦中・戦後の日本映画を引きながら、撮影所のあった鎌田や、現在すっかりハイソな郊外になった二子玉川も紹介している。それらの場所は、確かに昭和30年代まで郊外と言うに相応しいところだった。そこから多摩川を越えると、川崎市になり京浜工業地帯、上流の登戸周辺に一歩踏み込めば、田舎とか村と呼んでも言い過ぎにならない環境で、70年代も郊外と言う明るい趣は無かった。
東京の西郊から南、神奈川県を区切る様に多摩川が流れている。何もテニスボーイだけではなく、東京郊外に暮らす者は、多摩川を行き来しながら暮らす必要が生じる。そうした、境界的−同時に象徴的でもある−多摩川を考察する際、川本が岡本かの子小説『混沌未分』を引用するのは、確かに批評家の手腕と言いたいところだ。しかし、岡本かの子が描く現代の「川の妖精」や土地の霊をもって、現代人の置かれる土地(住む場所)にまつわる、違和感や孤独感を説明出来るかと言うと、かなり違うのではないかと思はざるを得ない。
以前、バイクで走り回って、丸子橋から川崎市側の神社脇に、ひっそりと建つ岡本太郎による、母かの子を記念するオブジェを発見したことがあった。そこから、二子橋の架橋と段丘状の対岸(二子玉川)にそびえる、高級マンションやショッピング・センターこそ望見可能だが、多摩川の水面は国道の車の流れが遮り、見ることを得なかった。


今を生きるわれわれには、過去の文芸作品から慰藉を得ることは、最早出来ないのかもしれない。3.11以来3年が経過したとは言え、あの災禍を経験した後を生きるわれわれには、早いもので11年前の著作となってしまったこの本が「文学誌」と題されているから致し方ないとは言え、小説や映画と言ったフィクショナブルな世界からもう一歩踏み込んで、あり得べき都市や郊外を構想してあれば、どんなにか良かったかとも思うのだ。
本も読んでから、時を置いて見れば、われわれ読者は、年齢を重ねる。過去の自分と現在の年齢を重ねた自分とでは、異なる。そこから過去に読んだ本が、何かしら物足りなく感じられるのは、自然な成り行きだろう。
主なき家
庄野は既に亡く、庄野の家族の消息を描く小説は、永遠に中断された。今、終章に「郊外に憩いあり 庄野潤三論」があることは、意味深長だ。そして、この先まで生きるわれわれは「郊外に」もせよ、何所にも憩いはないことを承知している。
川本が自著の最終章に「郊外に憩いあり 庄野潤三論」をおいたのには、おそらく、川本自身も、庄野小説の「家族の憩い」が、現代では希な文学的希求とも言え、小説的世界であることを充分承知していたからこそ、最後に据えたのだろ。
わたしは小学校6年の夏休み明け、東京都、豊島区巣鴨−ここは、何度も言うが「老人の原宿」なのだ−から、H市へ引っ越した。当時、H市は郊外と言う趣より、わたしの実感からすると、田舎と言うに相応しかった。何しろ、トイレも水洗では、なかったのだ。H市と埼玉県T市との境界は、80年代全国的に人気を博すアニメ映画の舞台として、注目されることになる。調度、わたしが移って来た時期に設定されているのだった。そこは如何にも牧歌的な環境ではある。引っ越して来た当初、実際の移住者には、自然の猛威に囲まれ不安な毎日だった。当時、町子のわたしには、文化果つる土地だった。
現在のわたしとしては「郊外」論より「田舎」に就いて考察した論攷が読みたい。若い頃から、萩原朔太郎を読みつづけて来た。彼は群馬県前橋出身、実家は医家で彼の家、萩原医院は今で言うところの開業医院だ。それでも当時は群馬県ナンバー2、現代の規模から推し量れば私立の綜合病院と考える方が適切だ。家庭はお大尽、一応やりたいことは許された。前橋は現在瀟洒な地方都市だ。萩原は生前その土地を嫌った。田舎が何より嫌だったのだ。「生まれ故郷」そればかりは、どうにもならない。わたしの実体験もあり「都市論」以上に「田舎」論こそ書かれなくてはならないと思ったものだ。
川本が『郊外の文学誌』を書いた2003年以来10年以上を経過して、やり手青年(テニスボーイ)の「憂鬱」の後に、主亡き郊外の家が残されている。古びたと言う程には、年月を経ていないにも関わらず『郊外の文学誌』の最終章を読むと、そこにある種「寂寥」が漂うのを払うことが出来ない。寂寞を過ぎ、廃墟の趣すら漂うと言うべきか。
*
庄野潤三を再読する前、江藤淳『成熟と喪失−"母"の崩壊』(1967年 河出書房新社)を、40何年振りに再読した。著者はアメリカ遊学から帰ってこの評論を書いた。戦後の日本文学の「母性に溺れ父性の欠如」を、エリック・H・エリクソンの精神分析的読解手法をもって分析した。江藤の円熟期を期した、代表的評論だ。
「第三の新人」を論じた、一時代を画したこの本の後半、当時発表されて間もない『夕べの雲』が論じられている。
この本を締めくくることばとして、江藤は−漱石論で知られる評論家らしく−夏目漱石『明暗』を引き、母性の切り捨てた喪失のうちに、孤独を引き受け父性を獲得した個人に於いてこそ、来るべき漱石の『明暗』にも比すべき小説が書かれる、と宣言した。『明暗』に比すことが適切か分からないが、庄野潤三の文学は、家庭や生活の些事を採り上げながら、その根底に孤独を引き受けることにより、父性のあり方を示す、希有な資質を隠した文学だったことが、評論が刊行された当時より、庄野が逝去し作品が途絶えた現在、一層切実な感覚で証明された様に思えた。
『インド綿の服』を読み終えて後、一向に心が晴れなかった。何より、既に庄野潤三が故人であるからとも思った。始まりがあれば、終わりは必ず来る。締めくくる様な終わり方より、突然途切れる終焉の方が良い。伝統芸能の世界みたいに誰か庄野の名前を引き継ぎ「二代目庄野潤三」を襲名する者が出、同じ様に家族とのやり取りを小説にして行くことがあったとしたら、それはあさましく、見たく無い。読者も著者の逝去と言うことを、引き受ける必要があるのだ。
『夕べの雲』を現在のわたしが読むと、登場する親子が、今や読者のわたしより若いこと言うことは、既に申し上げた。著者も読者もこの半世紀余りの時間、年齢を重ねて来たことになる。作家と共に読者であるわたし達も、それなりに年齢を重ねて来たと言うことなのだ。わたしは、読んだ本と共に、その作家が成長するに合わせ、読者のわたし達も年齢を重ねられたとするなら、それはささやかではあるが、幸福なことだと思わないではない。現実は、物語を模倣するのだが、物語の主人公の様に著者は不死身ではいられない。
わたしが、庄野を初め戦後文学に触れたのは、前に申し上げた様に70年代だった。それから現在まで、そろそろ半世紀にもなろうとしている。その頃、読み始めた作家の多くは、既に故人になっている。
一冊の本を読み終えて、何か心が晴れないのは、著者−庄野潤三−は既に他界していて、新たな作品が書かれることは、金輪際ないと言うことからか。小説の父親は残り、作者はいない。小説のなか生田の家はどうなっているのだろう。残された老妻は、どう過ごすだろう。息子の誰かが、住むだろうか。つい、そんなことも考える。
*
近所に人の住んでいない住居があることに、改めて気が付いた。居住者のいない空き家が、東京都内でも増えていることは、TVのニュース番組でも取りあげているので、ご存じの方もあろう。
わたしは今いるところに、60年代後半から住んでいる。当時は雑木林が彼方此方にあり、まばらな住宅の周囲に畑が広がっていた。地方都市近郊の農業地区と差ほど変わらない景色だったのだ。そして、此処に引っ越して来た当時、家の近所には同じ中学に通う、同年位の年齢の顔見知りは、何人もいた。今近所に、当時を知る同世代は、皆無と言ってよい。近所に同年配の知り合いはいない。長いこと、子供の遊ぶ声も聞くことはなくなった。
働き盛りの年代で、職場が都心にあれば、平日居住地域のことは関心外のことだろう。平日、駅前のスーパーへ買い物に行けば、売り場にいるのは、年配の婦人や老人、小さい子供を連れた婦人ばかりだ。夕方から夜にかけて、駅の周辺は活気付き、会社帰りのサラリーマン風の男性が、スーパーのレジに並ぶ。むしろ、駅の周辺からこの地域は、日曜祝日など休みの日の夕方が寂しい。宵闇迫る日曜・祝日の駅前は、勤め帰りの人が途絶え閑散としている。休日の夜は、それぞれ自宅で家族の団らんやTVでも見ているのだろうか。スーパーも買い物客もまばらだ。もともと僅かだった地元の商店は、殆どが廃業し店は、シャッターを下ろして久しい。郊外の住宅地と言うものは、こんなにも寂しい場所だったと思う昨今だ。今の過疎化は、60年代後半〜70年代初めに戻る感覚とは異なるものだ。人にとって、自分の生活する土地、ふるさと、自ら根を下ろす場所とは、何なのだろう。果たして、われわれ東京人に故郷の思いは、ありや、無しや? 。
今、庄野潤三を読みたいと思う読者は、ネットで検索し文庫化された僅かの著作を手に出来る程度ではないだろうか。既刊本に関して、海外の英語作家のペーパーバックの方が、まだしも入手しやすいのではないか。現代では、活躍していた作家であっても、亡くなると急速に忘れ去られるものだ。初めに面倒を厭わず、庄野がどんな作家であったか、紹介しておいたのは、そんな昨今の出版事情を考慮してだ。
2014年 9月 マンゴーハネダ