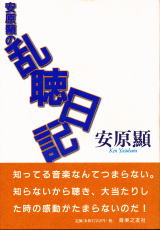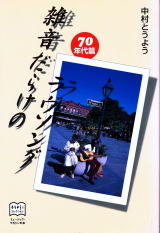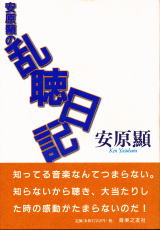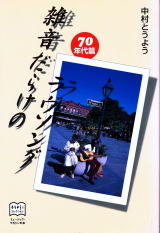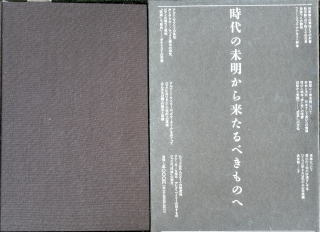リッケンばか−11−
ジャズから始める
前回、インドの地で、ビートルズとキース・ジャレットを聴いたことを書いた。今春、キース・ジャレットを連日かけ、この稿を書いていた。何時もの様に、ビートルズ始めロックを聴かない分けではない。しかし、ビートルズはパソコンで作業をしながら聴くには不向きだ。つい、手を止めて聴き入ってしまいがちだから。また、Abbey Roadと共によく聴く『赤盤』は、ベスト盤ながら一枚30分程と直ぐ聴き終えてしまう。大体、かつてLPレコードがCD化されたアルバムは、近年のCDアルバム一枚に比べて演奏時間が短い。パソコンに向かっていて、CDが終わっても入れ替えるには、手が離せない時がある。切りの良いところを見計らおうと思いつつ、一時間も経過してしまうこともある。何時の間にか音楽はなく、キーボードを叩く乾いた音だけなんてこともあるのだ。
そう言う分けで、キース・ジャレットのCDなど、一曲の演奏時間も長いものが作業しながら聴くのに最適だ。また、両手の指を使うピアノの演奏は、パソコンのキーを叩く動作−俺も両手でほぼ10本の指を使って打つ−と動作が似ているから、良い影響を与えるのかもしれない。
京都近郊に移り住んでいる実兄は、古くからジャズ・ファンだ。この春、ジャズに関する本を送って来た。ジャズに関しては、入門書から評論まで書籍化されている。あれこれ読みたいと思ってはいたが、普段聴き慣れていない音楽に関して、文章を読んでも一方の耳から片方の耳へ抜けて行くだけだ。本を読んでも、音楽はきこえない。結局、何に就いても自分の好みや趣味の世界を見つけるには、それなりの年期をかけた付き合いをして、行くしかない。
ジャズに刺激されて音楽本を紹介することにした。新書や文庫のレコード・名盤紹介など、入門クラスの本は、一度目を通せば、二度まで手にすることはないと思うものだが、思い出した様に引っ張り出して見たくなる本があるものだ。今回紹介する本は、安原顯『乱聴日記』(1999年 音楽之友社)と言う軽いノリの本だ。
皆さん、著者の故安原顯(1939〜2003年)をご存じだろうか。1960年代後半から70年代、安原が編集した本をおいらは今でも持っている。種村季弘『ナンセンス詩人の肖像』(1969年)や『ゴダール全集4 全エッセイ集』(1970年)また故・スーザン・ソンタグ二冊目の邦訳『反解釈』(1972年)など、センス抜群な本を出版していた竹内書店−今はない−の編集者だった。後に女性誌『マリ・クレール』の創刊・編集に参加し、その後は書評者−本の目利き−として一生を風靡した編集者だ。80年代末〜90年代初め、女性誌『マリ・クレール』の書評、海外文化欄をよく立ち読みした。最新の書評や音楽、映画など海外の文化情況に関して専門の雑誌があるにも関わらず。書店の店先で女性誌を手にするのは、気が引けない分けでは無かった。それでもこの雑誌の文化欄を好んだのか。それは海外の流行への眼の付け所がセンス良く、写真も豊富、エディトリアルが良かったからだ。本を始め音楽でも美術でも、総合誌や文化誌など特集形式の雑誌を長らく読んで来たが、それらは活字ばかりで立ち読みには適さない。編集者安原顯がジャズ・ファンであることは、1981年国書刊行会から世界幻想文学大系の一巻として出版された、フリオ・コルタサールの小説集『秘密の武器』(木村榮一訳)に付録された「月報」の『新ラテンアメリカ・ジャズ事情』と言う文章を読んで、薄々知っていた−「音楽なら、世代的にジャズかクラシックファンだろう」と言う−。
ちょっと話はそれるのだが、ラテン・アメリカの小説家コルタサールも、生前ジャズ・ファンだった。コルタサールは、1914年父親の仕事の関係でベルギーで生まれた。1918年、アルゼンチンへ帰り成人し、教師を職業としていたが、1951年フランスへ留学し、以後ヨーロッパを中心に執筆活動をしていた。惜しくも1984年に亡くなった。代表作に『石蹴り』(1963年)がある。この長編小説は、現代思想とパリの夜を舞台にした物語が入る組んで展開する、ラテン・アメリカのマジック・リアリズムの代表作の一冊だ。俺らは、80年代熱狂的に読んだものだ。
ラテン・アメリカの小説家で、音楽と縁の深い作家は、何と言っても『失われた足跡』の著者カルペンティエールを最初に挙げなくてはいけないのだが、コルタサールは世代的にジャズへの愛好が深いことが作品から伝わる。『秘密の武器』はそんなコルタサールの短編集で、その中の一篇「追い求める男」は、チャーリー・パーカー−1950年代に活躍したサックス奏者「バード」の異名を持つていた−をモデルに書かれた小説だ。チャーリー・パーカーに就いては、1988年にジャズ・ファンのクリント・イーストウッドが、フォレスト・ウイッティカーを主演に、伝記的作品を監督しているのが有名だ。おいらとしては、コルタサールの『石蹴り』や「追い求める男」の文体とジャズが、如何に関係しているか、興味のあるところだ。皆さんで未読の方がおられたら、是非お読みいただきたい。
『乱聴日記』を読んで、安原が高校大学にかけて、アマチュア・バンドでジャズを歌っていたことが分かり、ジャズを聴きまくる理由も分かる。そして、この本には、安原の本以外にない特徴がある。本の話題と音楽的関心が同水準で拮抗することなのだ。そして、何と音楽書の老舗出版社音楽之友社の発行だ。本に収録された文章の初出発表誌の殆どが音楽関係ではなく、書評紙や週刊誌だ。それをクラシック系老舗出版社が本にしたのは、なかなか粋な計らいだ。おれは安原が編集者時代に作った本は、今も持っている。しかし、著作と言えば、唯一この『乱聴日記』一冊しか所持していない。早いもので、亡くなって20年経ってしまったが、この人のことご存じだろうか。1997年頃、フリーになり書評やTVで本の紹介もしていたのを記憶している方もいるだろう。おいらもその姿を見知っていた。
前に申し上げたことだが、おいらは90年代半ば楽器業界誌の編集をしていた。ある日のこと、事務所前の舗道で、安原その人とすれ違ったのだ。黒縁の大きめで色の入った眼鏡にパーマのかかった髪の毛と髭、ノーネクタイの派手目なジャケット、如何にもラテン系風の風采はTVで見た通りで、直ぐその人と分かった。お茶の水駅付近の外神田と言うところだ。安原が歩いて来た方へ向かえば、湯島、手前の大通りを右に下ればS文社と言う音楽やサブカル系の本で知られた出版社もある。更に通りを下れば秋葉原に出て、角に高級オーディオ機材を展示販売する店や安原がCDを買っていたE○電気も近かった。本で知ったが、安原の自宅は上野にあって、この辺りは近所だった分けだ。だからか知らないが、入院した病院もお茶の水だったそうだ。
音楽に関してこの本は、一応「乱聴」と言っている様に、ジャズとクラシック音楽のCD購入記録−膨大な−になっている。良く知られた名盤を愛でる記述はなく、ともかく購入量で攻めまくる。また、音楽関連はもとより同時期出版された本にも触れている。CDも本も、彼氏の文章を読んでいるとこちらも、聴いて見たくなるし、読んでおきたくなるのは、名編集者による紹介だからかだろうか。フランク・ザッパに関する大著を貰い、読むや「本格的にサッパが聴きたい」なんて言う、おやじ−この時安原は60歳だ−は、偉い。クラシックに関しても、安原が評価していると、聴きたくなるから不思議だ。他に、映画や展覧会、コンサートや講演やオーディオ仲間との交友など渾然とした文章だ。
70年代半ばから80年代にかけて、おいらは山口昌男を読んだものだが、山口も本に関する文章を多数書いている。他に、演劇や音楽−おとなしいクラシック・ファンだった−に関しても触れていた。その山口が先頃亡くなったのだが、安原も内外の本を紹介していた頃の元気な山口に似てないこともない気がした。安原、山口共に、格好付けず「好きだ」と言える、心意気が気持ち良い。エンターテインメントな雑文でも、知的に読めるのだ。ただ、安原には高いテンションがあるのは、当たって、砕けて火花が散ったと言うところ。もともと学者だった山口には、なかった勢いだ。
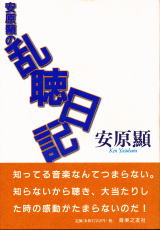
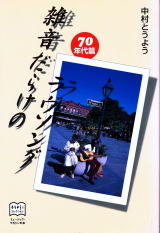
『乱聴日記』と共に、もう一冊紹介したい本がある。中村とうよう『雑音だらけのラブソング−70年代篇−』(1999年 ミュージック・マガジン社)と言う、コラム集だ。中村のこれまでに書かれた音楽に関わる文章は、それぞれ本になっている。このコラム集は、音楽からはみ出た雑文を時代で区切り、掻き集めまとめた本だ。
この二冊、おいらが参加していたビートルズの会−参加者が激減し、残念ながら無期限休会中だ−の二代目会長に、一月程貸したことがあった。本は戻ったが、肝心の感想は聞けなかった。本が会長から戻って、古い友人にも余程読んで貰おうかと思った。もっとも、以前友人に中村の本を読んだことを話した際、友人はかつて読んだことのあった中村の印象を「中・高校の社会科教師風」と評し、有り難がってはいなかった。確かに言い得てはいる。しかし、安原、中村両人とも、音楽と本に関し「仕事」と言う様な、醒めたところが無かった。友人には、未だ読んで貰っていない。会って本を渡す機会がないからだ。
安原も中村もおれは本と言えば、この二冊しか持っていない。両人とも名実共に評論家として知られているのに。中村の文章に出会ったのも遅かった。1981年、ミュージック・マガジン、J・レノン追悼号『ジョン・レノンを抱きしめて』を手にした時だ。この追悼号の編集・発行者が中村とうようだった。ここに「世界史の中のジョン・レノン」と言う論文風の文章も寄せている。この増刊号、表紙は『ダブル・ファンタジー』の篠山紀信、文章を寄せた面々は、横尾忠則から硬派な文筆家平岡正明や上野昂志など。沢田研二とかまやつ・ひろしの参加している座談会もあり、こうした異色な(?)取り合わせは、今となっては、時代−早いもので30年も経過している−を感じさせる。おいら、ビートルズ関係の参考書(ドキュメント)と言えば、唯一この増刊号しか所持して居らず「年表」代わりによく利用させてもらっているのだ。この増刊号でも、中村は、持ち前の「社会科教師」風に、ビートルズの出身地リバプールが大英帝国の港町として植民地へ向けて開いた場所と規定して、エリック・ウイリアムズ『帝国主義と知識人』『コロンブスからカストロまで』さらにラス・カサスまで引き合いに出し、白人優位主義(植民地主義)に警鐘をを鳴らしている。正に、友人の名言通り「社会科教師」の様な−過剰に教育的な−視点だった。中村の音楽に関する主要な文章は、既に本になっているが『雑音だらけのラブソング−70年代篇−』は、様々な機会に書き散らされた文章が集められている。安原と同じく、中村も展覧会−曾我簫白−からTVの批判、更に放課後、兄貴風を吹かせる如く「官憲」に絡んだことまで、日々の記録を文章にしている。こうしたコラムをまとめて読まされると、うんざりするかもしれない。しかし、こうした旺盛な社会性−お節介−があればこそ、世界の民衆音楽−民族音楽ではない−を包括的に捉える「ワールド・ミュージック」と言う考え方を、提起し、広めることが出来たのだと思う。
生前の中村も見かけたことがある。「生前」と言うのは、一昨年、中村は立川の自宅マンションから落ちて亡くなった(飛び降り自殺らしい)と言うからだ。中村の死を報じた新聞記事には、集めていた音楽関係の資料、民族楽器などを自宅から程近い「M美術大学へ寄贈した」とあった。意識して死への準備をしていたのかもしれない。そんな中村を見かけたのは、一時足繁く通った神田、神保町でのことだ。地下鉄九段下駅から神保町(本屋街)へ向かうと、先ず洋書専門北沢書店の新しいが老舗風のファサードのビルに出くわす。北沢ビル一階の北沢書店は、高い天井まで棚に洋書が並び、英文学は作家毎アルファベット順に分類されていた。他にも各国の「歴史」「文化人類学」なかには「オカルト」や「インド哲学」まで、品揃えが良かった。今、その売り場は貸店舗になっているが、このビルに(株)ミュージック・マガジン社が入っている。ある時、店舗脇の出入り口から、徹夜明けの様なさえない顔をして、中村が出てきたのを目撃したことがあった。
おれはここで、たまたま見かけたから気安く、安原とか中村と言っているのではない。また、自分も編集を職業としていた時期があるので、後輩面して、気安く呼ぶ分けでもないのだ。何たって安原、中村両氏とも実力、キャリアともに雲の上の存在だ。一般に良く知られた文筆家と言うことで、読者の特権と言うのか、親愛を込めて呼ばしてもらっているのだ。それにしても、知名度のある作家でも、亡くなってしまうと、当初はともかく一年もすれば余程のことがなくては、言及されることがなくなる。何時も思うが、そんなさばさばしていて、良いんだろうか。
ところで、おれの経験から言わしてもらえば、編集者だから一応本好きだと思うだろうが、本好きにもそれぞれ違いがあって一口には言えないものだ。中には、本に関して仕事上の付き合いだけで、余り好きではない人もいるものだ。安原、中村両氏は、むしろ例外的な存在かもしれない。おれもあるキャリアある先輩編集者から、その人の仕事−雑誌−に若い頃影響されたと話すと「あれは、仕事でやっていたから… 」なんて言われたことがある。
安原、中村の本とともにもう一冊紹介したい本がある。間章『時代の未明から来たるべきものへ』(1982年 イザラ書房)だ。この本の性格を述べるなら、右に安原顯『乱聴日記』最も左に『時代の未明から来たるべきものへ』を置き、中村とうようの本は、間の本の近くに置くと、それぞれの本の性格が分かる。
間章は、1946(昭和21)年、新潟産まれ、1978年急逝した、フリー・ジャズ評論家だ。間は、70年代フリー・ジャズやフリー・ミュージックのコンサートを企画し、その間、同人誌風のリトル・マガジンなどにジャズ評論、レコード評の執筆をした。
70年代半ば、学生時代に間の文章を見た時、バタイユやセリーヌ、ハイデカー、エルンスト・ブロッホ、或いはビート派など思想家や作家の名前がちりばめられていて驚いた。当時、ジャズ評論にしては、異色と思ったものだ。文学はもとより海外の思想書が、余程好きだったのだろう。今、間の文書を読むと、商業的な音楽に心底忌避の心を抱いていたことが分かる。俺が聴いているキース・ジャレットやロックへのシンパシーは皆無だ。
また、余りにも若くして亡くなったので、安原、中村と並べて紹介するのはどうかと思った。しかし、間もフリー・ミュージックのオーガナイザーと同時に、リトル・マガジンの編集も行い、本も良く読んでいた。編集感覚と本好き、安原、中村と共通している。
それでも、間は異様な存在だ。安原、中村両人が編集者としての仕事も文筆もライフワークとしてやり尽くした感があるのに反し、間は「志半ば」と言うのか、自らの志を遂げるまでには至らず逝去し、性格も三人三様とは言いながら、間は安原、中村に比べ、若いだけに自己主張が突出している。時代性も感じさせられるのだが、何より未完で断片的文章なのだ。そう言う「未完」で「断片的」で、出来上がることから無縁な、一種「無垢」と言うのか、若いままの主張が今だ共感を呼ぶのも、分からないではない。
しかし、俺が最も気になるところは、間がフリー・ジャズの即興演奏からか、読んでいた神秘家達の影響からか、インド音楽への関心を持っていたらしいことだ。
−《 インド音楽にしろ何にしろ(インド音楽がジャズと同じ即興演奏だと言っているのではない)即興性を有する音楽は本質的に集団音楽なのだ。即興を支えるのは血と文化と共同体の流れでありコンテキストそのものであり、それが血や民族・部族・グループによって支えられているからこそ即興演奏が具体的に了解可能な領域を持っていると言えるし、そもそもそうした背景の存在故に即興性は生まれたと言うべきものなのだ。 》−
最近『時代の未明から来たるべきものへ』が別な出版社から、同じ「黒ずくめ」の装丁で再刊された。こう言う本、今どんな人が、どう読むのか興味のあるところだ。
[追記]
この文章をここまで書いたところで、PCが故障し修理に出した。その際、ファイル、写真その他、バック・アップを確保することが出来なかった。DVDにバック・アップを書き込む機能も作動しなかったからだ。この文章は、アップ直前だったが、PCが戻って来た時には、失われていた。そこで、校正用にプリント・アウトした、ゲラから再度入力した。間の本に関する部分は、新たに書き加えた。
トップページに戻る