樂器は戀人の繪姿にも等しい。繪姿は口をきかないが、焦(こが)がれる人の心を慰める。よしや弾(ひ)かなくとも、弾き得ずとも、まだ弾く人がいないにしても、樂器ある家は何となくなつかしい。
藝術の友と心置きなく議論をするにしても、戀する人と唯(た)だたわいなく遊ぶにしても、または獨り靜かに物思ひに沈むにしても、其の室(へや)に樂器が飾られてある時は、その場かぎりに起つた凡(すべ)ての生活の斷片さへ、何となしに物優しく詩化されて、やがて來(く)べき他日の追想にも、一?奥床しい色調が加味されるような、云ひしれぬ嬉しいしい心持がする。
黙っている樂器の形は、是れを打目茂(うちまも)る自分に對して、折々音樂を聞くよりも猶豊な物思ひの樂しさを示す。
樂器は丁度魂のある人間と同じやう、其れぞれの性質によつて、それぞれの形から、いろいろ異(ちが)つた話を聞かしてくれる。
始めに掲げた文章は、永井荷風の『樂器』と言う掌編の出だしだ。ビートルズが有名にした、リッケンバッカのギターに就いて書いていて、以前簡単に触れたことのある、永井荷風『樂器』と言う随筆を、詳しく紹介しておきたくなったのだ。
永井荷風の『樂器』は、1911(明治44)年11月『紅茶の後』と言う題で「三田文学(第2巻11号)」に発表された。今この随筆は、『小品集』と言うタイトルにまとめられ、全集やわたしの持っている『荷風随筆一』(1981年 岩波書店)に収録されている。この『樂器』と言う文章は、四六判の本で漸く9ページ程のごく短い文章だ。数多い名文を残す荷風の文章にあって、この一篇は、ほんのささやかな文章と思える。それでも、楽器への思いと言うものが、荷風らしいノスタルジックで細やかな情緒でくるまれ披瀝されていて、一読すれば長く忘れがたい文章になるだろう。
この『樂器』に出会ったのは、偶然のことだった。わたしは荷風と言えば、長らく『日和下駄』を読みたく思い、ある日漸く古本市で『日和下駄』が収録されている『荷風随筆二』を入手する機会に出会った。その際、隣にあった『荷風随筆一』も、事のついでに入手しておいた。そのついでに入手した巻に『樂器』は、収録されていたのだ。
ところで『荷風随筆』と言う古本を手にしたのだが、わたしは根っからの荷風ファンと言うのではないのだ。それが荷風に興味を持った、そのそもそもの切っ掛けが、近代建築史の長谷川堯さんによる『都市廻廊』と言う評論にあり、そこで荷風の文章が紹介されていたからだった。長谷川さんは本で、『日和下駄』のことをページを割いて論じていたのだ。そこで、それまで知らなかった『日和下駄』を、どうしても読みたくなったのだった。
『都市廻廊』と長谷川堯さんに就いては、既に文章を書いているので、そちらを読んで頂こう。80年代はじめのことで、当時『日和下駄』は、未だ文庫化されていなかったのだ。荷風に関して残念ながらと言うか、現在においてもわたしは、人に読者と言う程の者ではなく、ましてファン的な読者ではないのだ。
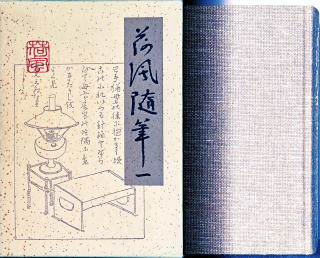
文頭に引用した一節につづいて、荷風は「細長く丈(せい)の高いカツトグラスの花瓶(はながめ)にさした薔薇(ばら)の花の一輪」の姿をさかさに映す「ピアノ」や、ペルシャ織りの絨毯が敷かれた上の長椅子に横たえられた「マンドリン」を存在をロココ調の絵画に喩えながら、それらを思い描いていると、遠くに「Seguidilla(セグイデラ)の踊りとHabanera(ハバネラ)の祭の騒ぎ」を聞く心地がすると表している。その後、続く節で荷風の語ろうとする樂器が、そうした西洋渡来の樂器ではなく、江戸情緒を連綿とする三味線と尺八であることが示される。
何度も言う様に、わたしは今に至るまで、永井荷風の良い読者では無い。それでも、『都市廻廊』以外にも、荷風に関する優れた本は、どういう分けか読む機会を得ているのだ。そうした荷風に関する研究・評論書で、残念ながら『樂器』に足を止めた記述を読んだ記憶はない。荷風としては、余りに短い文章だからだろう。それでも、そこには、荷風が生涯抱いた、新しい時代、進歩には背を向け、遠のく江戸の情緒を愛おしむ感覚、情緒の濃い文章になっているのだ。
確かに、新しければそれを良しとする時代や感性に対する批判を込めた随筆なら『日和下駄』をはじめ『江戸藝術論』で、より詳細鮮明に描き、荷風自らの思いを披瀝している。また、荷風の考え方や姿勢は、小説を始め『断腸亭日乗』によって、充分に感じとることが出来る。荷風を知るなら『樂器』の様な短い文章に、敢えて立ち止まる必要はないと言うことなのだろう。
わたしが敢えて荷風の短い文章に言及するのは、そこには楽器への憧れや慰め、センチメンタリズムが、切実に美しく語られているからなのだ。ものが豊富な現代では、そうした感覚は、全く見る影を喪ってしまった。それはまた、楽器と言わず何でも豊富で、行為の自由が行き届いた今日、なにかへの「あこがれ」と言った「あえか」な情緒は、語るに足るものではなくなってしまったのだろうか。
明治12(1879)年産まれの荷風、彼が『樂器』を書いたのは、明治44(1911)年、33歳の時だ。海外遊学を終えて帰朝し、既に3年が経過した時分に書かれた文章だ。要旨は、中学に通い始めた頃、上野の音樂学校で聴いた尺八の音に憧れ、自ら下町を歩き廻り、気に入った尺八に出会うまでの話など、既に後年の江戸散策者の姿を彷彿とさせる筆触の伺える文章と言える。未だ世紀末西欧の感覚を曳いているとは言え、少年時の尺八との出会いを語るなかに、遠のいて行く江戸情緒を愛おしむところは、既に後年の荷風の感覚が溢れた文章になっている。今し方、わたしは本棚から『樂器』を出して読んだが、この9ページの文章を読むに要した時間は、30分に満たなかった。その気になれば、誰でも簡単に読めると言うことだ。荷風の全集は大抵、市や町の中央図書館なら置いてあるはずだ。是非、読んで見て欲しい。
それにしても、荷風の情緒連綿と描く樂器へのあこがれは、わたし達現代人に、どう言う分けで、絶えて久しい感覚になってしまったのだろう。今でも同じ様な、楽器へのあこがれがあるとするなら、中学・高校の部活で吹奏楽を始めた少年・少女が学校から貸し与えられた金管楽器から、漸く自前の楽器を手にした時の晴れがましい興奮位にしか、跡を留めていないかもしれない。或いは、夏と冬休みいっぱいバイトに明け暮れ、正月に漸くエレキ・ギターを購入したバンド少女や少年の幾らか大人になった様な心持ちには「あこがれ」の片鱗は、あるかもしれない。ひとは成長し、遠い昔の己が少年・少女時代のこころは、余程の切っ掛けがなければ思い起こすことは、普通なかなか無いものなのかもしれない。大人になるとは、初心なこころの喪失に彩られているものと言うことなのだろう。最近、少女や年若い女性が自らギターをかき抱いて歌う姿がある。ギター類は、その広がりから、今や特別な楽器ではなくなっている。ガールズ−少女ばかりの−バンドを目にする度、そう思うのだが、どうだろう。ギターは比較的手にし易い。しかし、バンドでもやらないとベースやドラムは、なかなか個人が持つことが無い楽器だ。それにしても、以前も申し上げたが、大抵の場合、音楽好きだからと言って、自ら楽器を手にしない人の方が、圧倒的に多いものだ。
楽器らしいものとなれば、何によらずCD一枚に比べ高価である。トランペット、サックス、フルートなど金管楽器は、新品なら100万円を超えるものも珍しくはない。当然、楽器店には状態の良い中古品も用意されている。それでもものにより、数十万円はするものも少なくない。しかしながら、車や海外旅行に比べてみると、とんでも無く高価と言う分けではないと言えるのだ。確かにギター類など、アコースティック・ギターの有名ブランド品は、手作業で作っているから高額になるのだ。エレクトリック・ギターでもギブソン、フェンダーの輸入楽器は、近年の円安で価格、は高止まりしている。一方、エピフォンの様なアジア地域で製造しているギターなら、DCブランドのジャケット一着にも満たない金額で充分賄える。現代日本の社会の様に、比較的裕福な社会では、ピアノの様な高価で嵩張る楽器以外なら、大抵の楽器は成人が望むなら手に出来ないことは無いと思うのだがどうだろう。1970年代には、エレキギターを手にすると「不良」と言われたものだ。さすが現在では、その様なことは言われなくなった。
わたしのところには、リッケンバッカのギターの他にエピフォンのギターにベースがある。アメリカ製のリッケンバッカに比べ、エピフォンは韓国で製造され、エコノミーな値段ではある。それでも、ダイソンのクリーナー位はするのだから、弾きもせずインテリアの為だけに、買う者はいないのだろう。ダイソンの掃除機なら日常役に立つだけでなく、誰でもその機能を遺憾なく発揮させることが可能だ。ギターやベースは日常の役には立たないだけでなく、一応弾ける人でなければ、本来のギターとしての音を出すことすら叶わない。住宅広告で部屋の片隅にギターが立てかけてある広告写真があるが、ミニマリズムが言われる現代では、弾けなければギターは、インテリアにするどころか、即古道具屋に売られてしまうことだろう。
わたしはこれまでの出会いで、人によっては上手くギターを弾ける人でも、日常生活の場で、ギターを自由に弾けないと言う、意外な事実を知っている。あるセミプロ・バンドのヴォーカル兼サイド・ギタリストの男性は、家ではエレクトリック・ギターをアンプリファイせず弾いていると言うのだ。特にアコースティック・ギターを弾くと「音が大き過ぎる」と、奥さんが飛んできて、近所迷惑だから「止めてくれ!」と言われるのだそうだ。
確かに、エレクトリック・ギターはアンプリファイしなければ、弦の振動だけでギター音はしない。アコースティック・ギターの方が、生音なら断然大きな音がする。故にエレキ・ギターは、バンドのリハーサルでスタジオを借りた時しか、自由に音をだせないのだそうだ。何より、一般に楽器が広がらないのは、弾けないにも関わらず、高価な楽器を持つことへの遠慮があるからだろう。荷風の『樂器』では、「楽器は音が出なくとも、日常の、家の片隅に、あるだけでこころ慰め、ゆたかに」してくれると言うのだが。
物質的には豊かになりながら、精神的に空虚なわたし達には「こころ慰め、ゆたかに」なると言うことが、意外に難しいことが分かる。恐らく、楽器と言うもの、例えばエレクトリック・ギターを格好いいと思っても、弾きこなせない者が持っていても仕方がないものと思っているのだろう。楽器に就いてあらためて思えば、普通の社会人で楽器を自由に弾きこなす人は、やはり多くない。何故、そうなのかは分かっているのだ。
わたしも小学生の頃より音楽は聴くだけで、自ら歌うことも、何か小さな楽器を奏でることも出来ないで来た。わたしが6年生の夏まで通っていた小学校の鼓笛隊は、都や区の大会に参加し、好成績で知られていた。音楽を担当するYと言う男性教師は音楽の授業はもとより、放課後も鼓笛隊の練習を熱心にしていた。特に、鼓笛隊の太鼓や鉄琴担当の生徒を選抜するについては、音楽授業の成績や生徒の性格など細かく審査して決めていたのだ。鼓笛隊に選抜されない大半の生徒は、縦笛で行進の練習に参加させられるのだった。Yと言う音楽教師は、自分の教育実績の為に、生徒にやりたくもない楽器演奏や行進を強要していたのだった。
わたしが小学生だったのは、1960年代の中頃だ。その頃、一クラス50人に近い生徒がいた。既に、戦後のベビー・ブームは終わってはいたが、未だ社会に子供は大勢いて、人権と言う意識未だ低かった時代だ。現在の様に子供の人権への配慮は、薄かった。小学校の教師と言わず、社会的な地位が人格の高低の基準の如く錯覚された時代でもあったのだ。
わたしの学校嫌いは、そうした体験によっている。音楽が教育の一環に利用され、あまつさえ音楽教師の見個人的栄達、見栄の道具にされ、未だ幼いこころに演奏を強要されていたのだ。不幸中の幸いは、音楽を聴くことまで、嫌いにならなかったことだ。
その頃、わたしが最初に買ってもらったレコードは『大脱走』や『史上最大の作戦』のテーマ曲の収録されたドーナツ盤だった。小学校の5年生頃、スティーブ・マックイーン主演映画『大脱走』を観て、そのテーマ曲を聴くと映画の情景が目に浮かんだのだった。それが、中学の運動会でわたし達生徒の入・退場の行進曲に利用されるに及んで、一時全く聴く気が失せたのだった。それにしても、教育関係者は、勝手に運動会等で、既成の曲を生徒の行進になど、勝手に使わないで欲しい。
長じて、大学に入学した頃、当時お付き合いした女性が音大出身だったことで、散々クラシック音楽を聴く様になったこともあった。その彼女と別れると、別に音楽まで嫌いになった分けではないが、クラシックは、殆ど聴かなくなった。それでも近年、グレン・グールドのピアノ演奏によるバッハを聴いたり、ベース・ギターでバッハのフレーズ−タブ譜があるのだ−を弾く一時は、こころ安らぐものがある。
楽器の世界
そう言う分けで、わたしは長らく自ら楽器を手にしようなどとは、思いもせずに来た。1980年に社会人になってから、当時、高度成長期のまっただ中、多少の小遣いは自由が利いた。しかし、とてもアメリカ製のエレキ・ギターなど、手にする余裕は無かった。多分、わたしと同世代は、皆同じ様なことではなかったかと思う。
社会人になり最初、わたしは渋谷の画廊に勤め始めた。当時、勤め先の画廊の周辺は、マンションがあるだけの閑静な住宅地の中程にあった。そんなかつての勤め先の一角が、現在プロなど出入りする専門的なギター・ショップから量販店まで、何と一区画に数店舗が集まって、地域の楽器店街をなしているのだ。
長らく楽器には縁がなかった分けだ。その気持ちに変化が生じたのは、40歳になり偶然楽器業界誌編集の仕事が、舞い込んで来た時だった。この時の仕事は、楽器は勿論のこと、社会人の趣味や趣向と言うことを考えさせらた。わたしには、願っても無い仕事だった。その楽器業界誌は、戦後の復興期に創刊された伝統ある業界誌だった。仕事を始めると、近年言われている様な「少子高齢化」と言う時代の波をうけ、廃業寸前の時期を迎えていることが分かった。戦後最初の楽器業界誌は、数年後廃業し、無くなった。そんな楽器業界誌の仕事を経験しなければ、楽器を考える切っ掛けも、エレキ・ギターを手にすることもなかったと思っている。
戦後高度成長期は、調度わたし達世代の少年〜青年期と重なる。少年時代、裕福な家の子供−上昇志向の強い家庭の−は、ピアノやバイオリンを習わされていた。わたしが中学生の頃、夕飯前の一時、家の近所では良く、どこからともなくピアノの音が聞こえて来たものだ。普通の家庭でも、アップライト式のピアノのある家があったのだ。ピアノやバイオリンを習うだけではなく、複数の子供が電子オルガンを使いながら行う音楽教室も、各所に見られたのだった。現在、音楽教室と言えばシニア向けになっている。何とも隔世の感である。
ピアノと言えば、近年のTVクラシック音楽のコンサートを見て分かった。殆どの場合演奏で使用されているピアノが、スタインウエイ社のコンサート・ピアノを使用しているのだ。言うまでもなく、日本にも世界に誇るピアノ・メーカーがあるにも関わら。多分国産ピアノより高価な外国製ピアノをホールに据える様になったのは、各所にコンサート・ホールが建設された、バブルの時代以降からではないかと思っているのだが。
ポピュラー音楽を聴く場合、どんなメーカーの楽器を用いて演奏されているかは、普通意識したりはしないものだ。こんなことに疑問を抱くのは、わたし位かもしれない。それもこれも、楽器業界誌の仕事をした経験がもとにあるからだ。
楽器業界誌の仕事をしていた、ピアノと言う楽器を意識させられた体験があるので、お話ししておこう。楽器業界誌の編集室のあった建物は、楽器組合のビルディングで、その楽器組合とは、大きく製造、卸、販売と三つに分けられていた。
ある時、販売・卸部会の浜松研修旅行があるので、プレスとして取材をするため参加したこがある。参加して初めて分かったが、年に一度行われる研修旅行は、研修と名が付いてはいるが、業者の慰安旅行を兼ねたものだった。参加の楽器店も都心で若者を集めている様な有名量販店から、学校教育の場に楽器や音楽教材を提供する地場の小規模な老舗楽器商とまちまちだった。有名量販店からは、ビジネスマン風の社長や店長が来ていた。小規模な楽器商からは、現在一線を退いた先代の年配経営者の方も参加し、慰安旅行として楽しみにして来た様子が見て取れた。
その研修旅行で、浜松のスタインウエイ社製ピアノのレストアとメンテナンスを専門にしているピアノ工房を訪ねたのだった。そこは木造平屋の古い保育園の園舎の様な建物に、小講堂の様な主屋の床には、厚い鉄板が敷かれ、メンテナンスを終えたスタインウエイ製の様々なタイプのピアノが、20台ほど良好な状態で並んでいた。
案内係の技術者は、若い作業員を傍らに立たせ、純正部品と他者の同じ部品をそれぞれ鉄の床に落とし、金属音の違いを聴かせてくれた。真鍮は大まかに言えば銅と錫の合金だが、銅と錫の割合により、黄色味も微妙に異なる。見てくれだけでなく振動の伝導も違いが出る。それにより、ピアノ全体の音にも違いが出て来るだろう。スタインウエイ本来の音を追求することから、そこでは、部品の交換をする場合、わざわざスタインウエイ社から純正部品を取り寄せているとのことだった。
ピアノと言う楽器は、大まかに言えば、木で作られた箱と、その内部に分けられる。箱の内部には、鋳鉄で作られた共鳴器に鉄線が張られ、鍵盤を叩くとそれがハンマーに伝わり、張られた鉄線を叩くことにより音が出る。鍵盤からハンマーへ伝わり、鉄線を叩き、その振動が共鳴器と全体を包み込んだ木棺まで振動し音がする仕掛けだ。故に、木棺(ボディ)の木質、内部の鋳鉄の素性などが、その音色に大きく関わることが、分かったのだった。
スタインウエイ社のピアノが広く知られている一方で、あるピアニストがベーゼンドルファーと言うメーカーのピアノを、好んで使用することに気が付いた。
ある時、ベーゼンドルファーを好む演奏者−加古隆、山下洋輔それに穐吉敏子ら−がいて、理由を述べていた。それは、ピアノの鳴りが、より木質のナチュラルな感覚−スタインウエイに比べ−が、あるからとのことだった。
なお、ビートルズ映画LET IT BEでは、ポール・マッカートニーがブリュートナー(BLUTHNER)のピアノを弾いている。前に紹介したTHE BEATLES` SOUNDによれば、初期ロックンロールで伴奏に使われたピアノは、スタインウエイだったそうだ。スタインウエイの方は、恐らくアビーロード・スタジオ備え付けのピアノだったのではないだろうか。ビートルズは1968年、自らのレーベルとしてアップルを設立し、自分達のスタジオを持った。その時に選んだピアノが、ブリュートナーだったのかもしれない。
浜松と言う土地が出たので、次いでながら、もう一つ申し述べておけば、日本の楽器(ピアノ)生産地として知られている浜松市は、ご存じの様に、自動車・オートバイの生産地としても知られている。日本を代表する楽器メーカーが、オートバイのブランドとしても、世界的に知られていることを思い起こして頂きたい。わたしのバイクも、そのY社のものだ。浜松が、楽器取り分けピアノの生産地となったのには、自動車やバイクのエンジンをはじめとする金属加工、特に鋳物の成形技術が地場の産業としてあったことと関係が深い。
先にピアノの組成で述べた、内部の共鳴器こそ鋳物の技術が必要だからだった。更に、ピアノの木棺を作る木工と材料になる木材の産地が周辺−例えば、木曾川中流域(Y・ギターのある可児市)や天竜川上流の長野県側−にあることもピアノ製造の条件に適っていたからでもある。
むかしの達人(音楽家)
今回、最初に永井荷風『樂器』出だしを引用して、始めた。こう言う機会もそうは無いので、他に音楽、楽器と縁のある、わたしの好きな文章を引用したいと思う。その文章は、鴨長明による『発心集』所収の逸話だ。
その鴨長明と言えば『方丈記』の作者として、現代でも知られている。その『方丈記』は、3.11以来、災害の状況を生々しく描いたルポルタージュ文学として注目され、今日的な本として話題にもなっている。鴨長明の生涯に関して、今年5月、鈴木貞美『鴨長明−自由のこころ』(筑摩新書)が、刊行された。長明に就いて伝記的に詳しく知りたい方は、容易く知ることが出来る様になった。
鴨長明は、久寿2年(1155)産まれと言うのが、現在定説になっているそうだ。健保4年(1216)62歳で没したと言う。名字の鴨氏は、下賀茂神社の神職の家系から来ている。長明はもともと新古今集に選せられた歌人であった。数多い中世歌人のなかで、位階は必ずしも高くはなかった。それでも、新古今集を勅撰する後鳥羽上皇の推挙もあり、生前は気鋭の歌人として知られていた。歌人長明は、当時から楽人としても知られた者であった。自ら琵琶を製作する程だったことも記録にあると言うことだ。ことに長明隠棲の切っ掛けとして、琵琶の秘曲をかってに演奏して物議を醸したことは、異伝として伝わっている。
歌人で楽人であった長明だが、今日われわれにとっては、歌人や楽人と言うより、長明は『方丈記』の作者として知られる存在と言うことになる。わたしがその『方丈記』を知ったのは、高校生の中頃、堀田善衛『方丈記私記』を読んだことが切っ掛けだった。それを切っ掛けに、唐木順三『中世の文学』(1955年 筑摩書房)等の古典文学に関する評論を好んで読んだ。もっとも『方丈記』を別にすれば、唐木などの評論で論じられている古典作品を、自ら読みはじめたのは、漸く近年のことになるのだ。
古典文学の中でも『方丈記』は、近年火災や大風など中世にあった災害をルポルタージュした文章として注目されていることでも分かる様に、古典としても現代のわたし達にも読みやすい文章なのだ。岩波文庫本を始め他の文庫もあり、何時でも読むことが出来る古典だ。
近年、わたしは『方丈記』の著者である鴨長明個人への興味も膨らんで来た。それと重なる様に、実兄が京都市外山科に近い地に住するに及んで、長明が実際に庵を結んだ場所が近いことを知り、一層惹かれる様になった。
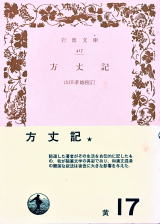
さて、その鴨長明には『発心集』と言う、如何にも中世らしい乱世の意識を映した仏教説話を集録した書物があるのだ。仏教説話と一口に言っても『発心集』は、『方丈記』の著者で隠棲者として知られる鴨長明らしく、信仰、仏の世界への希求から異様なまで身をやつす僧侶や上層階級の人々と、中世人の信仰に絡まる奇異な逸話を集成した書物になっている。
その『発心集』のなかに樂器と音樂に関わる話 <永秀法師、数寄の事>と<時光・茂光、数寄天聴に及ぶ事> の二つが集録されている。ここでその二つを紹介したいと思う。しかし、その前に『方丈記』後半−五−の一節を是非とも引用しておきたくなった。短い節なのでお読み頂きたい。
いま、日野山の奥に跡をかくして後、東に三尺余の庇をさして、柴折りくぶるよすがとす。南、竹の簀子(すのこ)を敷き、その西にあかだなを作り、北によせて障子をへだてて阿弥陀の絵像を安置し、そばに普賢を掛(か)き、前に法花経を置けり。東のきわに蕨のほどろを敷きて、夜の床とす。西南に竹のつり棚を構へて、黒き皮籠三合を置けり。すなわち和歌、管絃、往生要集如きの抄物を入れたり。傍らに、琴琵琶各各一張をたつ。いわゆるをり琴つぎ琵琶はこれなり。
山田孝雄校訂の岩波文庫旧版『方丈記』により、行間に附された漢字を活かして引用してみた。『方丈記』を引用したのは、むかしの人が楽器を如何様に取り扱っていたのかを、具体的に書き残してくれていたからなのだ。
先に長明が秘曲を演奏した逸話に触れたが、それは『文机談』と言う書物にあるそうだ。それによれば、鴨長明は音樂仲間の集まりで「秘曲づくし」をした際「啄木」と言う秘曲を、故意にか、悪乗りしてか、弾く資格無く弾いたことで、楽所預(がくしょあずかり)は後鳥羽院に上訴したと、書かれていると言う。秘曲は許された名手のみ演奏が許されるのだが、長明は許されていなかった。演奏するのに資格云々とは、まるで現代の著作権法以上に堅苦しい話だ。ともかく、秘曲が演奏が出来たと言うことは、秘曲の中身を知ってはいたことになる。
それはそうと『方丈記』と言えば、方丈−四角い−庵を結ぶ隠棲を言うのだが、こうして引用してみると、現代における独居人と差ほど変わらないことが分かる。琴、琵琶を「一張(いっちょう)」と数えているが、多分弦を張った楽器だからであろう。ここから今日に言う「一丁」や「一挺」が始まったのかもしれない。
また「をり琴つぎ琵琶」とは、新潮日本古典集成 方丈記 発心集(三木紀人校注)の頭注によれば<ともに携帯用の独特の楽器らしいが詳細不明。あるいは長明自身の考案・作成によるものか>と、ある。長明は出家した際、長明が自ら藤を薄板に削り、貼り合わせた手製の琵琶「糸竹」を、後鳥羽院に献上している程なのだ(鈴木貞美『鴨長明−自由のこころ』)。そう言うことから、長明が自分用の楽器を自作した可能性は大きい。現在も三味線など胴と竿に分解して携帯することなどから、琵琶や琴も分解したのだろう。なにしろ、鴨長明と言う人は、方丈の庵も分解して移動が可能な様に、自ら考案した位の者なのだから。
なお、琵琶の糸巻きがある部分(ヘッド)を「天神(天神)」と言う。楽器業界誌の編集者をしていた際、社長が社にクラシック・ギターを持ち込み、器用に弾いていた。ある時、ギターのヘッドを指して「天神」と言っていたのを思い出す。
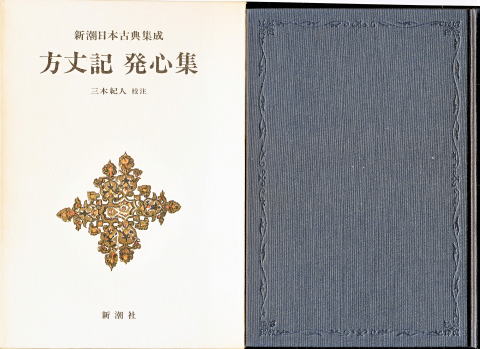
さて、『発心集』から引用して見よう。はじめは、第六の七 永秀法師、数寄の事
八幡別当頼清が遠流にて、永秀法師と云う者ありけり。家貧しくして、心すけりける。夜昼、笛を吹くより外の事なし。かしかましさにたえぬ隣り家、ようよう立ち去りて後には、人もなくなりけれど、さらにいたまず。さこそ貧しけれど、おちぶれたるふるまいひなどはせざりければ、さすがに人いやしむべき事なし。
頼清聞き、あわれみて使ひやりて、「などかは何事ものたまはせぬ。かように侍れば、さらぬ人だに、事にふれてさのみこそ申し承る事にて侍れ。うとくおぼすべからず。便りあらん事は、憚らずのたまはせよ」と云はせたりければ、「返す返す、かしこまり侍り。年来も申さばやと思ひながら、身のあやしさに、且は恐れ、且は憚りてまかりすぎ侍るなり。深く望み申すべき事侍り。すみやかに参りて申し侍るべし」と云ふ。
「<頼清は>何事にか、よしなき情けをかけて<しなくてもよい同情をして>、うるさき事や云ひかけられん」と思えへども、「彼の身のほどには、いかばかりの事かあらん」と思ひあなづりて過す程に、ある片夕暮に出で来たれり。則ち出で合ひて、「何事に」など云ふ。「あさから所望侍るを、思ひ給へてまか過ぎ<そのことを考え続けて>侍りし程に、一日<先日の>の仰せを悦びて、左右なく参りて侍る」と云ふ。「<頼清>疑ひなく、所知<地所>など望むべきなめり<希望するに違いない>」と思ひて、これを尋ぬれば、「筑紫に御領多く侍れば、漢竹の笛の、事よろしく<上等なのを>侍らん一つ召して給はらん。これ、身に取りてきはまれる望みにて侍れど、あやしの<いやしい>身には得がたき物にて、年来えまうけ侍らず<入手できません>」と云ふ。
思ひの外に、いとあわれに覚えて、「いといとやすき事にこそ。速かに尋ねて、奉るべし。其の外、御用ならん事は侍らずや。月日を送り給ふらん事も心にくからずこそ侍る<心にかかっておりますが>に、さやうの事も、などかは承らざらん」と云へば、「御志はかしこまり侍り。されど、其れは事欠け侍らず。二三月に、かく帷一つもうけつれば、十月までは、さらに望む所なし。又、朝夕の事は、おのずからあるにまかせ<たまたま手近にある物を利用して>つつ、とてもかくても過ぎ侍り」と云ふ。
「げに<なるほど>、すきものこそ」と、あわれにありがたく覚えて、笛いそぎ尋ねつつ<探し求めて>送りけり。又、さこそ云へど、月どとの用事など、まめやかなる事どもあわれみ沙汰しけ<生活のことなどを心配して物資を整えてやると>れば、其れが有るかぎりは、八幡の楽人よびあつめて、これに酒もうけて、日くらし楽をす。失すれば又、只一人笛を吹きて明し暮しける。後には、笛の功つもりて、並びなき上手になりけり。
かようならん心は、何につけてかは深き罪も侍らん<一体どんなことに関して深い罪を犯すんでしょうか>。
次いで、同じ第六の八 時光・茂光、数寄天聴に及ぶ事を引用してみよう。
中比(なかごろ)、市正(いちのかみ)時光と云う笙(しょう)吹きありけり。茂光と云う篳篥(ひちりき)師と囲碁を打ちて、同じ声に裏頭楽(くわとうらく)を唱歌(しょうが)にしけるが、面白く覚えける程に、内よりとみ<急用で>の事にて召しけり。
御使ひいあたりて、此の由を云ふに、いかにも、耳にも聞き入れず只もろともにゆるぎあひて、ともかくも申さざりければ、御使ひ、帰り参りて、此の由をありのままにぞ申す。いかなる御いましめかあらんと思うほどに、「いとあわれ<見事な>なれる者どもかな。さほどに楽(がく)にめでて、何事も忘るばかり思ふらんこそ、いとやむごと<尊いことだ>なけれ。王位は口惜しきものなりけり。行きてもえ聞かぬ事」とて涙ぐみ給へりければ、思ひの外になむありける。
これらを思へば、此の世の事思ひすてむ事も、数寄<風雅の心>はことにたより<方便>となりぬべし。
カッコ内は読み、<>内は現代語の意味を添えておいた。これだけあれば、そのままお読みになっても、充分文意は理解して頂けるのではないだろうか。現代に活きるわたし達は、中世の数寄者楽人の脳天気な生き方をどう感じるだろう。案外明日のことなど心にかけない生き方は、生活のストレスや悩みとも無縁で、良い人生が送れそうにも思える。何処かに、必ず数寄を「やむごとない」こととあわれんでくれる者がいて、何かと援助をしてくれないとも言えない。
どうだろう、こうして直に読んで見ると、文章にある人物の存在は、中世と言う古い時代を忘れさせ、その生き方には、共感と言うのか不思議と親しみを覚えさせられる。そして、彼らの熱中していたとうの音楽がどんなであったか、聴いて見たいと言う気持ちが湧き上がる。
以前、服部龍太郎著『日本音楽史 伝統音楽の系譜』(1974年 社会思想社)を読んだが、文章からは音楽を知ることは出来ない。また、長明が熱中した音楽がどの様なものか、更に中世に秘曲とされた楽曲が、どの様なものであったか、何か知ることは(今のところ)出来ずにいる。また、小中村清矩著『歌舞音楽略史』(1984年 岩波文庫)は、上代に大陸から渡って来た音楽に関して詳しい。残念ながら、中世に入ると能楽と平家の語りものが採り上げられているだけだ。
今回、中世の音楽と言うことから、岩波書店日本思想大系23古代中世藝術論(林屋辰三郎編 1973年)と東洋文庫所収『新猿楽記』(川口久雄訳注 1983年 平凡社)を思いだし、書架から出して見た。この『新猿楽記』は、成立が王朝期末、鴨長明の生きた時代から2世紀も前の時代に成立した、漢文による書物だ。この『新猿楽記』では、王朝期末の世態風俗を事細かに描かれている。最終章に当時の音楽家−雅楽寮の養子−が登場するのだが、そこでは、笙、篳篥など笛に太鼓や鼓など、打楽器楽類が列挙されている。更に、当時雅楽寮で奏されていた舞楽−音曲には必ず、舞が伴っていた様だ−を挙げて、中には「青海波」と題された曲は、インド起源であることが注されている。舞楽は現在も雅楽寮で伝えられているので、王朝期から二百年後の中世の音楽を偲ぶよすがになるやもしれない。なお、大系本には『教訓抄』と言う雅楽家の家伝で、中世に於ける雅楽と雅楽士のことが詳細にするされている。今回、読み始めて見たが、先に進むことが出来ない。
今日、永秀法師や時光・茂光の消息は、杳として知ることは出来ない。当然、彼らの、また鴨長明らが奏していた音楽がどの様なものか、わたし達には、皆目分からないのだ。長明は歌人であったから、彼の和歌は残って現在でも読むことが出来る。その長明は、歌人と同時に音楽家でもあったことも知られている。文字に残る和歌と異なり音楽は、奏でられればたちまち消える。当然、今のわたし達は聴くことが出来ない。思えば、不条理なことだ。
2016年 秋 マンゴーハネダ
トップページに戻る